北條和馬の写メ日記
-

SNSは楽しんでナンボ:自分で楽しまなければ継続できない
-
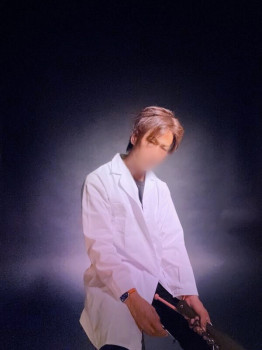
なぜ夏は「怪談の季節」なのか:そこには歌舞伎が関係している!?
-

品のあるテーブルマナーを心得よ:一緒に食事をして恥ずかしいと思われないように
-
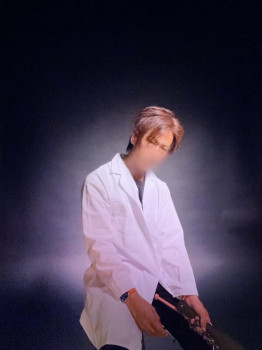
睡眠は体のメンテナンスに必要:寝ている間に体が回復する
-

人間関係の距離感はとても大切:近ければ良いというわけではない
-
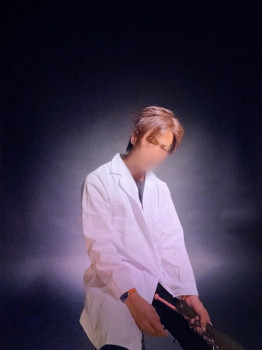
海外の人が魅力を覚える「お弁当」:bentoは海外でも通じる単語
-

顧客情報をしっかり管理していますか?:絶対に漏らしてはならない
-
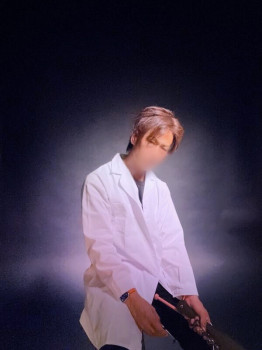
高速道路で出口を間違えてしまったら?:スタッフに申し出よう!
-

キャストが主導権を握ろうとしてはならない:女性がキャストを選ぶ
-
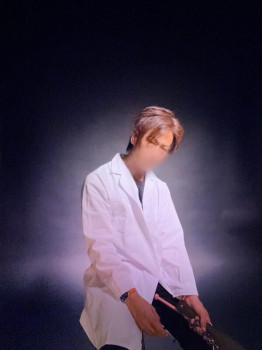
お茶がなかなか売れない!?:そんな時に伊藤園が考えた営業方法
-

SNS上の人間関係に振り回される必要はない:自分を大切にしてくれる人の存在
-
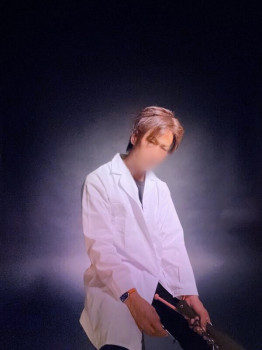
缶入りのお茶の開発には10年かかった!?:缶のお茶が開発されるまでの課題
-

キャストはカメレオンであれ:女性が求めるものを提供してこそ
-
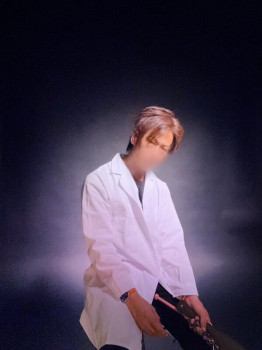
お香の始まりとは:淡路島に流れ着いた枝こそが…!
-

基準から逸脱した状態は当たり前ではない:ルールには理由がある
-
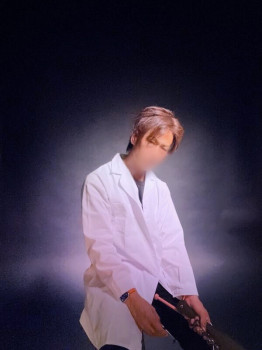
「ワクチン」という言葉はどこから来た?:予防接種の先駆けとなった大発見
-

女風は苦しむ場所ではない:心を解放させ、ストレスを発散し、楽しむ場所である
-
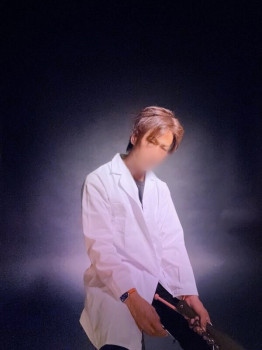
「い抜き言葉」はカジュアルな言い回し:置き換えられる言葉
-

キャストの仕事は誰でも始められるけれど:毎日しっかり向き合う必要がある
-
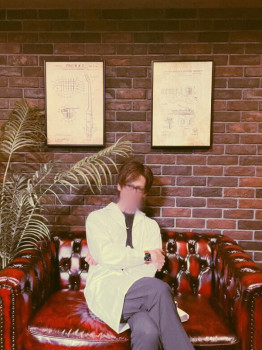
本来の意味、きちんと理解できていますか?:「敷居が高い」における行きづらい理由
-
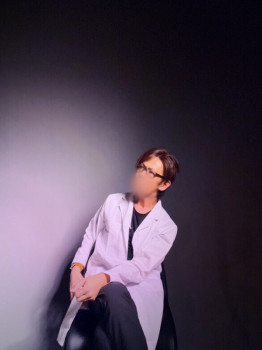
キャストの仕事は勝ち負けではない:キャストとして1番目指すところとは
-
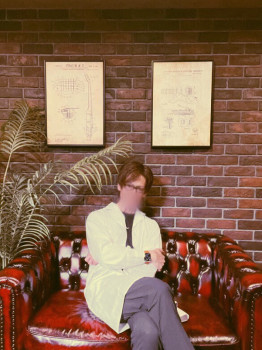
本来の意味、きちんと理解できていますか?:「役不足」と「力不足」
-
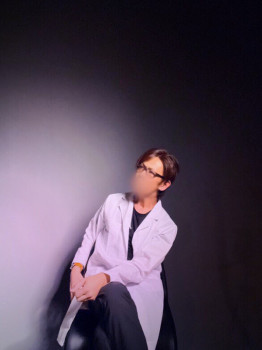
年齢で何かを諦める必要はない:様々な経験を重ねて周りの声に耳を傾けられる余裕
-
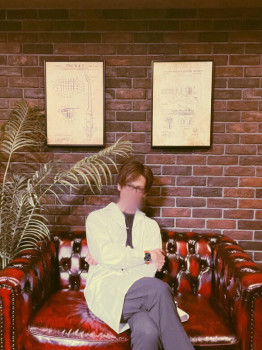
2025年の節分は2月2日!:恵方巻の由来と食べ方について
-
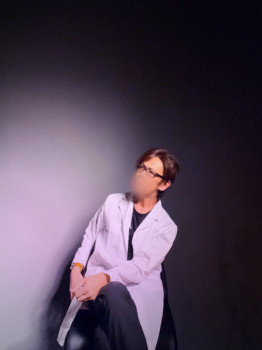
体調管理も仕事の1つ:お客様との約束の時間に穴を開けないように
-
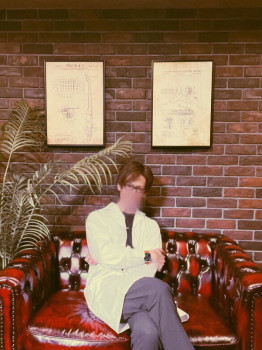
巻き寿司の由来:華やかな庶民文化とともに広がった日本文化
-
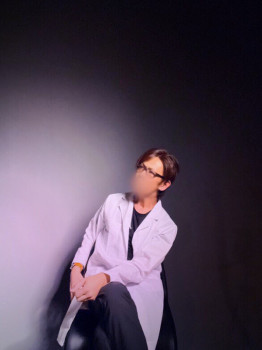
Xっておもしろい:わかった気にならず、常に模索する意識を持つ
-

冬はつとめて:「枕草子」に出てくる冬の早朝の風情に思いを馳せて
-
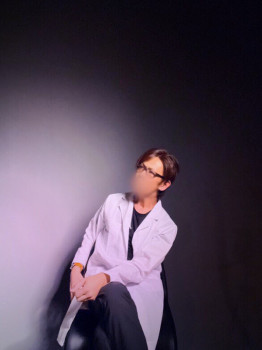
日本人がサードプレイスを持ちにくい理由:それを女風が克服するために
-
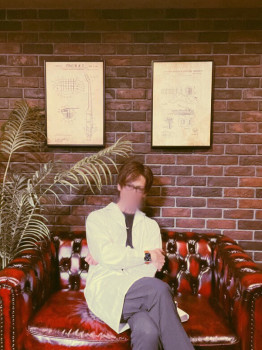
日本の国民食であるカレーはどのように広まったのか:物事は変化していく
-
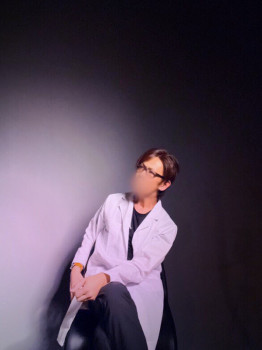
サードプレイスがもたらす効果3選:キャストはそれを提供するエンターテイナー
-
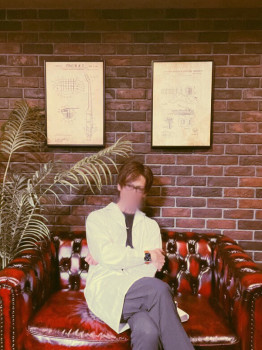
「詫び寂び」とは?年が経つにつれて生じる変化をプラスに捉える
-
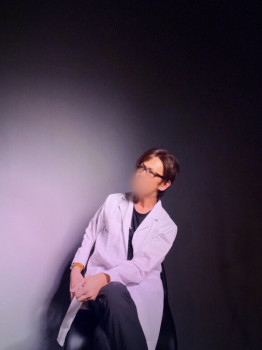
自らの力を過信しない:「盛者必衰の理をあらはす」
-
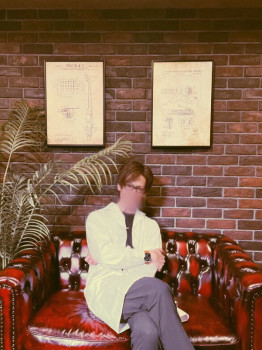
れ足す言葉も誤用表現である:ビジネスではしっかりとした言葉を
-
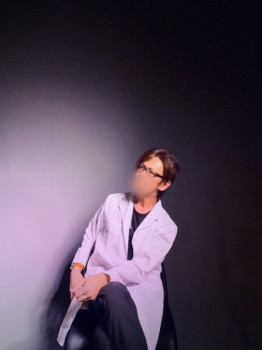
サードプレイスとしての女風:潤滑油としてストレスを解消できる場所
-
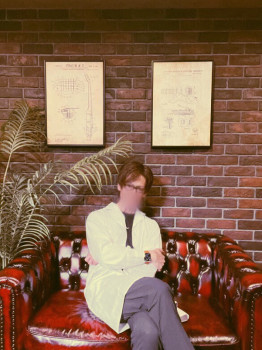
「ら抜き言葉」はビジネスでは恥ずかしい?:実はもともと若者言葉だった!
-
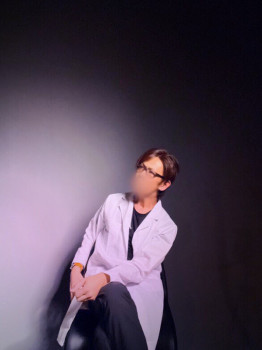
行動に移す前に考えることも大切:考えてばかりではいけないけれども
-
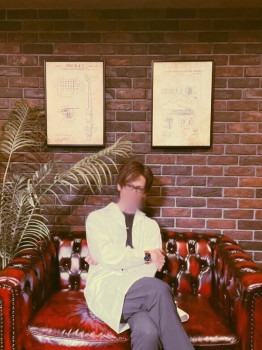
「すみません」が謝罪の意味を持つ理由とは?:ビジネスでは適切か
-
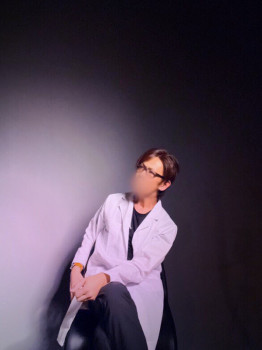
女風はネットビジネス:どれだけ先を読んで考えられるかが重要
-
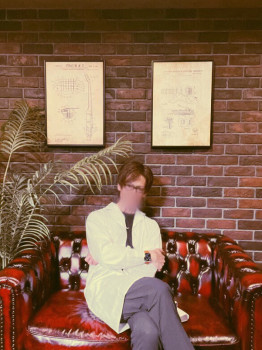
日本人が毎日お風呂に入る・入れる理由とは:日本人のきれい好き
-
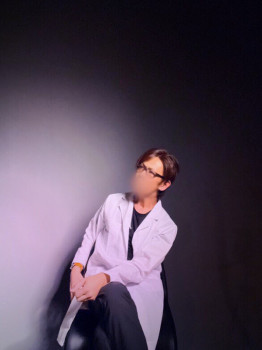
忙しい時こそ、人と話す機会をしっかりと儲ける:多忙を理由にスルーしない
-
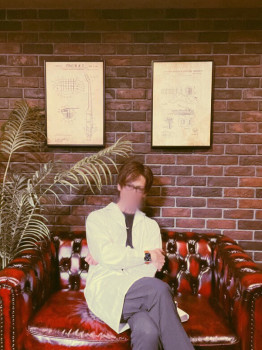
日本のディズニーが成果を叩き出した3つのビジネス戦略:7年間で2.5倍の売り上げ
-
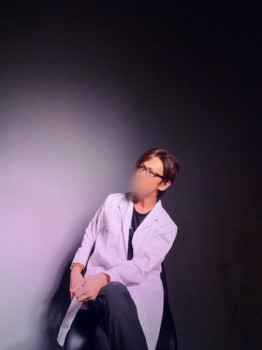
「おもてなし」の言葉の由来:当たり前のことをきちんとすることが大切
-
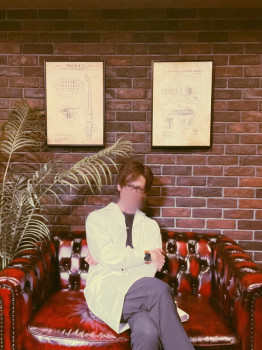
最先端の技術が最善とは限らない:新幹線の技術が保守的な理由
-
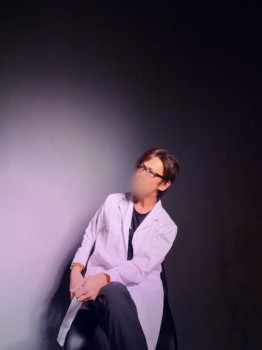
向上心よりも「変わろうとする気持ち」があるかどうか:人の意見を受け入れる
-
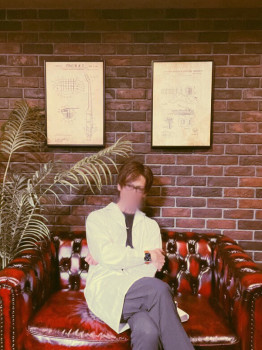
新幹線の走行を可能にした4つの技術:なぜあれだけ快適なのか
-
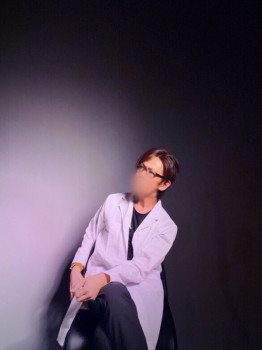
やる気の出しすぎに要注意:気持ちに余裕を持てるように
-
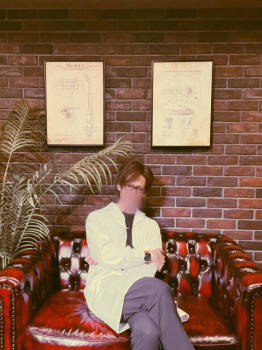
人を労う優しい言葉:「おはよう」はもともとどういう意味なのか
-
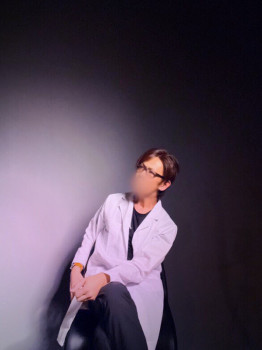
待っているだけでは成功できない:自分から積極的に行動する
-
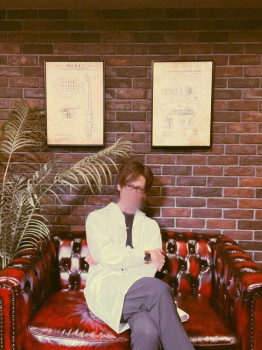
東日本大震災で情報収集を助けたSNSツール:Twitter(当時)の力
-
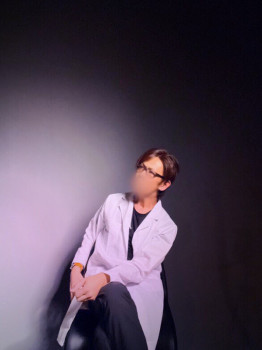
デジタルデトックスの大切さ:気分が落ちたらXから離れてみる
-
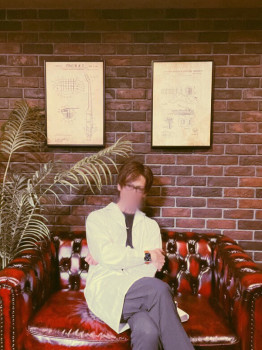
空港コードはどうやって決まった?:その背景や由来
-
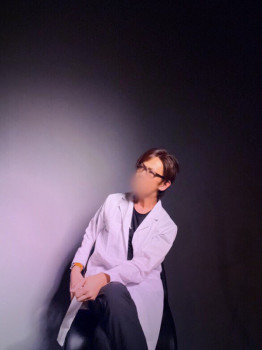
新人はまだその存在を知られていないと心得よ:まずは知ってもらうことから
-
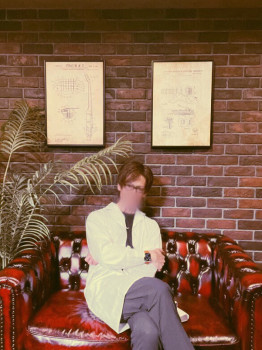
日本語での呼び方、実は海外では違う?:海外では通用しない呼び方
-
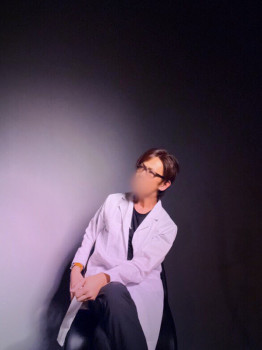
問題が生じたら、筋違いな方向に進まないように:本題に特化する
-
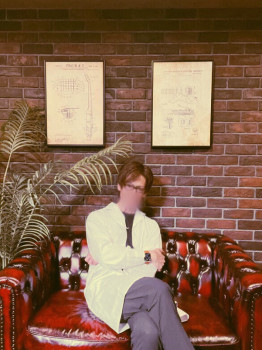
日本の学校で生徒自身が掃除をする訳とは:2つの理由がある
-
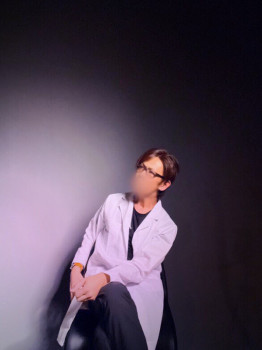
自分自身が刺激を受ける大切さ:キャストの仕事に活かす
-
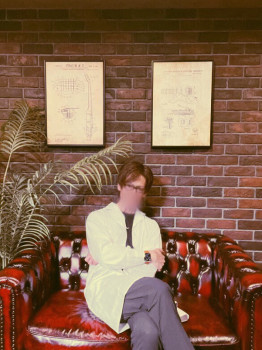
「もったいない」という単語に込められた意味:ありがたい存在
-
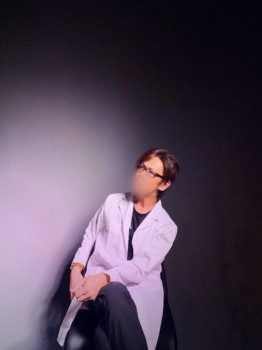
お客様がキャストを選ぶ:お客様を選ぶようなポストに思うこと
-
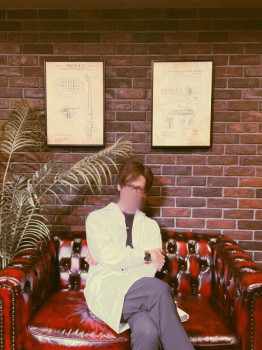
なぜ日本には玄関があるのか:建物に入るのに靴を脱ぐ理由

