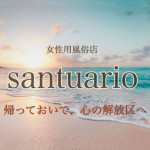モチベーションについて考えるとき、自分でそれを維持し、管理するべきだとされることが多いですが、果たしてそれが本当に可能なのでしょうか。例えば、santuario OSAKAの凱代表はモチベーションは自分で保ち、管理していくものだとよく語っています。確かにその通りだと思う一方で、私自身が学業や日々のモチベーションを常に高い状態で保っているかと問われると、そうではないと感じています。そこで今回は、モチベーションが果たして自分だけで保つものなのか、それとも外的な要素に頼るものなのかを考察してみたいと思います。
僕がよく行う方法として、ある概念を深く考察する際に、その語源を探るというものがあります。モチベーションも例外ではなく、その語源を探ることで、私たちがどのようにそれを理解するべきかが見えてくるかもしれません。
モチベーションの語源はラテン語の「motivate」から来ており、その「motivate」は「motive(動機)」が変化したものです。「motive」の元々の意味は、「movere(動かす)」という動詞に起因します。このように、「モチベーション」とは「動かす状態」すなわち「動機づけ」と訳されるわけです。
「動かす」という動詞が示すように、モチベーションには常に主体(動かす者)と対象(動かされる者)という関係が存在します。モチベーションを自分に向ける場合、その主体は自分以外に見えることもあります。しかし、モチベーションを外的要因に頼ることは、単なる軽薄な考えに過ぎないというのが私の結論です。
ここで問題となるのは、「行為の主体と対象が完全に一致することは可能か」という点です。20世紀のフランスの哲学者、モーリス・メルロ=ポンティは、身体についての哲学的考察を行い、特に「可逆性(la chiasme)」という概念に注目しました。この概念は、「右手が左手に触れる」など、主体と対象が交差し、一時的に重なる現象を示します。しかし、メルロ=ポンティによれば、この一致は決して完全ではなく、主体と対象は「完全な統一に向かって進むが、常にずれを残す」関係にあるとされます。
さらに、メルロ=ポンティは世界を「肉(la chair)」としての質を持つものと捉え、私の身体と世界は互いに触れ合い、絡まり合う存在であると考えました。主体と対象は外的な対立ではなく、内的に絡み合う存在なのです。
メルロ=ポンティにとって、モチベーションは単なる精神的な決定ではなく、身体的な傾きや習慣、環境との関係性の中で生まれてきます。つまり、モチベーションを「保つ」という行為は、精神的に強制することではなく、身体や環境、リズムといった要素との関係の中で、行動に対する傾きが自然に育っていくことだと考えることができます。
モチベーションを保つことは、身体と世界との関係の調整に近いものであり、メルロ=ポンティは「意志することとは、すでに身体がその方向に傾いていることだ」と述べています。つまり、モチベーションは、すでに身体と世界との関係性の中で芽生えてくるものだと考えられるのです。
この考えに基づけば、モチベーションを「保つ」ということは、強制的に自分に命令することではなく、自分の身体や環境との調和をとりながら、行為を持続可能なものにしていくことです。自分を環境に開き、体とリズムを整えることで、自然に行動へと導くという形でモチベーションが保たれるのです。
例えば、ピアニストの練習においても、意志は確かに必要ですが、練習の中で身についたリズムや習慣がすでに行動を支えています。モチベーションを保つとは、命令することではなく、自己と環境の調和の中で“持続可能な傾き”を育てることに他なりません。
この考察の結論として、モチベーションは単なる精神的な努力や強制的な命令によって保たれるものではないということが言えます。むしろ、モチベーションは自分の身体、環境、リズム、そして世界との関係の中で自然に形成される「傾き」や「調和」によって育まれるものです。主体と対象が完全に一致することはないが、それらが交差し、互いに影響を与えながら共に生成されていくように、モチベーションも自分の意志だけでなく、周囲との相互作用の中で持続的に高められるものなのです。したがって、モチベーションを保つということは、強制的に自分を動かすのではなく、環境や自分の身体との調和を取ることによって、持続可能な形で行動へと導かれることだと言えるでしょう。
ほなまた!
柚香の写メ日記
-
モチベーション柚香