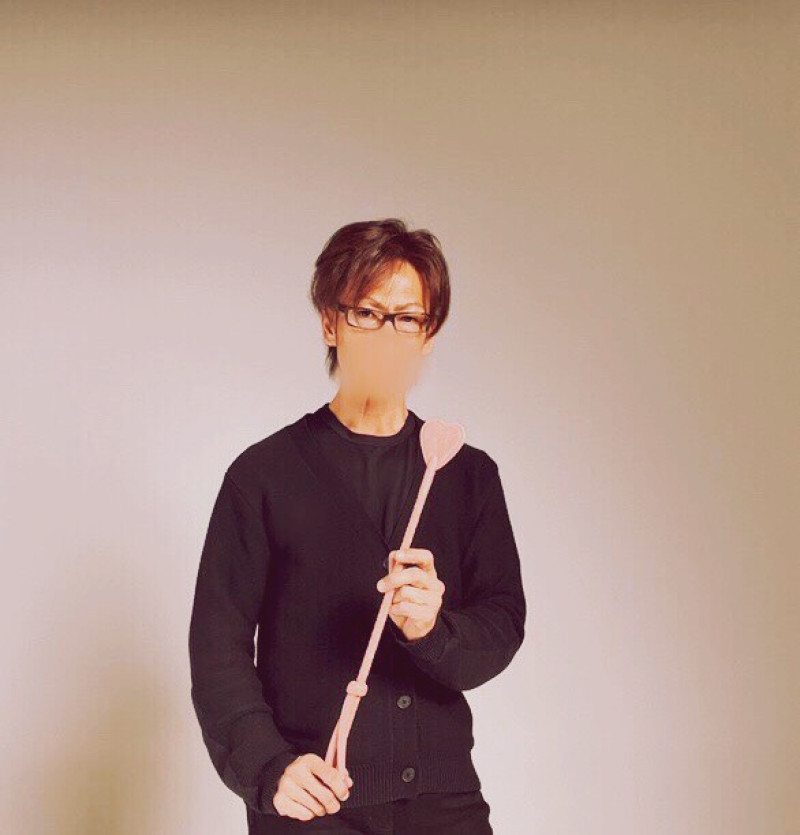少し早いですが、今日はこいのぼりのお話。黒、赤、青のこいのぼりが有名ですが、これ、それぞれがだれを意味しているか知っていますか?最近では黒いこいのぼりがお父さん、赤いこいのぼりがお母さん、青などそれ以外が子どもたち… といったイメージの人もいるかと思いますが、実際は違うんです。
黒い鯉、いわゆる真鯉は江戸時代に誕生しました。もともとこいのぼりは、この真鯉1匹のみだったんです。江戸時代は、「男の子が生まれたら、その子供の立身出世を願い、真鯉を一匹揚げた」んです。そう、元々真鯉は、お父さんでなく「息子」だったんです。明治になり、そこに赤い鯉、つまり緋鯉が加わりました。これによって真鯉は「息子」から「父親」へと役割を変えました。
それなら緋鯉は「母親」?違うんです。緋鯉こそが「息子」になったんです。1931年に作られた、きっと誰もが一度は聞いたことがあるであろうこいのぼりの歌詞はこうなっていますよね。
屋根より高いこいのぼり
大きい真鯉はお父さん
小さい緋鯉は子どもたち
おもしろそうに泳いでる
そうなんです。お母さんはまだ存在しなかったんです。
そして東京オリンピックが終わり、五輪の輪を見たこいのぼり職人が青色のこいのぼりを作りました。これによって緋鯉は「息子」から「母親」へと役割を変え、青が「息子」となりました。今では緑や紫、オレンジ色などのこいのぼりが作られることもあり、これらはすべて「子ども」と認識されていますね。