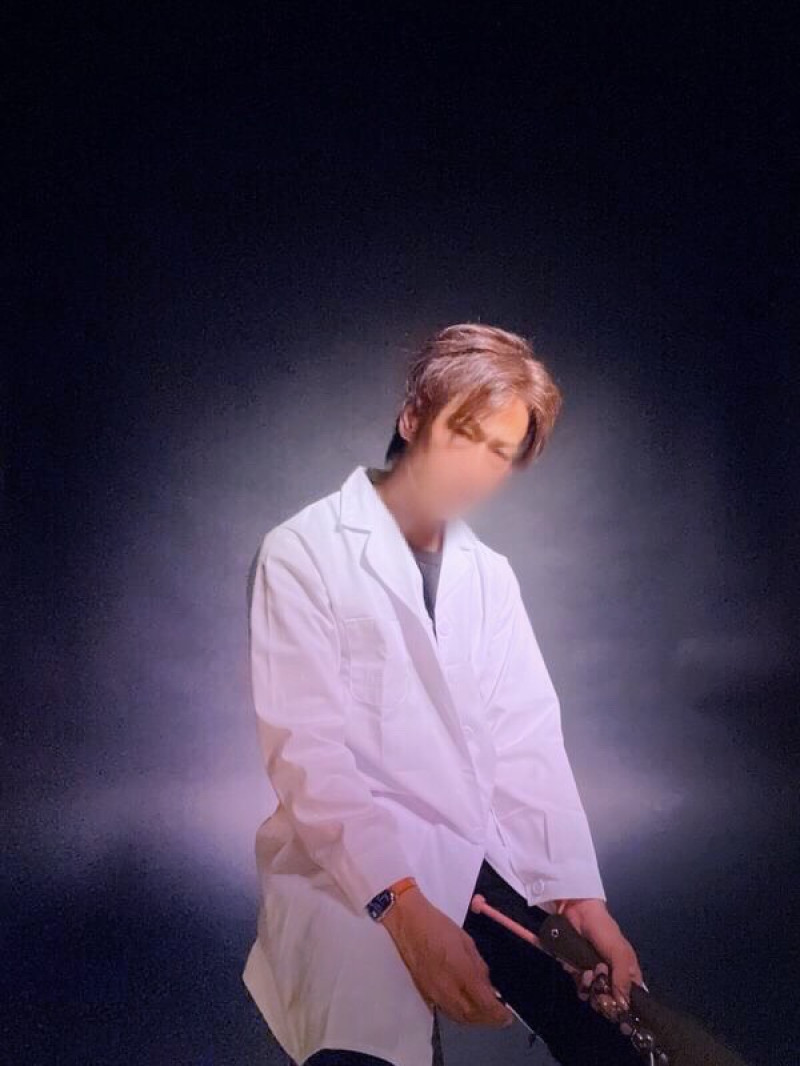三色団子と言えば、春の風物詩のように感じる人もいるかもしれません。桃の節句でも愛される和菓子の1つ。そんな三色団子、なぜ三色なのか知っていますか?
もちろん諸説ありますが、実はあの豊臣秀吉が考えさせたもの、という説があります。もともと派手好きだった秀吉は、京都の醍醐寺で家族や家臣を集め、お花見をしたのだとか。そのためだけに桜の木を700本植えた、なんて説もあるんです。
そしてこの時のお茶菓子として振舞われたのが三色団子だったと言われています。この頃のお団子と言えば、甘くない団子にお醤油をかけるのが一般的。でもそれでは華やかではないからと、秀吉が見た目の美しい三色団子を考えさせた、という説ですね。
ここからお花見には宴会、三色団子、などと言った考え方が広まるようになりました。江戸時代には庶民の間でも流行し、「花より団子」ということわざが生まれたのも、この頃だそうですよ。
ちなみに、ピンクは桜の咲く春、白は雪の降る冬、緑は葉が生い茂る夏を示しているのだとか。「あれ、秋がない」と気付いた人もいるでしょう。これね、「秋がない=(食べ)飽きない」というダジャレの意味があるそうですよ。
これ以外には、ピンクは春の陽光の季節、白は春の霞がかった空、緑は春を象徴する芽吹いた大地、なんて解釈もあるそうです。だから、1番下は大智の緑、次に霞がかった空、そして上に光を表すピンクが来る、とも言われていますね。