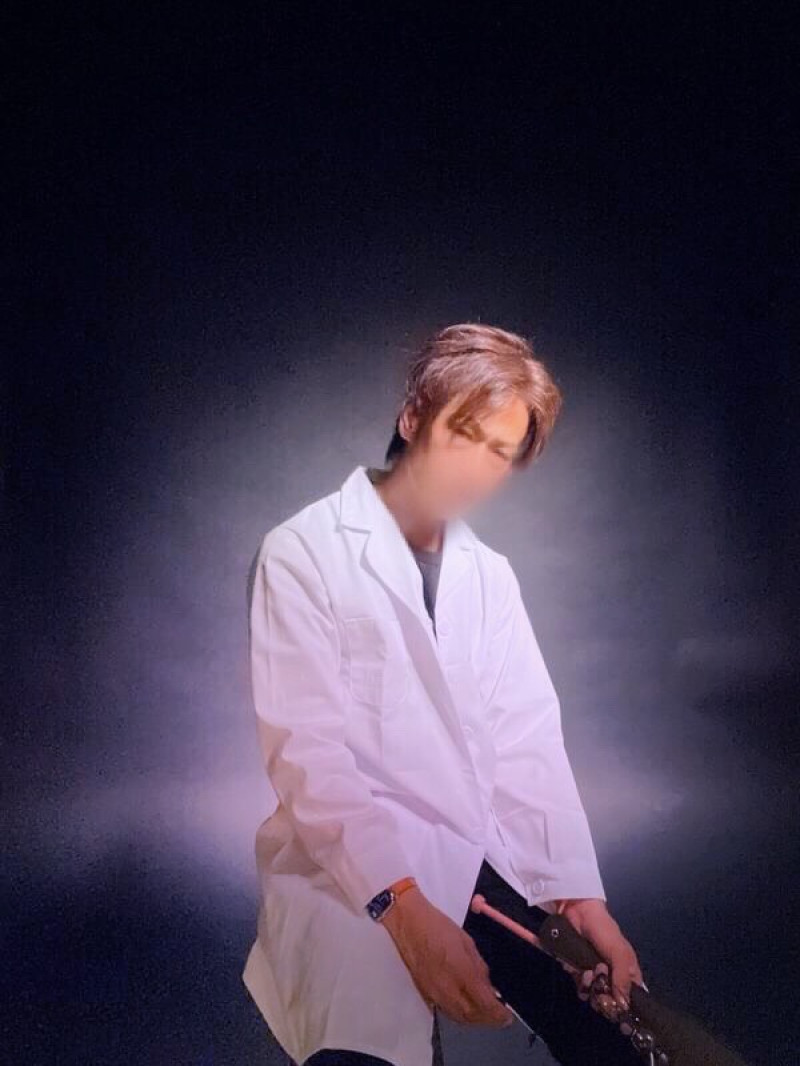温かくなってくると、桜餅を見かけるようになりますね。実はこの桜餅、関東と関西で形が異なることを知っているでしょうか。
関東では、小麦粉と砂糖、白玉粉を混ぜて焼いた生地でこしあんを二つ折りで包んだ【長命寺(ちょうみょうじ)】ですね。これを塩漬けした桜の葉で包んでいます。江戸時代中期、1717年、徳川吉宗が花見名所を作ろうとして、隅田川のほとりに多くの桜を植えたことこそ、この桜餅が生まれたきっかけだったそうです。桜は美しく咲き誇ったものの、近所にあった長命寺の寺男、山本新六が、隅田川の桜の落ち葉掃除に悩まされるようになりました。そこで、樽で塩漬けした桜の葉を使った桜餅を考え出し、これが関東の桜餅として親しまれるようになったんです。
それに対し、関西では道明寺粉で作られた粒の形が残るお餅で、あんこを包み、塩漬けした桜の葉で包んだ【道明寺(とうみょうじ)】こそ、桜餅として認識されています。京都には、道明寺粉で作られた餅を椿の葉で包んだ餅菓子がありました。それが関東の長命寺にならい、椿の葉に代わって桜の葉で巻くようになったことから、関西風の桜餅である道明寺が誕生したんだそうですよ。
長命寺は関東近郊に広がり、道明寺は近畿から北陸、四国、九州へ伝わったのだとか。でもおもしろいことに、北海道では道明寺が一般的だと聞きました。江戸時代、北前船という船が瀬戸内海と北海道を結んでいたらしいですね。この影響で、北海道や東北の一部日本海側地域では、道明寺が親しまれているのだとか。
同じ国の中で違う形のものが同じ名前で存在する。面白いと思いませんか?