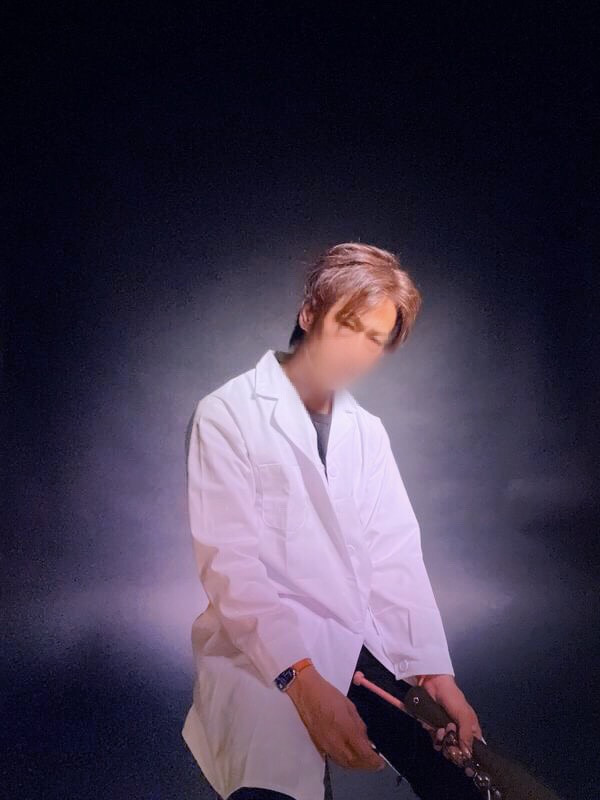今は「令和」ですが、元号と言えば、天皇が代わる時に変わるものという印象を持っている人も多いのではないでしょうか。実は、最初の元号「大化」が誕生してから「令和」に至るまで、248もの元号があったと言われているんです。
天皇が代わる時だけ元号が代わるというのは、実は近代の話。今までは、大きな出来事が起こるたびに元号が代わっていたんです。例えば自然災害が起こった時は、「悪い影響を断ち切る」目的で、元号が代わっていました。かといって良いことが起こった時は変わらなかったのかというとそうではなく、その出来事を漢字で表して元号にしていたこともありますし、天皇への贈り物を記念して元号が変わったこともあります。
例えば、704年には「虹色に輝く雲が見えた」ということで、「慶雲」という元号に変わりました。天皇に白い亀が贈られた時は、「宝亀」という元号になっています。
そんな元号を決める時には、こんな条件があるそうですよ。
1.世間で使われていない言葉であること
2.書きやすく、読みやすいものであること
3.国民の理想にふさわしい良い意味を持っていること
そしてこれに加え、「明治以降の元号と頭文字のアルファベットが重ならないようにすること」というルールもあるのだとか。公式書類などの略字として使う場合に混乱を避けるために、このルールが設けられているそうです。