【女風小説】20話~32話|1話数分の読み切り短編サイズ
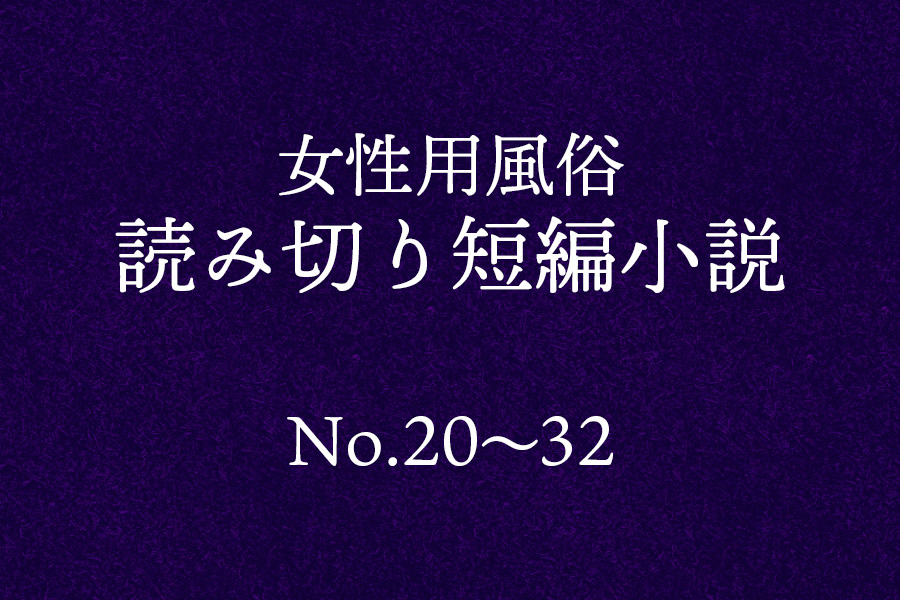
1.
~おたすけマン!~
2.
~ なめたいはら~
3.
~デートにはルージュを~
4.
~ワインひとくちのうそ~
5.
~むらがって~
6.
~もっと、して……。~
7.
~ハッピーバースデー~
8.
~アオイシーツ~
9.
~こどもじゃないもん~
10.
~サクラ・サク~
11.
~ジェラシー?~
12.
~アイジンのおきて~
13.
~きらいにならないで~
~おたすけマン!~
「おくさま、え? なにって?」
「だからぁ、」
職場の同僚の南さんと一緒にランチに来ている。オーガニック野菜専門店の人気フレンチ店。まわりを見わたす限り、女の人ばっかりだ。若い子からおばあちゃんまで。皆一様に楽しそうな笑顔をふりまいている。南さんの喋った最後の方の語尾はお店の中の人々の笑い声やらの喧騒に紛れ聞き取れなかった。
南さんは目の前のクレソンをフォークで突きながら、今度は少しだけ声をあげてつづける。
「【おくさま助け隊】っていうね、サイトがあるのよ。あたしね、なにを助けてくれるのかしら? なんて興味本意でそのサイトを見たのね。でね、なんだと思う?」
ふふふ、南さんは今度はパプリカをつつきながら微笑むように笑う。なんだと思う? なんだろう?助けたい、でしょ? ダスキンみたいに掃除やら草むしりやら用を足してくれるとかかなぁ?
「と、思うでしょ? 普通?」
「え? 違うの?」
前置きの長い南さん。本当に話しが好きだから。タクっ。
「性欲を助けるのよ。おくさま助け隊は」
ねっ、と、最後にウインクをしてまた笑った。そういえば最近の南さんは心なしか綺麗になった気がしないでもない。と、対面にいる南さんに目を向けると口の端に米粒がついていて、つい、ニヤけてしまった。
「性欲をねぇ〜」
おくさまの性欲を助けたい! をもじって【おくさま助け隊】か。笑えたけれど、ダスキンに仕事を頼むかのようネットで指名しメアドが書いてあるから勝手に連絡をして会うシステムになっていた。
南さんの気に入りの子はやめて、他の子を閲覧する。真面目そうな『荒木』という男の子(30歳)といくばくかのコンタクトを取り合い、会うことになった。
「わ、本当に普通な感じだぁ〜」
「普通です、てゆうか僕、普通に会社員ですよ」
荒木さんは副業だった。まあ、専門でしているとは思ってなかったけれど。
「じゃあ、荒木さんは偽名かしら?」
ベッドの上に並んで座っている。普通のビジホの一室に。荒木さんは首を横にふる。
「え? 本名?」
「はい、なんて、嘘です」あはは。豪快に笑った。おもしろい人だなぁ、全くイケメンでもないし。それこそずっと知り合いだった気がするし。
「奈菜子さんは偽名なんですか?」
あたしも首を横にふって
「本名ですよー」と、明るくこたえた。
「ですよねー、お客さんが嘘の名前あまりいわないですもん」
荒木さんはスーツだった。シャワーはいいわ。あたしは荒木さんの着ているものを脱がして匂いを嗅ぐ。営業職なのだろうか。薄っすら汗ばんでいて男性特有の匂い鼻腔をくすぐる。嫌悪感を抱く匂いではない。むしろ舐めたくなるほどだ。
「舐めたい、いい? 全てを」
ベッドに仰臥している荒木さんは靴下以外のものはなにもない。無防備なその身体にあたしはムジャブリついた。あっ、たまに声をあげるお金を介してあっている荒木さんをとても愛おしく感じる。足の指から手の先、顔に至るまで全て舐め尽くてあたしはまるで天然のシャワーになった。鉄柱は勃っているが、そこだけは違反のような気がしてやめた。
「あれ? これじゃあ、僕が奉仕されっぱじゃないですか?」
荒木さんはぼそっとつぶやきいて上体を起こしてあたしの洋服に手をかける。あたしは、いやいやするように抗う。あの、聞いてくれるかな? あたしの口が開きだす。
「舐めるのが好きっていうかね、奉仕をしたいの。男性に。で、自分の身体はっていうと全く触ってほしくないの」
ほほう。荒木さんは真剣に聞き入る。
「だからね、あたしの性欲は、男性を気持ち良くさせると発散できるのよ。だから今夜は荒木さんはあたしの性欲を立派に助けたわ。よっ、助け隊!」
ちょっとだけおどけてみせる。荒木さんも笑いながら頭を掻いた。
「性欲の種類なんて人それぞれ違うから。奉仕をされたい、受け身の女性がほとんどだし奉仕をしたいなんていう女は多分に稀ね、きっと……」
荒木さんは裸のままあたしをそうっと抱きしめた。そのぬくもりの中にあたしの唾液の匂いも混じっていて余計に満足感が脳内を支配していく。
~ なめたいはら~
「お電話ありがとうございます。中根さま」
すっかり常連の人種に成り上がっているあたし。けれど電話をして、中根さまと名前を告げられるととても嬉しくなる。利用者記録に登録されていることは百も承知だし、お客さんの名前を呼ぶことはどの業種に至っても同じだけど。
「こんにちは。どう? 今夜? いる?」
この4文字の単語をいえば、電話口のオーナー・森崎さんは即座にこたえてくれる。
「ええ、いますよ! ちょうどよかったです。中根さまにごあつらえ向きの男の子がおととい入店して、」
森崎さんはそこで一旦言葉を切って、ちょっとまってくださいね、と、つづけた。
「今夜でしたら、午後8時なんていかがでしょうか」いかがでしょうか、の語尾はもう質問系ではない。いかがです、に切り替えてくれてもいいのに、と、思う。
なにせあたしが電話をして断ったことなどないのだから。それに指名もしない。あたしのタイプを理解している森崎さんに任せている。
「ええ、いいわ。ふふふ。たのしみね」
「あはは、期待して待っててくださいね。いつものホテルでいいです? こちらでおさえておきますよ」
じゃあ、おねがいね、タバコに火をつける音が電話越し耳の中で弾ける。森崎さんは控えめにタバコの煙を吐き出す。ささやかな音がいつもあたしの欲望を掻き立てる。
指定されたホテルの部屋に先に入る。あたしは先に入って男の子がうろたえながらも入ってくるさまが好きだ。今夜くるのは『24歳のタカユキくん』
午後8時を少し回ったところで部屋のチャイムが鳴る。どうぞ、あたしは大人の余裕を見せるよう大きめな声をだした。
「こ、こんばんわぁー」
部屋のドアが開き逡巡をしながら入ってきた『タカユキ』くんは、わわわ、と、声がでちゃうほどにあたしのどストライクの男の子だった。
「こんばんは。あたしは京子。今夜はよろしくね」
「あ、あ、はいっ、」
んー、参ったぁ、可愛いすぎる。この寒いのに額に汗をかいている顔にぱつんぱつんのスーツ姿。肉肉しいほどにはち切れんばかりのお腹。それにいも虫を彷彿させるあの指。
「ここに、座ってくださいね」ふふふ。あたしは微笑む。タカユキくんは、袖で額の汗を拭いながら、あ、おじゃましますぅ、と、よそよそしい感じで隣に腰掛けた。
「すみません、まだ、不慣れだし、って、それに、この体格だし、」あはは。タカユキくんは泣きそうな顔をして嘘くさい笑顔を浮かべる。
あたしは首をよこにふって
「あら? なんであやまるの? あたしはタカユキくんが好みなの。森崎さんに聞いてない?」
まあ、それなりに、タカユキくんはぼそっとつぶやいた。「ふっくらした男子を好きな女性はたくさんいるわ。細ければ顔がよければってだけじゃ出張ホストは出来ないの。器量なのよ」
わかるかなぁ? あたしはタカユキくんの顔を覗き込んだ。
うつむいた顔には緊張と自分の体型へのコンプレックが溢れていた。これからよ。タカユキくん。あたしは胸底でエールを送る。
ベッドの上に上がると別人になってあたしの身体を隈なく舐めて、愛撫を施し優しい声で「かわいいです、きょうこさん」と、甘い声音でつぶやいた。ああ、そうはいってもやっぱりタカユキくんはプロ意識があるんだなぁと思うと余計に応援したい気持ちが生まれた。
「舐めていい?」
「えっ?」
ざんざんイカされたあと、最後にお願いをしてタカユキくんのお腹を舐めさせてもらう。
「わ、くすぐったいですって」ククク、笑いを殺すのに必死な彼を横目でみつつあたしはこのお腹を食べてしまいたいという思いをこめてへそのまわりを重点的に舐めた。
「あははは、」
タカユキくんの屈託のない笑い声。あとで森崎さんに電話をしておこう。
「今日も最高でしたよ」と、そして「また大きな身体の男の子いたら教えてね」そうつけたして。
あたしはその実。スー女だ。
相撲が相撲取りが大好きなのだから。
太っていてもね、性感ホストは出来るんだよね〜。だってフェチだもん!
~デートにはルージュを~
SNSで最近よく流れてくる『女性専用風俗』というものに興味があって様々な『女性向け』を閲覧をした。正直さみしかった。会社に行き、誰もいない部屋に帰ってくる日々。
都内住まいだけれど都会ならではこその孤独がある。窓の外には環状線が走っている。なにをそんなに急いでいるの。タバコを燻らせながらいつもそう思う。急いでいるの、か。その言葉はあたしの心の中に矢を放つ。癒されたい、喋りたい、触ってほしい。その欲望だけが頭をもたげる。
あたしはいくつもある中からあくまでも普通そうな感じの『寺岡さん』をお願いした。年齢は35歳。あたしと同年代だ。きちんと書かれた写メ日記? とやらにも顔は載せてはいないけれど、パネルの顔(ぼかしてあるけど)からしてもきっとタイプだろうということは察知できる。
癒されたい……、『寺岡さん』はあたしをどうして癒すのだろう。
「えっ」
待ち合わせの場所に行くと、待ち合わせの切符売り場の前に金髪のちょっとだけ恰幅のいい男性が立っていた。スマホをいじっている。うつむいているので顔は把握できない。けれど、金髪……、まさか。
近寄ってその場に立つと
「沢田さん?」
やや低めの声で名前を呼ばれた。あ、ち、違います、そう断るのは簡単だった。しかし、見た目との派手さはその低めのボイスによって払拭される。あ、はい、沢田ゆうこです、なんてあたしは律儀に名前と苗字を名乗っていた。
「あはは、ゆうこさんですね。名刺でも出てきそうな挨拶ですね。うん、とても素敵です。その赤いルージュもね」
赤いルージュ。そう、あたしは今夜真紅のルージュを引いてきた。あたしではないあたしを演じるために。
「ありがとう。寺岡さんも。金髪お似合いだわ」
「そうですか。ありがとうございます」
いきますか、寺岡さんはあたしの手をさっと取って歩き出す。どこにいくの? その言葉がいえない。とゆうかいわせてくれなかった。
赤提灯のかかった居酒屋で軽く飲んでホテルに向かった。「あ、僕が払いますよ」まさかお金を払ってあってもらっているのに、寺岡さんの言葉に驚いた。「僕の方がたくさん食べたので」そう、はにかみながらつづけた。この時点であたしは彼にすでに癒されていたのかもしれない。
「オイルとパウダーどっちがいいですか?」
どっちが得意ですか? あたしは反対に訊き返す。「おー、そうきましたかぁ」ククク。寺岡さんは目を細めた。
「じゃあ、まあ、うつ伏せから」
部屋はこじんまりした赤を主張とした部屋だった。燃えるような赤。興奮をそそる赤。赤が全面に出ている部屋はいかにもな部屋だ。
背中にさわさわという感覚がして顔を上げ振り向くとパウダーが舞っていた。
「パウダーを使って触っていきますね」
顔を元の位置に戻しつつなにもいわずに身を委ねた。背中にあるパウダーが寺岡さんの繊細な指先によって滑ってゆく。ゾクゾクとさせる指先にあたしは知らぬうちに悶えていた。声が、つい、出てしまう。背中からお尻、太もものあわいにまで指先が悪戯を始める。
金髪の髪の毛にパウダーが舞っている。それはなんだか夢でも見ているような光景だった。
「あれあれ」
施述が終わり呆然となったあたしの顔を見て、あれあれ、と苦笑まじりにいいながら、タオルであたしの口を拭う。
「せっかくのルージュが台無しだ」
タオルにはあたしには全くそぐわない真紅のルージュが付着していた。やだぁ、ついちゃったわ。あたしはクスクスと笑う。寺岡さんも同じように笑った。
「ねぇ、」
あと、少ししか時間がない。どうしてもいいたいことがあって肩をポンと叩いた。
「わかりました。僕も、そう思います。見た目じゃない。そう優しさですね」
「そうよ。あたしには真っ赤なルージュは敷居が高いわ」
今夜はよく眠れそうな気がする。きっと。パウダーの匂いはラベンダーだった。
次週、また寺岡さんの日記を読んだ。
【黒髪にして3日目。うん、とても新鮮ですね。おっさんぽくなってしまったかもですが、中身は優しいおっさんですよ】
カフェのテラスで撮ったであろう写メが添えてあった。
『あのね、金髪は、こわいわ。きっと黒髪にした方が指名が増えると思うの』
~ワインひとくちのうそ~
「やっぱり牛肉には赤よね」
照明がロウソクだけの隠れ家的お肉専門店にいる。シャトーブリアンをはじめとする高級牛肉がレアでちょこちょこと出てくる。
「口の中で肉汁が溢れてそれでいて噛まないでもとろける感じです。それでいて全くしつこくない……」
フォークとナイフの使い方があまり上手とはいいがたい。けれど、美味しい、美味しいと、何度も言葉にして、蔓延な笑みを向ける彼はとても愛らしい。
「ふふ。なんて上手な食レポなのかな? みさきくんは」
「えええ! そうっすか? あーざす。てゆうか俺、こんなに美味しい肉を食べたの始めってで、」
本当に、美味しいです。と、最後にあらたまった声でしめくくる。
「赤ワイン好きっすね。リナさん。白は? 苦手なの?」
苦手じゃないわ。あたしはクスクスと笑いながらワイングラスを持ち上げて赤ワインを一口飲んだ。白も好きだけれど、やっぱり赤。燃えるような赤。赤ワインは比喩じゃなくてあたしの血となり肉となり欲望の炎を燃やす。
「さーて、今夜はまだ飲むよ。いい?」
みさきくんは、目を大きくあけて、望むところです、と、こたえてから笑う。みさきくんも結構飲める口だ。だから一緒にワインが飲める出張性感癒しホストを呼んでいる。どうせ好きなワインを飲むならば顔が良くて、機転のきく、それでいて誰がみても羨ような男の子と飲みたい。なんて素敵な世の中になったのだろう。
お金で彼の時間を買っている。だから余計その時間をどう過ごそうか考えるのも楽しい。と、いっても結果的には『酒を飲んでべろべろで終わる』のだけれど。
ホテルに入るや否や浴槽に湯をはって、赤ワインを流し入れる。飲むために買うワインは高価なものにしているけれど、浴槽に入れるのは安物のワインだ。
一緒にワイン風呂に入る。これで3回目だ。ワインの匂いに包まれ至福の時間が始まった。
「いい匂い」
背後からみさきくんの声がしてあたしの胸を揉んでいる。乳首をコリっとつまみあげて、少しだけ意地の悪い顔がのぞきでる。
「あっ、」声がもれる。「トントンに尖ってる」みさきくんがささやく。結構飲んでいるし、ワインの湯気によって頭の中がぼんやりとしている。この空間がなにせ好きだ。ワインの湯気は酔いとエロスをかもしだすから。
その後、お風呂のヘリに座らされて陰部を舌先で舐められた。陰核がわななく。ビクン、ビクンと身体をふるわせ、何度目かの舌の悪戯でイッテしまった。指は優しく蜜壺の中に収まっている。声にならない淫靡な声は狭くてワインの湯気のお風呂の中に吸い込まれてゆく。
若いくせに。
あたしは、心の中でつぶやく。どうして男って裸になると女を変にさせるのだろう。毅然とした女でも裸になれは、ただの女。
「いやぁ〜、今日はリナさん、感じ方が半端じゃなかったです」
お風呂から上がって、冷えたワインを飲んでいる。みさきくんは白ワインを飲んでいる。
「俺、本当は、白の方が好きなんっすよ」
ホテルに入る前にこっそりと教えてくれた。けど、と、タバコに火をつけてから、こう付け足した。
「リナさんはきっと食わず嫌いじゃなくて飲まず嫌いかも。白、結構うまいです」
今、一緒に白ワインを飲んでいる。喉越しがとてもいいしなんてあっさりしているのだろう。
「おいしいわ」
~むらがって~
「あ、そうそう、」
乱れたシーツの上で息を整えていたら、横からなにか急に思い出したようにりょうまくんが口を開いた。空虚で無機質な真っ白い天井をみあげながら。
「あ、そうなのね」
「え? ってまだ、僕なにもいってないっすよ」
ほんとうにみっちゃんっておもしろいなぁ、と、笑いながらあたしの髪の毛をさわさわと触れる。
「んっと、今、お店に新人が2人入店してきて、モニターになってくれる女性を募集してるんですよ」
天井を見るのをやめて首だけりょうまくんに向ける。長い睫毛に鼻筋の通った整った鼻。それで? あたしは話しの先をうながす。
「みっちゃんしてみない?」タバコすっていい? みたいな軽いのりで訊いてきた。モニターは無料なんだ。けど人は選べないけどね。りょうまくんはすくっと立ち上がり、テーブルの上にあるマルボロライトに手を伸ばす。『カチャ』と、ジッポの音がして、スー、と息を吸う音とはー、と息を吐く音がしずかな部屋に煙りと共に充満した。
「吸う?」
はい、と、タバコを差し出されて受け取る。そうして、口に加える。間接キスだね、あたしはタバコを一息吸ってからこたえる。
「は? てゆうか、間接キス以上のことしてるよね? 僕ら」あははは、りょうまくんが声を荒げてあははあははと楽しげに笑った。
「いいよ。けれど、そのときはりょうまくんもいて。りょうまくんの料金はきちんと支払うわ。あたしの感じている姿を見ててほしいな。そうゆうのってダメなのかな?」
んー、りょうまくんは長考したのち、まあ、オーナーに訊いてみるけど、と、あまり煮え切らないこたえが返ってきた。
「なに? やきもち?」ふふふ。あたしは意地悪なことを質問する。
「そう」
えっ? その単語は嘘でも嬉しかった。りょうまくんはあたしよりも4つ年下だ。
モニターの日。
りょうまくんの後ろから入ってきた男性はなんとわりと年齢高め自意識高めな男性だった。
「よろしくお願いします」
低空飛行で腰を折る。なのであたしも折った。お手柔らかに。
「なおみつです。35歳の新人です」
「みつるです。30歳の独身です」
なんだよそれ。お見合いかよ。りょうまくんが笑いながら突っ込んできた。あたしとなおみつさんはその言葉で緊張が解けふふふ、と同じように笑った。さあ、僕は居ないていではじめてください。真面目な顔になってそういった。窓際の椅子に腰かける。そうしてモニター体験が始まった。
なおみつさんの手のひらは常に汗ばんでいたし時折つくため息が気になった。大事な部分を弄られているとき意図してなのかりょうまくんの方から良く見えるように足をひらかされた。うつむいていたけれどいたく視線が気になって顔をそうっとあげたらりょうまくんと視線が重なった。いつもと違う種類のまなざしだった。欲情をしているようにもみえ、哀れんだようにもみえ、けれどあたしはその状況にもっとも興奮をした。なおみつさんはそれを自分のテクニックと勘違いしているようだけれど、それでも構わなかった。いつもお決まりのパターンだったりょうまくんとのプレイもこうやって見られることで逆に刺激になり高揚をした。きっとお互いに。
「みっちゃんさ、エロい顔してたよ。僕さ、勃ったもん」
「やだぁ、そうかなぁ。でも、嬉しいな」
あれから一週間が経ちまたりょうまくんを指名した。彼は勃ったもん、と軽口を叩いた。けれど、あたしにとってその言葉は涙がでちゃうほどに嬉しかった。
彼は勃起をしないのだから。ほんとは。なので「勃った」といったのはあたしにたいしてのリップサービスだったのかもしれない。女はまことに不思議な生き物で男性の勃起で自分の魅力をはかることがある。
「嬉しいな」
~もっと、して……。~
依存なのか、中毒なのか、自分でもよくわからない。日常の中でふと、頭に浮かぶのが『ミナトくん』の真正面からみたその顔立ち。目はあきれるほど大きな黒目を持ち、筋の通った鼻梁。薄くもなくかといって分厚くもない唇。そうしてあたしは唯一無二に好むのはその手だ。ほっそりしていて、男性なのに白魚のような……、とかではなくむしろその逆で手が汚れているのだ。その汚れは彼の日常を物語っている。
あいたいよぅ……。
先週あった分だった。けれど、また今週も予約をいれてしまう。決して安くない金額だ。キャバ嬢にお熱をあげる男性の気持ちが最近よくわかる。決してわかりたくなかったけれど。
お金が介在している間柄だからこそあいたくなるのか、これがもしプライベードならどうだろう、とか、考えたところで理由などはない。
好きだから。あう。今はただそれだけだ。
あたしは29歳の普通の事務員。地味な顔に地味な制服をまとい地味に生きている。
「お金を払う彼氏かぁ」
つぶやいた声は三月の匂いをぞんぶんに溜めた空に吸い込まれてゆく。春めいている毎日の中でミナトくんはあたしのオアシスだ。
「僕がぁ? オアシスですかぁ?」
夜ミナトくんを自宅に呼んだ。最初と2回目だけホテルにしてあとは自宅。「ホテル代もったいないっす」ミナトくんからの助言で。
「そう、今あたしの生活の中のオアシスなの。ミナトくんは」
「あーざーす」
けど、大袈裟だね、ミナトくんはちょっとだけはずかしそうにうつむいてそう付け足す。
「お腹空いてない?」
時計は午後8時を回っている。昨日つくったビーフシチューがまだ冷蔵庫にあったのを思い出す。
「あ、わかります? お腹鳴ったの聞こえたの?」
あはは。あたしたちは互いに笑った。急に静寂な時間が流れ、対面しつつ抱き合って唇を重ねた。長い長いキス。ミナトくんの手のひらがあたしの後頭部にそっと添えられる。あ、あの手があたしの頭に。キスは徐々に大袈裟になってそのまま縺れ合いソファーに寝かされた。
「指を、ミナトくんの指を、ちょうだい……」
ミナトくんはうなずき、あたしの口元に指を持ってくる。あたしはそれを掴んで自ら口の中に入れて一本一本確かめるように丁寧に舐めた。冷静に見守るミナトくんの目は嘲笑っているようにも見えるし、しかし決していやそうでもない。口の中でうごめく指先が歯や喉の奥をおかす。指だけで頭の中がおかしくなりそうで、いや、もうおかしくなってあたしはいつの間にか裸になっていた。
あたしの唾液にまみれた指先で乳首をつままれる。
「あっ、あああ、」
声がたくさん出てしまい、それでももうとめることなど決して無理だった。指はあたしの身体を這いずり回る。そういて何度も頂点に達した。
汗だか唾だかわからない気だるい身体のままぼーっとしていた。
「……、ゆ、指、」
隣にいるミナトくんが指を差し出しながら口を開く。やや間があったけれどあたしは待つ。
「僕、塗装屋で、車の。この指の色は落ちないんですよ。きっと仕事を辞めたらいつかは落ちるだろうけれど、俺、この仕事以外したことないから、多分永遠にこんなに汚い指っすよ」
手をひらひらとさせるミナトくんの横顔にはまだ少年の逡巡と葛藤が残っていた。
「いいんじゃないの、好きよ。働く指」
少年から青年に脱皮しようとしてる目の前の彼。この先きっともっといい男になるにちがいない。
「そういえば、めちゃくちゃ腹減ったっすよ」
「あ、そうだったね。ビーフシチューでいい?」
わお、大好きです! てゆうか多分なんでも喜んで食べると思う勢いだけれど、今夜はビーフシチューでよかった気がしてならない。
明日もまた仕事がんばろうと思う。
「ね、」
~ハッピーバースデー~
鏡の中の自分の姿を見たくないと思い始めたのは何歳からだっただろう。毎日見ている同じ顔なのに毎日どこか違いを見つける。けれど、それは決して良いほうの違いではない。悪い方の違いだ。
あれ? こんなところに。なんて科白をよくドラマなんかで聞くけれど、あれ? こんなところにシミ? と今朝まるでドラマの中の熟女女優のよう声に出してしまっていた。
誰にでも平等に律儀に歳は取る。
明後日あたしは51回目の誕生日を迎える。
平成最後の誕生日だ。世間ではなににしても『平成最後の』だとかいうけれど、それがどうしたってことはないけれど、あたしもその流れにうまく乗りこみ、思い切って『女性向け風俗店』の扉を叩いた。
処女ではないけれど、独身だし、前回いつ男性と触れ合ったのかおぼえがない。これはまずい。潤いもなくなってきているのは顕著だ。たまたま深夜のテレビで『女性向け風俗店』の存在を知った。
へー、そうなんだ、くらいにしか見ていなかったけれど、見ているうちに、わー、呼んでみたい、に気持ちが移行していた。なので思い切って明日の誕生日に呼んでみることにした。だって『平成最後の誕生日』なのだし。あたしの女の部分はまだ幸いにも残っていたようだ。
「こんばんわー」
待ち合わせの場所にぼーっとたっていたら、背後から語尾をあげながら挨拶をする男性に声をかけられた。振り向くと、そこには茶髪の若い男の子がいた。カラコンの青い目が前髪の隙間に垣間見える。
「あ、わ、はじめまして」
「かずこさん? ですよね? その赤いバックと白い靴」
その出で立ちのままのあたしは、首を小さく曲げてうなずく。けれど……。若い。なるべく、年齢の高めの男性でお願いします。と、前もっていってあったのに。
「行きましょうか」
目の前の男の子はそう続けた。とても自然だったのであまり驚かない自分に驚く。若いけれど、女性の扱いにいたってはあたしよりも何百倍も勝っている。
「どこに?」
「えっ?」
どこに? 男の子はあたしの言葉を繰り返して、ははは、と笑う。
「どこに行きたいですか。てゆうか、僕、たくやといいます」
やっと、名を名乗ったたくや青年は屈託なく言葉を継いだ。かずこさんの行きたいところへ。どこでもなんでもいいですよ。鷹揚な声が心に沁みる。あたしの子どもでもいいくらいの年齢なのに。そんなこと微塵たりとも思わせない自信たっぷりな行動に目をみはる。
あたしはホテルに行き、あんなことやこんなことを。などどありきたりなことを考えていた。そのつもりで呼んだわけだったけれど、なんだか気が変わった。
「えっと、今から一緒にケーキバイキングに行ってくれませんか?」
誕生日なので。ということは心の中でいう。たくやくんは、えっ? と、豆鉄砲をくらったような顔をして、いいですよ。と、素直に従い微笑む。僕、甘い物が大好きです、そう付け足して。
あたしたちは待ち合わせ場所から手を繋いでカフェまで闊歩した。たくやくんは人の目も気にしないであたしの手をとり、時折抱きしめたりしながら夜の道を並んだ。
春の夜気はあたたかさとつめたさが混在していて手に汗をかく。
「手、汗ばんじゃったね。ごめんね」
信号待ちでのタイミングでそう告げるとたくやくんは、繋いだ手を離すどころかブンブンと高く振り上げて
「かずこさん、お誕生日、おめでとう!」
深夜0時。
ほとんど吠えるような大声で叫んだ。
「えっ?」
~アオイシーツ~
隣にいる人はガーガーといびきをかき、ときおりおならをしながら、あー、だとか、うー、だとか寝言をいいながら快適に眠っている。あたしはシーツにくるまりながら天井をじっと睨みつける。保安灯の中でも天井の模様がわかるのは見慣れてしまいおぼているのだ。
いちいちの寝言があたしの眠気をさらっていく。明日も寝不足確定だ。
嘘でもいい、義理でもいいから、抱いてくれたらいいのに。
彼とはもう三ヶ月ほどいとなみがない。こんなにも大好きなのに。こんなにもそばにいるのに。こんなにも……。ああー、もう! 隣にいる人を起こさないようそうっと布団から出る。
そうしてスマホの画面に目を落とし、『女性専用風俗』サイトを覗く。お金を払ってまで男性を。そのような思考などあたしの中ではまるで皆無だった。けれど、たくさん羅列されている女性が書く感想レビューを読むたびに自分に投影をしてみた。
「女性専用風俗は浮気になるのかなぁ」
心の中で自問自答をする。男性だって風俗にいく。そうして風俗は浮気じゃないなんて平然といってのける。彼は風俗にいったことがあるのだろうか。同棲をして3年。そのような素振りなどみられないけれど、出張がたびたびあるので本当のところはわからない。
一度だけ。
あたしはあまりのさみしさと孤独さから禁断の扉をノックした。
禁断の扉はあまりにも誇張すぎだと、実際にマスダさんにあって苦笑いを浮かべた。
「わりと普通なんですね」
あってすぐに思った感想を述べた。「わりと普通ですよ。一体どんな想像をしてたのかな」マスダさんはくつくつと笑う。あたしもいちいち笑った。
「どうにでもしてください。今夜だけは」
なんでもわがままを訊いてあげますよ。マスダさんのブログにそう書いてあったし、女性側のレビューも好印象なことばかり書いてあった。マスダさんは目を細めながら、いいですよ、と、だけ短くいい、あたしたちは待ち合わせ場所から一番近いラブホテルに入った。
「わー、何年かぶりにホテルに入ったなぁー」
つい感嘆の声がでた。「あはは、そんなにはしゃぐの? かわいいね。あおいちゃん」
「だって、」
その瞬間唇を塞がれ、ベッドに押し倒された。はっ、として身体を強張らせると、すぐ真上にマスダさんの目があった。目の中にあたしの目が映っている。黒目が茶色いなと思った。カラコンかなとも。
「強引だったかな? あおいちゃんあまりにもかわいいから」
ごく自然に出る声は常套句だろう。それでもおんなあつかいされている方のが嬉しくて心臓が早鐘を打つ。事前にシャワーを浴びてきてよかった、と、胸をなでおろしあたしはそのまま目をつむった。
マスダさんの愛撫は『女慣れ』を通り越しているほどあたしの快感を得るツボをしっかりとおさえていたし、それに従ってあたしの身体からはたくさんの愛液とたくさんの嬌声がこぼれた。
散々いきまくってしまい身体が弛緩している中、天井をじっと見つめる。うちではない知らない場所の天井。
マスダさんはあたしの頭をなぜてくれている。
うちに帰って青色のシーツにくるまりたかった。彼は今夜遅いだろうか。ふと、彼に対する愛情の深さと脆さを同時に知った気がした。
「時間だね」
~こどもじゃないもん~
「せなちゃんはほんとうにかわいいね」
あら、今さら気づいたのかしら。百瀬さんは。あたしははらりとスカートをひるがえして夕焼け空をバックにいちいちかわいい仕草をして微笑んでみる。それからこう続ける。
「あたしなんてありていにいえば『かわいいほう』かもしれないわね」
「わぉ。認めたなぁー」
だって、百瀬さんの顔は夕日を背にしているので顔が真っ黒に見える。顔の様子がわからない。それでもクスクスと笑い声だけが春の夕方の風に乗って聞こえてくる。
「だって、若いからかわいいだけなの。若いから。若くなかったらかわいいなんて言葉をもらえないでしょ?」
あたしと百瀬さんは端から見たら親子ほどの年の差がある。お父さん? あるいは、ちょっと年の離れたお兄さん? 誰が見てもそう思うだろう。しかしまるでそれは違う。
百瀬さんは出張性感ホストのスタッフさんだ。39歳の百瀬さんは見た目も喋り方や仕草だって嘘偽りのない39歳。別に年上が好きだとかファザコンだシスコンだ、と、いう小説やドラマに出てきそうなエピソードなどはまるでなく至ってノーマルな家庭で育ち、今は衣服の専門学校に通っている。百瀬さんとの歳の差はちょうど20歳だ。
「せなちゃん今日はどこにいくのですか?」
2、3歩後ろを歩く百瀬さんの影が長く伸びている。まるであたしの身体を呑み込むみたいに。ついてきて、その口調はちょっとだけ命令ふうにもとれるし決定されているなにかがある、というふうにも聞きとれる。
「でもさ、結局ここなんだよねー」
結局ここなんだよね、といった場所は格安のラブホテルだ。専門学生の実家住まいではお金がない。じゃあ、一体お金はどこで捻出をしているの? 百瀬さんは以前質問をしてきた。「ナイショ」あたしは口に指をあてがい、ナイショだよ、と、秘密めいたことをした。けれど、百瀬さんはそれ以上込み入って聞いてはこず、むしろどうでもいいことだったなぁ、と心の中でのつぶやきが聞こえた。
部屋に入ると急いで窓を開ける。よかった、まだ、おもては自然のあかりを保っている。
「早くしないと、自然の光じゃなくなっちゃう」
あたしはほとんど百瀬さんを急かし自分も急かして裸になる。無造作に脱いだ洋服などおかまいなしにベッドになだれこむ。
「見て、あたしの身体」
「うん、とても綺麗だよ」
水でもなんでも跳ね返しそうなハリのある肌。お椀型のおっぱい。シミもシワもない化粧っ気のない顔。
あたしは百瀬さんの頬を両手で持ちそうっと顔を近づけて唇を求めた。吸って吸って吸いまる。まるでスケベオヤジみたいだなぁ、と思いながら。百瀬さんの頬はとてもスベスベで気持ちがいい。あたしの頬と同格にさえと思う。キスは率先しておこなうがその後の愛撫やらは百瀬さんの出番だった。最後まではしないけれど、その手前まではきちんとおこないあたしの理性を崩壊する。どんどんいやらしくなる。百瀬さんとあうとまた大人の階段を上ったと錯覚する。錯覚? 錯覚なのだろうか。あたしはまだほんとうの恋を知らない。
「月に一度だけどね、」アスパラガスの缶詰のようにベッドの上でくっついている。「うん、なあに」あたしは先を促す。
「せなちゃんはだんだんと綺麗になってく」
「……、うん」
天井に目を向けている百瀬さんの横顔が好きだ。好き、あたしはこの人にお金の介在する相手に恋をしてるのだろうか。
「けどね」百瀬さんがあたしの方に身体の向きを変え抱きしめる格好になって、けどね、と、つづける。
「若いからかわいい、ってそんなの関係ないんだよ。せなちゃんはきっとあと、20年しても今のよう華麗でかわいいはずだよ。だから、」
まって、あたしはその先の言葉は聞きたくなくてまたキスをしその言葉を遮った。
だから、老いることにおびえないで。きっと、彼はそんなことをいいたかったのだろう。見当がつく。
老いは誰にだっておとずれる平等な過酷な試練。痛いほどわかっている。
あたしは衣料ではなく医療福祉の専門学生で(百瀬さんには衣料と告げてある)たくさんの老いた女性たちを目の当たりにしている。バイトも福祉に携わるところでしているのだ。
「怖くはないのただね、後悔をしたくないだけなの」
~サクラ・サク~
「うーん。もう少し顔を上げて、あっ、そう、そう、その顔! いいよ! あっ、ちょっとその顔で静止してー」
その徹底的瞬間を逃すまいとあたしはがむしゃらにシャッターをきる。一場面だけでもざっと50回くらいはシャッターを押す。昔流行ったボタンゲームが得意だっただけある、だなんて考える自体あたしはもう若くない。
「えー! このまま静止っすか? ゲゲッ」
宙を見上げ被っていたキャップがちょうどいい具合に目を覆っている。斜め45度の顔は真正面から見るよりもいやに妖艶にみえる。
「いいよ! かっこいい!」甘ったるい言葉をささやきながらカメラを構えて写真におさめる。甘ったるい言葉は誰の顔も優しさで溢れさせる。『かっこいい』あるいは『かわいい』カメラマンはこの言葉を魔法の言葉だと信じて疑わないのだ。てゆうかあたしはそうだ。
「もう、いいよ。楽にして」
決めポーズをつくっていた『ヤシロくん』に声をかける。あー、明日まじで筋肉痛かもー、と、ヤシロくんは手で顔を覆った。細い指だし白い手。ごつい腕時計がいやに浮いている。「けど、」顔を上げたヤシロくんは話しを続ける。
「俺みたいな素人を撮っても楽しくないっしょ? さやかさんは。だって、」
「まって!」ヤシロくんがまだ話しているけれど遮って今度はあたしが続けた。
「素人だからいいの。だってなんていわないで」
「でも、」
でも、も、いわないの。あたしは少しだけ怒気を含んだ声でたしなめた。はーい、すんません、と、ヤシロくんは肩をすくめ、腹減ったなぁ、と、付け足す。
「何が食べたい?」
「さやかさん」
「ばか」あたしはふふふと、笑う。彼もクスクスと笑った。
ヤシロくんは『レンタル彼氏』だ。お金を出して買っている。時間と身体を、だ。23歳という若さ。細マッチョな色白のその身体。小顔だし色気がある。カメラマン(アマチュア)のあたしは主に人間を撮っていて気に入った人がいたら飽くまで撮り続ける。しかし、ヤシロくんだけはなぜだかまったく飽きないのだ。キスもするし、裸になって抱きしめあっていてもだ。
あたしはじき50歳に手が届こうとしている。
「飽きないの」
今夜は、肉が食べたい、と、騒ぐのでこじんまりした焼肉屋に来ている。焼くのはもっぱらあたしだ。この店は昔ながらの店で煙りがもんもんで目にしみる。
「飽きないよ。俺、肉食だもん」
「あ、うん、そうね。うん、あ、これもう焼けてるよ」
焼けたお肉をヤシロくんのお皿にのせる。うまい、うまい、その顔はほとんど小学生の男の子のようだ。育ち盛りか、胸中でつぶやく。
飽きないの、ってお肉のことをいったわけではなかった。あなたに飽きないの、そのつもりの言葉だった。彼は本当はわかっていたのかもしれない。けれど、重たい空気にはしたくないし、あたしはあくまでお客さんだ。常連のお客さん。
「あのね、もう一時間だけ延長いいかな?」
「えっ、」んー、ヤシロくんは顔を上げ、やや長考したのち
「すみません」
思いがけないこたえが返ってきた。「もう次埋まってるんですよ」
「そっか」そうだよね。急だったものね。かなしくなったけれど、そっか、以外の単語はいわなかった。
「今度はね、桜の下で写真撮りたいな、いい?」
「いいですよ。でも、早くしないと散ってしまいますよ」
ええ、そうね。あたしはもんもんの煙の前にいるヤシロくんを探す。ヤシロくんは焼肉屋でなくてもあたしにとってはいつも蜃気楼の中にいてそれでいて雲の上にいてまるで架空の人ようだ。
「また、店に連絡いれるわ」
「はい!」
好きになってはいけない。年齢とかではない。彼は『レンタル』なのだから。写真の中だけはあたしだけのもの。カメラマンで良かった。
この歳になって初めて自分の仕事をこころから好きになったし、人間を好きになる気持ちも知った。
男を買う。いや、あたしは心を買っているのだ。
「あ、すみません、カルビあと、2人前!」
彼は容赦なくよく食べる。
「飽きないの」
~ジェラシー?~
ユズキ(柚木)とは『女性専用風俗』で出会った。ユズキはお店の源氏名で【皆側ゆず季】となんとも風情のあるホスト名だけれど、本名は【柚木翔】といい、これもまたホスト然たる名前だね、と、一緒に住み始めてからいくどとなく会話に登場するようになった。
「りかちゃん〜」
ユズキは天性のホストだと思う。甘いマスクに甘い声。それにその体躯。身体がすばらしく綺麗なのだ。ユズキ目当てのお客さんはたくさんいる。ファンクラブがあるみたい、そんな芸能人みたいなことをさらっと口にする。
「へー」あまり興味がないので聞き流す。「嫉妬しないんだ。りかは」嫉妬? 嫉妬などしていたら身体も心もとうにおかしくなっている。
「いいえ」しないわよ。あたしはつとめて平然を装うけれど本当にあまり嫉妬をしていないのかもしれない。だって、ユズキはいつもあたしのところに帰ってくるのだから。最後はあたしのところに。
彼女ではない。なのに。一緒にいる。
1年前くらいに知った『女性専用風俗店』は好奇心で呼んだ。誰でもよかったし喋り相手が欲しかった。都会での一人暮らしは心もとない。そんなときに出会ったのがユズキだった。
「えー! 同い年なんだ」から話題は始まり「えー! 出身◯◯とか同中じゃん」みたいな偶然があたしの心を潤し、何度も何度もユズキを指名した。アパートだったのでホテル代はかからない。そうこうしているとき真夜中チャイムが鳴って、えっ? だれなの? こわい。あたしは防犯用の金属バッドを持って玄関の扉を開けるとそこにユズキが捨てられた猫のようにぼんやりと立っていた。
「行くとこがないんだよ」
真夜中の突然にあらわれた訪問者にあたしは特に驚くこともなくすんなりとうちに入れホットミルクをマグカップに注いでユズキにのませた。
なにも喋らない彼に対してあたしもなにも訊かなかった。その夜始めてお客さんではいあたしは彼と結ばれた。お店では最後まで禁止だった。けれど、ホストでないユズキはまるで子どものよう震えながらあたしを抱いた。その夜のことは今でも鮮明に覚えている。あの日から彼はいつのまにか猫のよう居座っている。
追い出すこともなくかといって養っているわけでもない。彼はきちんと毎月お金をくれる。ユズキのことを彼氏だと思っているオンナの子には罪悪感などは皆無。ユズキはプロの出張ホストとして夢と時間と癒しを売ってお金に換金しているのだ。あたしは影でそれを見守り話を聞いてあげる同居人。
「明日さ、りかお花見行こうよ。休みだろ?」
「え? うん。休みじゃないけどね。遅番だし行けるよ」
そんなあたしの職業は風俗嬢。彼も知っている。風俗嬢だからといって心までは売らないしあたしだってプロに徹して仕事をこなしている。どんな仕事だって矜持を持ってしていたら胸をはることだって出来るのだ。あたしは風俗の仕事は立派な仕事だと思っている。
だからユズキに嫉妬もいだかないし逆に応援したくなるのだ。
「花粉がさ、すげーなぁ」
「すげーなぁって」
ユズキの鼻から鼻水が垂れている。鼻かんでよ。あたしは急いでティッシュをひっぱりユズキに渡した。
「ゲゲ、なんかさ、エロッ」
「ん?」
~アイジンのおきて~
「ま、まじっすかぁ!」
「これ、あげる。欲しいって前にいってたよね」と、前置きをして渡した青いリボンの中の小箱を開けたユイトはまるで漫画でよくみかける目玉がとびでたイラストの男の子にすごく似ていた。
「ま、まじで……」
まるで信じられないとでもいうよな真顔でもう一度つぶやく。
「受け取って」「で、でも」この押し問答を3度ほど繰り返しやっとユイトはそれを手に取った。まじで嬉しいっす、ありがとうです、と、付け足して。
「でも、」ユイトが手に取ったものを見つめつつ「一体梨華さんってなにものなんですか?」と、探るような目つきで質問をしてきた。と、ついでに何歳なんです? どうせなら訊いてしまえ。俺。ユイトの心の声が手に取るようにわかる。なので質問が2つになった。
「MODEAL(モディアル)はおとなしいデザインだしシンプルでしょ? けどサイコロの形をしていてプラチナなんてイケてるって思わない?」
質問とはまったく違うことをこたえた。あたしも同じものもってるわ。「へー。けど、梨華さんじゃメンズだし重たくてごつくないです?」
「いいえ」あたしは首をよこに振った。いいの。ごつい方が。なんかね、強くなった気がするもの。ユイトの顔が歪んだ。うまく笑えてはいない。
部屋の中の音が消える。無言の空気がたれこめる。たっぷりした時間を要したあと、あたしの方から口火を切った。
「あのね、」「は、はい」ユイトの身体が前のめりになる。
あたしね、あたしの職業はね、アイジンなんだ。で、年齢は23歳よ。
「アイジンって? あのアイジンなの?」
あたしは苦笑しながら「ほかにアイジンなんていう職業があるのかしら?」ユイトは肩をすくめてみせる。
「あたしだからユイトより1つだけおねえさんになるわね。もっともユイトの年齢が嘘でなければ」
高層ビルの外から小さな雨音がBGMのよう聞こえてくる。あ、雨降ってきたみたいね。ユイトはまだ黙っている。
「65歳の社長の愛人よ。20歳からずっとね。高層マンションに住まわせて好きなときにあたしを抱きにくるの。けれど、年齢のせいっていうの? 勃起がままならなくてね。自分の下半身が不自由になると男っていきものはどうしてだか女の方に怒りの矛先を向ける。あたしを四つん這いにして背後からクスコを膣に突っ込んで中を見てね『おー、なんて綺麗なおま◯こだ』とか『おまえの子宮は下付きだな』とかいって婦人科の先生みたいな口調になるのよ」ふふふ。
唖然としているユイト。あたしはさらに続けた。
「膣の中を見てて興奮をするのかそのまま舌先で舐めてくるの。最初はいやだったけれどね、けど、けどさ、その舌でイっちゃうの……」
ー女だということにたまに絶望をするの
雨の音がさらに強まる。あたしの声は雨音に負けている。頬にも雨がつたう。ぐっと抑えてきた感情が吹き出してしまった。出張ホストであるユイトの前では絶対に弱音を吐かないし本性はあかさないと決めていた。
「もういい」
真っ白なシーツをふわりと被せてユイトはそのままあたしを抱きしめる。糊の清潔な匂い。
「誰にだって秘密はあるし泣きたいことやどうしょうもないこともあります。僕も嘘ついてます。本当は19歳です」
シーツ越しに聞こえる声と熱気。あたしは肩を震わせ声を押し殺して泣いた。お金に困っているわけではないしこうやって好きにホストを呼んで高級ネックレスを買いあげく職業が愛人でクスコでおま◯こをみせる。23歳のあたしはこの先どうなっていくのだろう。ねぇ、ユイト教えて? あるいはあたしと…。
~きらいにならないで~
『あのぅ、初めて利用するのですがぁ……』
男性とつきあったこともなく男性と喋った記憶など小学生以来ないくらい男性との接触がないまま40歳になっていた。女子校のうえ、女性ばっかりの職場に配属され内気な性格上友達も出来なくてこのまま死んでくのかなぁ、と、考えていた矢先で知った《女性向け風俗店》
『はい、大丈夫ですよ』
電話口の人は女性だった。『初めての方たくさんいらっしゃいます』女性の声は快活そうであかるい声だった。不安などなにひとつ感じさせない。『どのような男性が好みですか?』さらに女性は続ける。
『どのような、ですか』
『はい、タイプです』
あたしを見ても笑わない人なら誰でもいいです。
『おまかせします』
『わかりました』淡々と話しは進み、今、ホテルの一室でおすすめのホスト(みすずくん)を待っている。
あたしはかなり太っている。かなりというかものすごく。あげく摂食障害で過食症。あたしはいったいなにを望んでいるの。
時間どおりあらわれた(みすずくん)は、えっ? と逆の意味で見紛うほどそこらへんにいる男の人だった。えっ? そんな顔をしていたのだろうか。みすずくんが、あはは、と、声をあげわらう。
「あ、今、僕を見て、えっ? この人がホスト? って思ったでしょ? ゆきさん」
あっ、えっと、あたしは必死に首を横に振る。ち、違いますって。そういいかえす。
「あ、でも逆にあたしみたいな巨体がいて驚いたのではないですか?」
目の前の彼は特別おどろいた様子ではない気がしたけれどあえて訊きたくて質問をした。こたえは期待通りのものではなくてむしろあたしのささくればった心を癒した。
「ははは。はい、驚きました。すみません。けれど、これほどまでふくよかな女性初めてで逆に興味がありますね」そこまでいってあたしを抱きしめる。わ、男性に抱きしめられている。いい香り。男性ってもっと獰猛な匂いの印象があった。
「けれど、ゆきさん、僕もそうですが、人間は見た目ではありません。その人にはその人の良さがあって人生があって、こうやって出会った縁はきっと最初から決まっていたんですよ。どうかゆきさんが僕と出会ったことで吉になりますよう」
背中に腕が回る。まあるい背中。大きなお腹。それでもみすずくんはあたしをきつく抱きしめた。あたしの頭を抱え込むような形になる。目に入ってくるのはみすずくんのスーツのズボンだった。
あっ、視界に拾ったものを見て声を上げる。なに? 上から声がしてみすずくんがあたしから離れた。「かわいい顔してるね。ゆきさん。うん、顔が赤くなってる」
「もう、嘘いわないでよ」
正直嘘でも嬉しかった。キスをしてほしい。会話が和んできたころお願いしたら、目を閉じて。の声と同時に唇に温かいものが触れた。涙が出るほど嬉しかった。
それ以来何度も指名でみすずくんを呼びその度にあたしはあかるくなっていったし『最近痩せたみたいね』と仕事先でいわれた。
人生の諦観からの脱出が『女性向け風俗』だった。けれど今あたしはますます元気だし毎日がひかってみえる。
「ふふふ」
あたしはあの日みすずくんのスーツのファスナーが開いていたのを見つけてしまったのだ。チャックを閉め忘れるホストなんているのかしら。あたしは盛大に笑った。忘れかけていた笑顔に次の日顔が筋肉痛になったくらいだ。
「笑って生きないと損ね」











