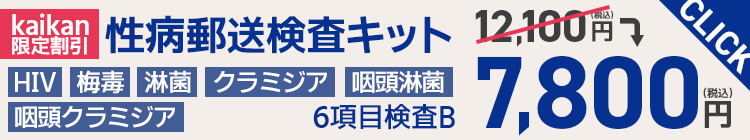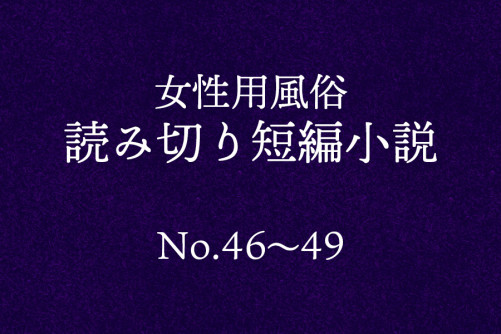
【女風小説】46話~49話(最終話)1話数分の読み切り短編サイズ
~そのきにさせて~
「今度あった時絶対に教えるからさ――」
まただ。
アヤメくんを疑っている訳ではないし、お金を介しているし、ただのお客だってわかっている。わかっているけれどもう何回も(といってもまだ5回目)指名しているのにLINEを教えてくれないのはなぜだろう。アヤメくんを指名する前に気に入って呼んでいたマサオミくんはあったその日にLINEを教えてくれたのに。
けれど、と思い返してみる。マサオミくんにしょっちゅうLINEをしていていつのまにかブロックされていた過去がある。あたしは多分ひといちばい、いやひとにばいほど嫉妬深く貪欲だ。しかしお金を払っているのはあたしだしでもっと器用にあたしを利用できないかなぁって思う。LINE連絡をとりあえばお店を通さずにあえるわけでお店おちのお金だって彼にはいる訳だし。
あたしが逆の立場ならそうするよ。とは本人目の前にしていえやしない。
「そんなことよりもお風呂はいろ。お風呂」
お風呂ぅ? あたしはおどろいてしまう。いつのまにバスタブに湯をはったのだろう。
「ななちゃん〜、本当にかわいいんだから」
どうやら顔が多少のお酒のせいで赤らんでいるのだろう。頬赤らめて〜、とくつくつと笑う。
「うん。わかった。けど今日は絶対にLINE教えてもらうからね」
すっかり裸になっているアヤメくんの胸板が目に優しくない。この胸板に出会ったばかりにあたしは彼に狂ってしまった。アヤメくんはモテてモテてしょうがないのだろう。いつも予約で満員御礼状態。
バスタブに一緒に入り対面して抱きしめてもらう。そうして濃厚なキス。とろけそうな抱擁。無駄な肉のないその体躯はどうして保っているのだろうと身体の中をのぞきたくなる。
「やん、恥ずかしいよ」
あたしのおっぱいを揉み柔らかくて気持ちがいいといつもいう。天然物だ。とも。たまに天然物ではない子もいるようだけれど彼はそれはそれでいい個性だしね、とつけたし、女性は皆かわいいよとさらに続ける。
「けどね」
「けどね? ってなあに? ってもうそこはやだ。くすぐったい」
太ももに手をもっていきゆっくりと陰部をなぜるよう愛撫する。『手マンをする男など信じてはいけないよ』はアヤメくんの口癖。
「けどね――」アヤメくんは話を続けた。納得をする文面に100点マークをあげた。その後たくさん愛してもらいホテルで別れた。
これでいい。これ以上望んではいけない。
「ホストの僕だけを好きになってくれればいいんです。ホストっていわゆるアイドル的なところじゃないですか? アイドルとはまるで違うけれどファン(常連)は大事にしたいから。あえてプライベートはあかさなしLINEばっかしてきても俺その子嫌いになっちゃいそうだし。まあめんどくさがりだからね。だからね。好きだからあえて教えないんです。逆にもう会いたいないって思ったら教えますよ」
クロールで100メートルを息継ぎなしで泳ぎきったよう一気にいいきった。アヤメくんはいいおえたあとはーはーと肩で息をしていた。
「そっか」
プロに徹しているなぁ。とほとんど感心をしたしますます彼を好きになり応援したくなった。
「また呼ぶ。いい?」
~ほけんをかける~
恋ってしなくても死なないけれど、していても死にたくなることもある。なんなら両思いの不安な動作のいちいちよりも片想いのドキドキの方がまだいいと思う。
「恋は依存性があり猛毒で自分を失うおそれがある――」
目の前の男にそういってみる。ことを済ませて男はひどく子どもじみた顔をしている。つるんとした顔に毛穴など見つからないしヒゲもなけれはヒゲ後もない。絶対に永久脱毛をしている。
はぁ? なんだそのできそこないの川柳は。バカにしている口調でやっぱりバカじゃんという顔を向けあたしの首に腕をまわす。
「ミカちゃんの身体ってなんかさ、こうエッチだよね。ずっと触っていたいもん。俺」
男はそういいながらもう片方の手で脇腹を撫であげる。アンッ、感じやすいのでつい声が出てしまう。
俺にそんなこといわせるなんてもうミカちゃん最高かよ、と、付け足す。
「あは、どうもありがとう」
「どういたしまして」
男の手はまたさっきのおこなった通りの順番で脇腹から太ももに移動しつるんとした割れ目に人指し指をあてがう。あたしも人のこといえないんだった。陰部の毛は永久脱毛済み。割れ目をそうっと割っていきとろとろの液体を指先に絡ませ小さなお豆をコリコリとこねくり回す。
「あーあ。またこんなになって。おもちゃ使う? また?」
んんん。あたしは必死で首を犬のようにブルブルと横にふり、このまま指でして、と懇願のまなざしを送る。かんなくんの指がは媚薬でも塗ってあるんじゃないのか。と突っ込みたくなるほど絶妙な部位を刺激してくる。外したことなどないように。あたしの身体の全部を熟知しているかのように。
「アーッ、またイくぅー」
頭が快楽を憶えてしまっているのでイクのなんかはカップラーメンを待つよりも早い。何回もイケるしなにせあたしは『外派』なので出張ホストにはおあつらえむきなのだ。決して挿入にはこだわらない。
指あるいはおもちゃでイカされ嘘でも愛されている証が欲しい。そうでないと死んでしまう。かんなくんだけではない。呼んでいるのは。けれど出会い系などしようとかはまるで思わない。だってこわいもの。
安全と愛と時間をお金で買っている。そう思うとまた生きている証拠にもなる。
「身体がね良くても、本当に好きな男は去っていくのよ」
2度も果てておいてまたもや話を続ける。
「そうかなぁ。俺だったらミカちゃんのこと飽きないよ。多分」
多分。ねぇ。その台詞はどの男からも最初に聞いて最後はいつも『重い』とか『うざい』とか『性欲が強くて無理』などという意味のわからない暴言とともにすっかりとあっさりと振られる。あたしは自慢ではないけれど男を振ったことがない。もっぱら振られるだけだ。かわいいのに。なんて。
「こうゆうさ関係がいいのかもね。だってきっとあたし振られないでしょ? こんなにエッチでも」
てゆうかさすがホストだね。あたしをここまで喋らせてさ、とあたしは笑う。え? てゆうかミカちゃんが勝手に喋ってるだけじゃん、とかんなくんも白い歯をみせながら笑う。
「どうして男と女ってきりがないのかしら」
~りゅうじ~
―― う、うまくなってる……。
3ヶ月と20日ぶりに出張ホストである『りゅうじ』を指名した。その日りゅうじくんはなんとこの世界に入って初めてのデビューだった。その1番客だったのがあたしだ。そうゆうあたしも『女性向け風俗店』は3回目だったうえ男性にも慣れていないのだからりゅうじくんとの時間はなんともぎこちなさだけしか印象がない。
「あ、すみません」とか「あ、もっとこうしてほしいことありますか」とか「背中が綺麗ですね」なんていうどうでもいい世辞を並べて気をつかいその会は気もそぞろに終わった。
「ねえ、ちょっとだけいってもいいかな」
あまり語尾を尖らせない程度にしりゅうじくんと向き合った。はい? 彼のポカンとした顔はいまだに思い出しても笑えてくる。子どもじみた顔。まだ23歳という顔。
「これからね、もっといろんな経験を重ねていくと思うの」あたしはそこで言葉を切る。りゅうじくんの目は真剣な眼差しになっているのを確認し続ける。
「でもね、これだけは憶えていてほしいんだ。女はね、線香花火みたいなものなの。燃えている最中はあちらこちらに火の光線をなげかけ男に電波を送るわ。けどねその電波の終焉とともにまあるい熱の塊になるの」
うん、うん。彼は顎を引き真剣に聞いている。で? 先を促されたので
「熱の塊のときが、地面に落ちてしまう前がいちばん熱い余韻があるの。だから最後まで抱きしめてあげて。いくら突飛なサービスでもね、最後が大事なの。最後の抱擁が。熱くなった塊をりゅうじくんの身体でそうっと冷やしてあけて――」
女はなにせ包まれたいのだ。余韻を大事にしたい。線香花火は女性に似ている。そのことがいいたかった。
「うーん」
彼は唸ってなにかを考えていた。至って図面通りの言葉に態度だった彼はまだ原石でこの先の接客次第で上にも下にでもなれる。
「ごめんなさい。あたし。知ったかぶりね。嫌味なねーさんだと思ったでしょ?」あたしはそういって顔をしかめた。いいえ、りゅうじくんは首をよこにふってから、最初がハナさんでよかったですよといいながらクスクスと笑った。あどけない笑いだったけれどどこかでなにかを決心した笑いに見て取れた。
「ハナさん僕の胸の中におさまってください」
3ヶ月と20日前のりゅうじくんとはまるで別人のよう女性に対するあれやこれが上達していた。変わってなかったのは可愛い笑顔とポカン顔だけ。
「たくましくなったわ」なのでそういった。うまくなった。はどうしてだかいえなかった。
そうかな。彼は鼻の下を指でこすってうふふと笑う。あたしもほんとうにたくましくなった胸の中におさまってうふふと笑った。
「あれから、」りゅうじくんが独り言のようにつぶやいたのでとくになにもリアクションもなく耳をそばだてた。
「あれからたくさんの女性と出会いました。本気になられたこともあります。線引きはむずかしい。僕は仕事でこなしているから。けど惚れていただくもの仕事だし。あ、でもうまく交わしてます。そこらへんは熟知しています。割り切るのもうまくなったし」
あ、僕喋りすぎだ。だってハナさん師匠みたいなものなんだもん。とまた笑う。いやいや師匠呼ばわれされたくなぁといいあたしも笑う。
「けどこうやって笑いあえることって素晴らしいじゃない。素敵だわ。熱の塊をうまく中和してる」
きっと接客していくうちに身についたのだろう。彼はうまく立ち回っている。もうすっかりプロの顔だ。
「僕、この仕事好きです。女性は奥深い」
「そうね」
~しゅうと~
後悔をしている。
あたしの生活圏内に『しゅうと』が加わってしまったことに。何をしていてもしゅうとのことばかり考えているししゅうとのブログやTwitterやインスタにおよぶそういったことまで1時間おきにチエックをしているのだから。ぶっちゃけとるにならないけれどストカーかもしれない。
「おい! 何ぼーっとしてんだよ。手を動かせよ。手を」
背後からの声におどろきはっと我にかえる。す、すみません、と小声であやまり、急いでキーボードの上で指を踊らせる。時給泥棒じゃんよ、たくっ、と、舌打ちする上司に、いやいやあなたにあたしの恋心なんてわからないのよ、と心の中でみえない舌を出す。仕事にまで影響を及ぼすなんて。あたしは本当にしゅうとに恋をしているのだ。
「すっげー、大人しいんですね。あきこさんって」
真夏の夜気はむわんとして昼間の熱が空気に混じっている。背中に汗粒がツツツーと流れるのがわかる。しかし目の前の愛しい人はほとんどさわやかな笑顔で無邪気な目を向けてくる。
「あ、うん。大人しいかも……。ですね」
すみませんとあやまりうつむく。あ、いやいや大人しいって悪い意味でいったわけではなくて、と、しゅうとはあわてて口をひらく。
「大人しい女性も好きです、って意味です。みなさんの個性ですから」
「はぁ」
個性ねぇ。個性かもだけど緊張して喋れないなんていえない。あたしはどちらかといえばお喋りな方だし女友達によれは『うるさい』方よりらしい。しゅうとはさらっとあたしと手を繋ぎ、どこに行きますか? と質問をする。
あーー! しゅうとの手があたしの手と繋がってるぅー! キャー! ヤダァ! 動揺をみせないよう努めながらぎゅっと手を握り返した。もうこのままどこか連れ去ってほしいの。なんてまるで映画の中のヒロインになっている。
レンタル彼氏——。彼はレンタル彼氏だ。本当の彼氏ではない。月に3回と決めてあっている。会うたびに好きになり会うたびにあたしは映画の中のヒロインになる。自分じゃない自分。大人しいキャラ設定のあたし。嘘だらけの仮面を被っているあたし。
「焼き鳥屋にいきませんか? 僕大好きなんですよ」
歩いていたら飲屋街の赤ちょうちんが目に何個も入ってきた。そういえば緊張と会える喜びですっかり空腹を忘れていた。
「はい。あたしも大好きです。焼き鳥。特に軟骨が」
「……、ナ、ナンコツ?」
軟骨が好きなことが何か腑に落ちないのだろうか。あたしはしゅうとの横顔をのぞき込み、しゅうとも一緒にこっちを向いたので向かい合う格好になった。
「ナンコツってなんですか?」
「えええ!」
あたしはまったくおどろいてしまう。つい大げさになってゲラゲラと笑った。
「若い子は軟骨は食べないのかなぁ?」ボソっというと
「あきこさんと僕同い年ですけどね」としゅうとはクスクスと笑う。てゆうかあきこさんって本当は酒豪じゃないんですか? ええ?
いいえ。あたしは首を横に振って認めなかった。しゅうとの前でははかなげでいたいんだもの。
「かわいいな」
しゅうとは突然あたしを引き寄せてキスをした。たくさんの人のいる飲屋街の真ん中で。
こうゆうことをするところが好きなのだ。あたしを大人しくさせる魔法をかける彼が。好きになったキセキ。ホストでもしゅうとはしゅうとだ。
「後悔はしてないわ。やっぱり」
「え?」