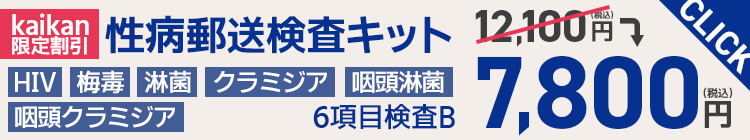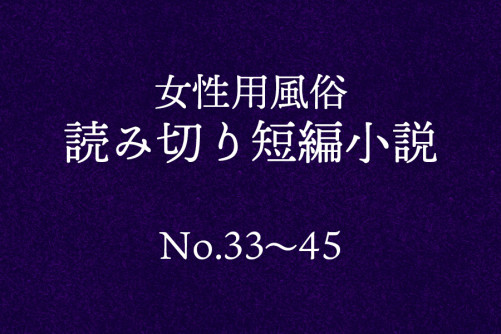
【女風小説】33話~45話|1話数分の読み切り短編サイズ
1.
~シメイナシ~
2.
~ホンキでスキに~
3.
~しばられたいの~
4.
~ここからだして~
5.
~ウランくん~
6.
~マネー&ラブ~
7.
~おどろかないで~
8.
~うさばらし~
9.
~きままもいいけど~
10.
~おんなどうし~
11.
~フウフ・エンまん~
12.
~それは・あるひとつぜんに~
13.
~ジェラシー~
~シメイナシ~
「ショウコさんって愛に飢えてますね。きっと」
目の前にいる出張ホストはいとも簡単にあたしの心を見透かすことをいいきった。
「だって、貪欲ですもん」
と、さらに付け足し
「それに絶対に指名しないでしょ?」
と、続ける。
指名しないって。それは全く関係なくないか? そう内心で思いながら、あ、そういえばあたしってば指名しないなぁ、と気づく。
「今度はこの僕。イチムラをぜひともご指名くださいね。ショウコさんに指名されることがないからキャストの間で『ショウコさんから指名があったらそのキャストに1000円を払うって企画があるんですよ」
は? あたしは口をあんぐりとし
「なにそれ?」
眉間にシワをよせながら訊いてみる。冗談じゃない。あたしのことをかけるなんて。そう喉の底まで出かかったけれどやめて
「ロシアンルーレットかしら」
あたしはついクスクスと笑いだしてしまう。
今回呼んだ『イチムラくん』はオイルマッサージもうまかったし、キチンと舐めてくれたし、腋の下や足の指までも舐めてくれたし、あげく潮まで吹かせてくれた。サービスは申し分ないけれど、気になったのはお腹の贅肉。キャストである以上身体を醜くしては台無し。いくら清潔感があって顔が整っていたってお腹の贅肉を見たらうんざりしてしまう。その逆もダメ。細マッチョならともかくガリガリでもぎょっとなってしまう。
「今日はありがとう」
あたしはいつもの常套句でイチムラくんと別れた。
イチムラ・カワサキ・ミナミ。
ここのところ毎週と呼んでみたけれど、3人足して割ればあたしの理想になるのになぁ、と、思ってみる。
出会ってすぐみるのは容姿だけれど最後はその人の中身だけれど決して恋に落ちることはないため愛を求めることなんてできっこないのだ。わかっている。
あたしは出張ホストから快楽を求めているのではなく、愛を求めているらしい。イチムラくんにいわれてはっきりとわかった。
正直快楽なんてものは男性から受けなくても自分でちゃちゃと処理できてしまうし下手な愛撫でストレスをつくるなら男性など呼ばないだろう。
「はぁ」
ため息がもれる。愛って一体どこにあるのだろう。快楽はお金を出せば買えるのに。
前々回の『ミナミくん』は、ネットの口コミや他の女性の親密なことまであたしに律儀に話してくれた。え? そんなこと思ってたんだぁ。ってことまで。けれど、やっぱり女の感じるツボを得ていてミナミくんには散々快楽を受けた。快楽は得ても心の快楽は得られない。か。
まあ、そうなのかもしれない。『愛』は売り物ではないのだ。彼らは『快楽』と『癒し』を売っているのだから。だからあたしは指名をしないのだ。『快楽』が『愛』に変わるのが怖いからなのかもしれないから。
『愛』を売る商売があったのならもしも。あたしは買うと思う。
愛に飢えた女はきっとたくさんいるから。あたしのように。
「今日は誰かいるかしら? 新人で入った、サワキくんって予約できるかしら?」
~ホンキでスキに~
最初は興味本意のなにものでもなかった。けれど、ネットの中の彼は至極素敵にみえ、ぜひネットの中でなくほんものに逢いたくてスマホを握った。
電話をするのがとても躊躇われてまずはメールを送った。その後すぐにこっちが戸惑っている隙すらもあたえず電話がかかってきた。
『あの、突然すみません。今、メールくれた方ですよね?』
ご都合がよいときにお電話をくださいという言葉と携帯番号を添えてあった。だからなのか本当にすぐ電話がかかってきたので戸惑うよりもさきその低音ボイスに荒波のごとく引き寄せられた。
『は、はい、えっと、そうです』
『そうですか。こうゆうお店は始めてですか? 好みは? 癒し系? マッチョ系? お笑い系?」
電話の彼は矢継ぎ早に続けるので、あたしの入る余地はなく黙っていたら
『あれ? 聞いてます?』
と、声をひそめられた。
『あ、はい。すみません』つい、癖で謝ってしまった。彼は、ははは、と、笑いつつ、『なに謝ってんねん?』と、くだけた口調で笑われてしまった。
『てゆうか、ほかのキャストさんも見ました。けれど、オーナーのりゅうさんにあいたいんです』
あたしは勇気を振り絞って一息にいった。沈黙になった。ハーッと息を吸う音がしてりゅうさんが話し出した。
『実は、僕はもう現場には出てないんですよ。裏手に回りましたから。って、いうのは本当ですが、別にいいですよ』
僕は少しだけ値段が高いですよ、と、笑いながら付け足す。
構いません。うれしいです。あたしは本当にうれしくてほとんど叫んでいた。りゅうさんはそれから一週間後あたしのアパートに来てくれた。ネットにのせてある写真は宣材写真でプロに撮ってもらったといって、なぁ、実物はそれほどでもないやろ? と、謙遜した態度をとった。あたしは首をかなり横にふって、とんでもない、と、頬を赤く染めた。とんでもないってなんや? りゅうさんはまた笑う。
「そっち面白いなぁ」りゅうさんはいつの間にか関西弁が出ていた。自分では気がついてないようだった。32歳という年齢も魅力的だったしなにせ素晴らしい体躯。顔はたれ目で愛嬌がある。サングラスがよく似合いうっとりと見入ってしまうほどだ。
「ハナっていう名前って本名なん?」
名前について聞かれるとは思っていた。あたしはうなずく。
「たちばなはなこ」
「あ、へー」
でも、花子はあまりにもいやだったので普段でも『華』です、といってるの、と、話した。
「かわいいじゃん」
同じ歳とはいえないままあたしはりゅうさんと裸で抱き合った。りゅうさんの背中には般若の刺青が一面に入っていた。けれどあたしの背中にも竜が渦を巻いている。般若と蛇がにらみ合い絡み合う。りゅうさんはあたしを唖然とさせるほどプロの仕事をした。般若は薄っすらと汗ばんでいた。あたしの背中の蛇は泣いていた。
それ以来りゅうさんを独占したくてとりつかれたように何度も呼んだ。あげく「つきあってほしい」とまでわがままをいって困らせ、泣きついてしまったこともある。りゅうさんはけれどお金はきちんと要求をした。僕はあくまでも仕事で来ているんだよ。そんな姿勢は微塵もくずさなかた。
もどかしくてどうしていいかわからずあたしはいつも渇望をしていた。お金で動くスキな男。だからお金がないとあえない不甲斐なさと寂寥感。会うのにお金がいる関係はあたしの心を徐々に腐らせていった。
きりがない。しがない建設会社の事務員だ。お金など続くわけがない。
あたしは意を決してりゅうさんを忘れることにした。会わなければいい。連絡をしなければいい。それだけだ。
般若の刺青に秘めた思い。りゅうさんに聞いたけれど忘れた。そうやって徐々に彼のぬくもりも消えていけばいい。
~しばられたいの~
こんな裸を誰かに見られたら絶対にひかれるに決まってる……。
『こんな裸』にしているのは妻子持ちのあたしの上司だ。とんでもないサディストで優しい顔からはまるで想像もできないほどあたしを虐める。
キスをするにしたって唇を噛み乳首をおもいきりつねり上げ、セックスの最中は絶対に首を絞めるし、背中を向けたら最後、背中じゅうに歯を立てる。
仕上げは彼の身体を隈なく舐めあげ綺麗にしないとならない。
ぐちゃぐちゃな顔と髪の毛のままで。
『いやぁ、やめてぇ』
抗い嘆き呻く声にあたしも彼も手に負えない。それでも関係は続いている。彼はどエスであたしがどエムだからだ。Sの男性はノーマルなプレイほどつまらないものはないという。スミタさんはあたしがMでなかったらとうに別れているだろう。既婚者の上に上司なのだから。
3日前のおこないのとき背中をたくさん噛まれてまだ歯型が残っているし、ともすればうっすらと血も滲んでいる。傷が癒えたころにあう。そのほどよいスタイルでもう4年。
あたしの身体はもはや普通では物足りなくなった。
『りな』
スミタさんがあたしを呼ぶ。会社のお昼休みに。ちょうど誰もいなかったから呼んだらしい。
『はい』
スミタさんはニタニタと笑いながらあたしの耳元でまるで子どものようにひそひそと小声になってとんでもないことを口にした。いいな、わかったよな。それはもう聞く前から決定されているようだった。否定などできるわけがない。否定をしないとわかっていてスミタさんは予定を組んだのだから。
スミタさんの提案はあたしが縄で縛られているところをみたいしそのまま虐めたい。というその提案だった。え? 誰が縛るの? スミタさん? スミタさんは『いいや』と瞬きをゆっくりとして、一旦言葉を切り、アイコスを灯す。スーッと吸ってハーと吐き出したあとで言葉を続けた。
『出張性感ホストだよ』
え? つい声をあげてしまった。ホスト。ホストって男だよね。スミタさん以外の男があたしの裸を見てどう思うのかしら。いくらホストだからってひくよね。心の中でつぶやく。けれど興味があった。緊縛に。出張ホストに。
「こんばんわ」
ホテルの一室にスミタさんとあたしと『出張ホスト』が顔をあわせた。
えっ? 少しだけ拍子抜け。ホストって顔がいいものだって思っていた。いやいや、スミタさんの顔面偏差値が東大並みに高いので比べてはいけない。
「ハクといいます。よろしく」
まずスミタさんにいい、次にあたしの方を向いて挨拶をする。
「ハクさんって、」
あっ、あたしはそこまでいい口を噤む。
「し、縛れるのよね?」緊縛で呼んだのにアホくさいことを訊いた。ハクさんは、ははは、と大仰に笑い、ええ、専門ですよ、と、付け足す。
へー。そうなんだ。けど、なんだか似合うわ。また心の声。あたしは即座にためらいなく肌をさらした。スミタさんに命令されたから。
「じゃあ、縛っていきますね。まず、腕を前に出してください」
歯型だらけの身体を見てギョッとなった形跡はない。きっと見慣れているのだと思った。カップルで呼ぶお客さんはきっとM女が圧倒的に多いのだろうか。
素早い手つきで縄が身体を滑ってゆく。ああ、身体がぁ、どんどん弛緩していく。拘束をされているのに自由になってゆく。スミタさんの卑下た目つきに余計に粟立つ。ときおり故意なのか乳首に縄があたり、あっ、と、官能の声がもれた。
「写真撮ってもいいかな」
家族に内緒で持っているスマホにあたしの縄姿をおさめていく。「どうだ? 感じるのか?」スミタさんの方が興奮をしているのが伝わってきた。身動きの出来ないあたしをベッドに押し倒し髪の毛を引っ張り背中を噛んだ。今夜はいつもの何十倍興奮をしているようで、挿入をしても呆気なくイってしまた。
ホスト・ハクさんは縛ってからはしばらく傍観者だった。じっとあたしの痴態かたまばたきもしないでみつめていた。ハクくんはどんな気持ちであたしを見ていたのだろう。スミタさんはまた男性の前で裸をさらすことに羞恥心はないようだった。
「ハク、ありがとうな」
時間がきて身支度を整えたあとスミタさんが声をかけた。
「いえ、また呼んでください。先輩」
先輩?
帰りしな軽く遅い夕食をとりながらスミタさんが淡々と話し出す。
「あいつ、俺の高校のときの後輩なんだ。で、相撲部だったの」
「うん。そう思った」ふふふ。あたしは彼の容貌を思い出して笑みが溢れる。
「ハクは本名なんだ。博って書いてハクって読む」
へー。そっちか。あたしはつい横綱の『白鵬』を浮かべた。
「あ、いま、白鵬を思っただろ? りな?」
ははは。スミタさんは声をあらげて笑う。
「いいえ」あたしはうつむき否定をしたけれど、相撲好きだし、きっとばれているし、それでも首を縦にはふらなかった。
「あいつさ、今彼女居ないってさ」
「ふーん、それで?」
~ここからだして~
ー今日は雨じゃないわー
朝なのか昼なのかわからない時間に起きてベッドの横にある熱のこもっているカーテンをあける。ムワンと窓の外にへばりついた熱が顔に直面しあたしはまたカーテンを戻した。
ー雨だったはずよ。今日の天気はー
昨夜は確かに雨がシャワーのように降っていて雨音がいいBGMになり眠剤を飲まないでも眠ることができた。こうも好天だとおもてに出ないといけないのでは罰があたるのではないのだろうか、という感覚におちいる。けれど雨ならばうちにこもっていてもいい、と誰しもが許してくれているようで雨の日が好きなのかもしれない。
ひきこもりになって3ヶ月がたつ。必死で働いてきたのに車内での陰湿なイジメにあい精神を病んで辞めざるおえなくなった。会社側からのリストラ扱いにしてくれて給与の面ではしばらくは安心だけれどその代償はひどく大きい。おもてに出るのがこわい、人の視線がこわい、世界の色が全て灰色に染まって見える。
「冗談じゃないわ」
あたしは誰にでもなくつぶやく。独り言が多くなった。もうまる一週間深夜にいくコンビニ店員ぐらいしかろくに口をきいてない。喋らないので自分の声を忘れかけている。笑わないのでシワは増えないのでいいのかもしれない。孤独。孤独はちっとも退屈ではない。むしろ孤独こそが人生かもしれない。と、思う。
それでも誰かと他愛ない話をしたいときは『レンタル彼氏』に頼ることにしている。お金で彼氏を買う。たまたま見ていた動画で知った。本当に実在することにほとんどおどろいた。気が向いらときに呼んでいる。汚い部屋の中に。ベッドが主役のような雑多な部屋に。
「まったぁ、こんなに散らかして〜」
久しぶりに部屋に来た『ハルキ』がぶつぶついいながらテーブルにあるコンビニ弁当の空だの空き缶だのを仕分けしつつ文句をたれる。
「ほっといてよ。あなたはあたしの喋り相手として呼んでるの。余分なことはしないで」
短パンとTシャツ姿のあたしはあまりにも子どもじみている。伸ばしっぱなしの髪の毛は腰までありあまりにも痩せていて頼りなさずぎる。腕なんて鶏ガラのようだ。あらから片したハルキがあたしの横に座る。いつもの香水の匂いと違う。彼女が変わったんだ。直感だけれどそう思う。人間は匂いを真っ先におぼえる。生理的に受け付けない匂いがある。その逆で好きななつかしい匂いもある。ハルキからは最初からなつかしい匂いがした。香水じゃない香水の裏の匂い。
ハルキがあたしを抱え込むように抱きしめる。線は細いのにきちんとした男なんだと知る瞬間。だけど他の女も同じよう抱きしめているだろうと思うしてはいけない嫉妬心。そのはざまであたしはハルキから愛撫をうける。
「あっ、あああ、」
そのときにやっと自分の声を意識する。あたしってこんな声だったんだ。あるいは、こんなにいやらしい声を出せるんだ。と。今夜のハルキは執拗にせめたてた。容赦なくあたしの身体を愛撫した。生きているんだと知らしめるかのように。
「ねぇ」
冷蔵庫からミネラルウォーターを2本取りだし1本をハルキに渡す。サンキュー、という仕草をしそれを受け取る。冷たい水が渇いた喉を潤してゆく。
「早く梅雨にならないかな」
「え?」
またカーテンをそうっと開ける。もうすっかり夕方から夜になりかけている。遠くのビルやマンションが逆光で黒くなっていていまにも切り取れそうだ。
ハルキは黙っている。いつも黙ってあたしの話に耳を傾ける。明日雨なら職安に行ってみよう。けれどそのことはハルキにはいわないでおこう。かわりに
「梅雨になるとね、かわいい長靴が履けるのよ」
「あー、そうだね」
~ウランくん~
ガーッ、
はっ、今あたしは確かにいびきをかいてた。やだぁ、と思いながらゆっくりとまぶたを開く。隣にいる人の方に身体を向けるとその人も『ガー、ガー』と、まるで子どもじみた顔をしておじさんのようないびきをかいていた。
どうやら眠ってしまったようだ。まんねん不眠のあたしなのに『ウラン』くんといるときだけ睡眠薬でも飲まされたかのよう必ず眠ってしまう。ラブホテルは窓がないし時計もない。ベッドの上にあるちいさなヘッドライトだけがぼんやりと灯っている。午後の1時にホテルに入ったことだけは確かだ。最初の1時間はきちんと『おしおき』をしてくれる。性感ホストのウランくんのプロフィールに『ドS』と明記されていたのと『だけど小心者』と、Sなのに小心者だという点に興味と好奇心がいっしょくたになって呼ぶようになってからもう半年になる。月に2度。なので12回あっている。8回目あたりからさんざんいたぶっていただいたあと恒例のよう眠たくなりひととき眠るのが習慣になってしまった。
なんて心地のいい眠りなのだろう。自分でも驚いた。今でも驚いている。不思議な存在のウランくんは髪の毛をピンクに染めている。たぶん20代半ばだろう。年齢など興味もなく聞いていない。ウランくんも聞かない。わかっているのはあたしの子どもでもおかしくない歳の差だということだけだ。
初見でのSMプレイでは腹が立った。
『このど変態が』とか『もっといじめてほしいのか』とか『叩いてほしいのか』とか。確かにSMプレイを懇願したのはあたしだったけれど初見で見知らぬ年下の男になにをされても腹が立った。あれ? あたしMじゃなかったんだ。と、そこで知った。生粋のMならいじめられることに快感を得るはずだ。けれど違った。得たのは憎悪と諦観だけ。
(愛してるからSMは成立するんだ)
そのときほど痛感したことはない。好きでもない男にいじめられてもいらつくしその男を蹴ってしまいたくなる。
Mの女は基本的に構ってほしいかまってちゃんでひどくさみしがりやで孤独をもっとも嫌悪するのだ。あたしもその一員だ。
「あっれ〜、寝ちゃったわ」
天井を見つめながらぼんやりと考え事をしていた隣からハスキーな声が聞こえる。
「ゆりさんも寝てたでしょ?」
ウランくんは頭を手で支えながら重ねて続ける。
「寝てた」
だろ? 俺らってすぐ寝るよなぁ。ははは。
ゆかいそうな声が心地よかった。そうね。あたしも、ははは、と笑う。
「今日ゆりさんの苦悶の顔よかったよ」
ん? あたしは首をよこにふって、まぶたをとじる。ゆっくりと呼吸するように。
「だって、」
だって。なあに? ウランくんの心の声がする。だって好きになってしまったんだもの。あなたを。
「だってね、あたしMよ」
「わかってるよ。ゆりさんは素直で乙女チックなMってことはさ」
そうね、あたしはみじかくこたえる。そうして、今何時かな? とたずねる。ウランくんはベッドの上にあるスマホのロックを解除し時間を確認する。スマホの灯りが顔をあかるくうつしだす。シワもシミもヒゲもない清潔な白い肌。
「もう6時みたい」
「そう」
現実味のない個室はひんやりと冷たい空気が流れている。このまま時間が止まればいい。
「腹減ったなぁ」
ウランくんがタバコを咥えながらテーブルに移動する。
「泊まってこっか」
あたしは自由なのだ。ウランくんを引き止めても自由なのだ。
「うん。嬉しい!」
~マネー&ラブ~
「もっと、お化粧を派手にしてみてもいいと思うんだよね。ついでに服装も地味だしね」
思うのではなくてそうしてほしいんだけれど。わかる? と、遠巻きにいわれているのだとわかる口調にあたしはうなずくしかない。薄化粧な顔を下に向け、全身真っ黒な服装を身にまとって。
今回は思い切って『外でのデートプラン』を提案してみたのだ。相手は彼氏は彼氏でも『レンタル』の彼氏。返却は今日の午前0時。当日返却なわりにいやに高額なのはテレビ画面で見るのではなく現実にいて話をしあるいは手をつなぎキスができるのだ。あこがれの『レンくん』と。
最近は顕著に『女性向け風俗店』が増えていてネットの閲覧だけでもかなり迷うし、え? もうこんな時間なの? みたいなことも多々ある。それに。あたしは最近の『女性向け風俗店』について感じることがある。
顔が整いすぎている人が多いのだ。こういうサービスを知ったのは約10年以上も前だったけれど過去に比べたら男性の質が高いふうに思う。それに女性向け風俗店に従事する男性は皆一様にエスコートもうまいし洗練されている。レンくんもその一員だけれど、ひとつだけ他の『レンタル』と違いがある。
「レンくん、こんな幸薄な顔をしたあたしと歩くのいやだよね」
あたしならいやだから少しだけ半笑いで聞いてみる。だったらもっとオシャレしてこればいいのだけれど。
「そうだね」
彼は容赦ない。素直に思うままに認める。
「そうだよね」
夕方の5時でも初夏のこの時期はまだ明るい。昼間の明るさよりも控えめだけれど。
「けど、」レンくんは、けど、と、前置きをし、目の前にあった石を蹴る。石はポンと飛んで道路の端に転がった。
「勘違いしてほしくないんだよ。確かに僕はお節介だしいやに辛辣だし女性に、いや、お客さんに対してもね、アドバイスをしていつまでも綺麗でいてほしいんだよ」
うん、そうなんだ。彼は自分でいったことなのにまるで自分に言い聞かせているふうに見えた。
「そうね。そんなこといってくれるのレンくん以外いないわ。普通いわないでしょ? だってあたし一応お客さんなんだしね」
あたしも目の前にある小石を蹴る。そしてづつける。
「あいたいけどねお金もいるしおんなってとてもお金がかかるわ。だから働くしかない。けれど今の原動力はレンくんなんだ。もっとがんばって働いて自分を磨くわ」
「おおっ、いいこというじゃん。ユナちゃん」
ラブあんどマネーね。
あたしは心の中でつぶやく。好きだから綺麗になる。だからがんばれる。世の中ってうまくできているなぁ〜。35歳のあたしはほとほと感心する。
「居酒屋行きたいな」
だんだんと空の色が群青色に染まりつつある。やべー、腹の虫が鳴った。レンくんはそういいながら、お腹を抑える。
「あはは。あたしもお腹すいた。そのあと映画いかない?」
「どこにでも行くよ。0時まではユナちゃんのものだから」
~おどろかないで~
もう何年も自分の体を鏡で見たことがない。家中にある鏡という鏡は全部捨てた。幸いにも勤務先は洋菓子をつくる工場で皆一様に白い帽子を被りマスクをし宇宙服のようなもので身を包んでいるため晒されているのは目だけであって他はない。あまり人に関わらず淡々とこなせる仕事があったことに何年も働いているのに至極ありがたいと思う。
時は残酷にいや、平等に流れていく。そうして年をとっていく。あたしはいつの間にか40歳の大台にのっている。いささか信じられない。ほとんど社会との関わりを絶ってきたのだから。
あたしの身体には生まれつき無数の大きな『イボ』あるいは『おでき』がある。その大きさは様々でぶどうくらいの大きさのものや干しぶどうくらいの大きさのものまで数えたらきりがないほど身体中に散らばっている。頭皮にまで出来ているのだからもはや施しようがない。レーザーで焼くにしても何年もかかる上お金だってかかる。生まれつき。幼い頃からあるにはあったけれど年齢を重ねることに増えていき大きく育っている。
その中の『イボ』がポロッと取れて血が止まらなく病院にいくと、あれ? そんな突然取れることなどないよね、と、不思議そうな声でいいよどみ、一応病理検査にだしますね、と、付け足した。そうですか、それ以上はなにも訊かなかった。いろいろとどうでも良くなってしまっていた。なので最後だと思って、男性をお金で買うことにした。お金はたくさん持っている。『イボ』の治療費にはほど遠いけれど。お金で男性が買える時代。あたしは別に勇気なども出さないで軽く電話をし男性をホテルに呼んだ。ドキドキするかと思ったけれどそれも杞憂でまったくドキドキしなかった。男性に肌を見せたことはない。なのでもちろん誰とも付き合ったこともないしキスもない。
もしこのまま死んでしまうのなら、そう思うとなにもかもが嘘の世界に思えたし嘘で固まった自分でいられると感じたしもし、あたしの裸を見て来た男性が眉根をひそめてもいいとさえ思っていた。
こわいものがもうなかった。
「お待たせしました」
待ち合わせ場所のホテルの部屋で待っていたら時間どおりに男性は来た。
「いえいえ。待ってませんよ」本当に待ってなかったのでそうこたえた。
「あ、すみません」男性はぺこりんと頭をさげ、「なおき」です。と挨拶をした。ゆみです。お願いします。あたしもぺこりんと頭を垂れる。
「あのぅ、」ちょうど夜が始まる時間たいだった。窓からの景色にまだ薄明るさが残っている。
「はい」
なおきさんが返事をかえす。すみわたるような低音質の声。あたしは薄明かりの中ゆっくりとブラウスのボタンに手をかける。なおきさんは立っていたけれど、なにもいわないでベッドの縁に腰掛けた。
「か、身体に出来物がおそろしいほど出来ていて、」声はなんとなく震えている。なおきさんは、はい、と、また返事をする。
「今まで男性に触れたこともなければ、触れられたこともありません。今夜は最初で最後と思い、呼びました。あ、出来物は人にはうつりませんので」
うつむきがちだったので目の前になおきさんがいることにまるで気がつかなかった。あっ、おどろいて声を上げる。
ブラジャーとショーツになったところだった。薄明るくても身体にある異物は消えるわけではない。なおきさんは、最初、ギョッとなったけれどすぐ今までの顔になって、脱いだブラウスを拾い上げあたしに被せた。そうしてそのままぎゅっと抱きしめた。知らない匂いがして心臓の音がして人の体温の高さにおどろいて温もりが胸を締め付けた。
「無理をしなくてもいいです」
背中をさするなおきさんの手が「大丈夫」「大丈夫」と訴えているようだった。あたしはまたたくまに子どもに戻ったように獣のような雄叫びでおいおいと泣いた。こんなに泣いたのは初めてだった。
「誰にでも悩みはあります。それを隠しながら生きていくのも辛いし見せるのも辛い。どうしていいのかわからない。そんなときは誰かと喋ることです」
うまく呼吸の出来ない中でなおきさんの声がする。
いつかは死にいつかは生まれ変わる。
「あ、ありがとう、」
きっと聞こえてないだろう声でそっと囁く。あたしはまだ生きている。なおきさんがそっと教えてくれた。ありがとう、あたしはまたお礼を心の中でつぶやく。
~うさばらし~
「どうしてオトコってさ、手に入れた途端徐々にめんどくさくなるかしら?」
午後の3時。梅雨の合間であろう今日は空がバカバカしいほど澄んだ青をしている。まるで絵の具の空色だ。あまりにも空が綺麗なのでカーテンを閉めていない。
「ええーーー! それ、俺に聞くんですかぁ? 意地悪っすよ」
お手上げのポーズをとって彼は口を尖らせる。だって、あたしは次の言葉を舌先にのせて、続ける。
「だって、最初はね、こっちに夢中なのにこっちが夢中になるのがわかると距離を取ってくるわ。ましてやあっちが既婚者の場合はね」
ふーむ。彼は真剣な面持ちで何か気の利いたことをいおうと考えている。ふふふ。つい含み笑いをしてしまう。
「真剣なのね」
あたしはクスクスと笑う。けれど、もういいの。と、付け足して。やや時間を置いて彼が切り出す。
「でもさ、全てのオトコがそうではない。不倫をしているオンナの戯事に聞こえます」
あ、いいすぎた。そんな顔をし彼はうつむく。すみません。いいすぎました。と蚊の鳴くような声を出して。
「忘れさせてよ」
あたしは本能のまま火照った身体を持て余していた。今夜は誰でもいいからオトコと過ごしたかった。お金を介してもいい。なのでオトコを買うことにした。オトコを買うとかいうと嫌な言い方だけれど、オトコの時間を買っているので買っているには違いない。彼は、ええ、もちろんです。と、きっぱりとオトコらしくいい切り、あたしの頬を持ち上げてキスをした。ディープキス。ベチャベチャになりながら唾を絡ませ合う。まだ出会って数時間しか経ってない。なのに素性を知らないからだろうか? あたしの陰部がこれでもかというくらい子宮がキュンキュンと鳴ってそのいちいちがうるさかった。
彼は何もかもが素直で素敵だった。さすがプロ。そう思わせることも平気でやってのける。今まで経験したこともない『潮』をクジラのよう何度も吹かされてしまい、脱水になりそうになった。潮など一生吹かないと思っていた。なんともいえない爽快感。逝く感覚とはまた違う気持ちよさ。
「すごい。あたし初めてだ。潮吹くんだ。あたしでも」
声が呆気に取られいた。まるで自分のことではないみたいなことのように。
ははは、彼は屈託なく笑い、『忘れられましたか?』と、質問をしてくる。
「いっときね。忘れたわ」
本当だった。快楽を得ている時、不倫のオトコのことをすっかり忘れていた。忘却だ。
「オトコを忘れるためにね、俺を呼ぶ人結構います。いいんです。オトコを忘れるにはオトコ。そうなんです」
ゆったりした口調にあたしはうなずく。目頭が熱かった。気を許したら涙が垂れそうだった。
「ありがとうね、修さん」
彼は、いいえ、と短く返事を返す。
修さんを呼んだ理由は不倫相手の名前が『修一』だったからだ。どうでもいいことだけれどどこかあたしの中でやっと吹っ切れた気がしてならない。
「僕は週末しか出てません。昼間は現場仕事で」
へー。不倫相手のオトコは現場監督だった。偶然? あたしはまたクスクスと笑う。
ん? そんな顔であたしを見つめる修さんはよく見れば彼に似てるような気がしてならない。
まさか。まさかね。
~きままもいいけど~
「いつきても、いい眺めですね〜」
今日は有給をとって午後から5時間。成瀬くんを自宅に呼んでいる。
「いいなぁ〜。だってさ、『家』を持っているなんてキャリアウーマンって感じだし」
気に入りの窓際にいる成瀬くんが、さもたのしそうに付け足す。
キャリアウーマンってそんな大層なものじゃないわ。あたしはクスクス笑い、成瀬くんの背中に腕を回した。あたしよりもひとまわりも違う、彼の背中からは優しい家庭の柔軟剤の匂いがする。実家住まいなのだろうか。それとも独り暮らし? まさか、結婚してる? 彼は出張ホストなのでほんとうの名前も知らないし年齢だって偽っているかもしれない。ただ。ただ、と素直になってみる。ただあたしは寂しいのだ。
雑誌の編集長(小さなデザイン会社)になり部下も出来人脈も広がり仕事もバリバリこなしているうちに40歳になってしまった。2年前にこのマンションを購入したとき悩んだのはよくマンションを買うと結婚が遠のく。とか昔からいわれていることで事実両親に至極反対をされた。けれど昔から『きかんぼう』気質だったので親はやれやれ顔で今ではもう何もいって来ない。たとえば『付き合っている人のひとりでもいるのか』とか『早く孫の顔が見たい』だとか。
付き合っている人はたくさんいるわ。と、こたえたら父親は目をまるくして、いやいやそういうんじゃなくて。と、口ごもったとき思わず親不孝でごめんなさい。と、心の中で謝ってしまった。
「どうして誰しもあたしのことを気ままでいいね。って決めつけるのかしら」
窓の外はすでに夕方の色から夜の色に変わろうと準備をしだす。成瀬くんの背中は華奢に見えるけれど実際男の身体。きちんと並んだまっすぐな背骨を持った大人の男。
「決めつける?」
彼は振り向き同じことをくり返す。
「そう。決めつけてるわ。世の中は」
「んー。そうかもですね〜。けど、そんなこといえば皆結婚に囚われなくてはならなくなってしまう。そうしたら僕達の仕事だがなくなってしまうし、世の中ががんじがらめになってしまう」
がんじがらめ。あたしはおどろいたしがんじがらめ。なんて言葉を久しぶりに聞いて(この若い男から)ふふふ、と笑みがこぼれた。
「そうね。自由でも、きままでも、自分次第だわ。そうでしょ?」
成瀬くんはあたしの方にむきなおり、白い麻のワンピースをたくし上げ、わりと豊満は胸のあわいに顔をうずめ指はいたずらにあたしのショーツのクロッチをなぞる。
「あ、ヤダァ」
ちっとも嫌ではないのにあたしは嬉しいとき『ヤダァ』と真逆なことをいってしまう。指は執拗にせわしなく蠢きクロッチはあっという間にぐっしょりと濡れそぼる。あわいから乳首に移動し乳首は温かな口内もてあそばれ、いやらしい声がいちいち出てしまい、ベッドにそのまま押し倒された。
窓。窓が開けっ放しだ。閉めないと。声が。聞こえてしまう。
頭ではわかっているけれどあたしは寝そべりながら窓の外に目をやる。夕方の橙色と群青色の中でカラスがサーっと横切っていった。
あら、あれ、あたしだ。きままできかんぼうで羽があってそうして真っ黒だから。
ククク。あたしはまた笑う。
~おんなどうし~
別にレズだとか性同一性障害とかでもない。と自覚はしている。けれどたまたま好きになった『人間』がたまたま『女』であり妖怪でもお化けでもないだけだ。性別を通り越した恋愛形態にまだ世間がおいついていないだけ。少なかなずあたしと彼女はそう思っている。
彼女とのセックスが果てがない。あるいはきりがない。女同士ツボを知り得ているし痛くしないやり方でお互いに快楽という名の形の見えないものをさんざんと与えつづけられる。ねことたち。そんな言葉があるけれどあたしたちにはそれがない。
「はー。わかんねーなぁ、でもなぁ、なくもないかな〜、でもね〜」
昼から仕事が半休になったので駅前のスタバにハヤトと来ている。ハヤトはいわゆる『代行彼氏』であってほんものの彼氏ではない。なんでも相談に乗ります。僕の趣味は占いです(なんちって)とお店のプロフに書いてあったのを気に入ってどちらかといえばバイなので月に2度ほどハヤトを呼んでいる。線の細い男の子だ。指など白魚のように細い。
新作が出たというなんとかなんとかという飲み物はあたしにはかなり甘ったるかった。ハヤトはズズズとあっけらかんに飲み干す。
「すごい吸引力だね。ダイソンも顔負けだよ」
「えーー! 俺ダイソンになった訳? たとえがウケるー」
ゲラゲラとハヤトが笑う。あたしもついつられ笑いをしてしまう。さてと、いこうか。すっかり飲み終えた飲み物をゴミ箱に捨ててハヤトはあたしの手をとってどぎつい日差しのおもてに出る。あっちー、これさ、きっと車のボンネットで目玉焼き焼けるよね、とつけたして。確かにそうだ。あたしもそう思ったから笑ってうなずく。彼女とは全く違う部類の大きな手はあらためて新鮮さを持ってくる。
「今日もローターとバイヴでいいんだよね?」
「うん。本物は要らないわ」
てゆうか本物は使用禁止です。あっそっか。うん。そう、だって俺冗談抜きで勃たないんだよね、と涼しい顔をしいう。まあ、女慣れし過ぎたのかもね。あ、変なこといっちゃったよ。と、顔をしかめる。
「いいよ。だってハヤトはそうゆうエロさをむき出しにしてないからあたしは呼んでるのね。彼女との関係はそれはそれは良好よ。けどね、時折忘れそうになるの。男の身体と男のため息を、だから___ 」
もういいよ。とでもいいたげな感じで、もうわかったからいいよ。と、話を遮る。
「人間だもん。男も女もないよ。その人を好きになった。なったのが同じ女だっただけ」
だろ? ハヤトはあたしの目をみつめた。
バイヴで散々と弄んでもらい彼女の前では披露したこともない動物めいた声をだしあたしは何回もイッた。身体は本能のままで動物じみているけれどやっぱり心は繊細で彼女でしかイケないという事実を突きつけられる。けれどそれによって彼女を愛しているんだなと確認が出来る。
「あのね、彼女といつも一緒にお風呂にはいるのね、でね、おっぱいをすり合わせて身体を洗いっこするんだよ」
「うんうん。とてもいい絵面だ。うん」
ホテルから出るとまだすっかりあかるかった。特に今時期は日が長すぎるほど長い。そして昼間のこもった熱気が否応無しにおりてくる。
「また気が向いたら呼んで」
「ええ」
なんて都合がいいんだろう。恋愛感情ではなくただ人間としてハヤトが好きだ。
「ハヤト、好き。今日は暑いのに急にありがとう」
~フウフ・エンまん~
「えーー! うっそー!」
いやいや、声が大きいってば。あたしは目の前の女友達に向かって口元に人指し指を持っていき、もういっかいシーっといいながら制した。
「だってよ。だってねーーー、」
女友達はだってだってを2度繰り返したのち、頼んだカルボナーラスパゲティをフォークに巻きつけながら喋りだした。
『結婚して21年も経つのに、まだセックスしてるなんて。信じられないって。あなた達夫婦はある意味、神だわ』とか
『うちなんかさ、もう寝室だって別だし、だからね、もうそうゆうの、ん〜、え? あれ、どれくらいしてないだっけ。ってほど遠い昔のことで忘れたわ』とか、まるでしてない方が普通のような勢いでまくしたてた。
「けど、まあいろいろな夫婦がいるからね〜」
散々おどろき散々喋ったあとで結局こう締めくくった。
真昼間のちょっと洒落た洋風のお店で高校時代の女友達とランチをしていて下ネタの話になったのだ。
まわりを見渡すと店内は皆女だった。料理人は男性で他は皆女。年齢はまちまちでそれでもお喋りはどの女もたのいんでいるし笑い声がたえない。
しかし。と、考える。しかし、この中にいる女性の何割が定期的にセックスをしてるのだろうと。人間の根本となる『性生活』はなぜだか皆あえて口にしない。隠れた秘密。自分自身にしかわからない秘密の情事。
21年もいる男性 (すっかりお腹も出ていて頭の毛もさみしい)とのセックスのどこがいけないのだろう。あたしは窓の外に目を向け梅雨独特の雲のたれこめたグレーの空を見上げる。
ーーーーーーーー
あたしって貪欲なのかな。語尾と頭をあげてユウマくんに問いかける。ユウマくんは出張性感ホストだ。
「どんよく」
ユウマくんはどんよくというのを貪欲と知るに約3分くらいかかった。こういうところがかわいくて気に入っている。32歳の大きくなりすぎてしまった子どものような彼。
「そう、貪欲よ」
たった今まで散々愛撫をされ潮を吹かされシーツがお漏らしをした状態になっているのでソファーに裸で移動していた。華奢だけれど筋肉はしっかりとついている。筋肉に埋まっていた頭をあげた。
「貪欲ねー」
女性は皆貪欲です。リサさんだけではありませんよ。ユウマくんはあたしの頭を撫ぜながらまっすぐした口調でそういった。
「貪欲な人ほど優しいし素直だし内面からも表面からもエロスが滲みでてます」
ふっ、あたしはつい鼻で笑ってしまう。エロス? そうかしら。
「旦那と毎日でもしたいのよ。旦那と21年も一緒にいるのに。で、それって変って指摘されたんだ。友達にね」
たばこに火をつける。最初の一口がうまいのはタバコとビールだと思う。ユウマくんもタバコに火をつけた。煙が細くゆるゆる心もとなく立ち上ってゆく。
「ユウマくんに会った日はね、絶対に旦那とするの。ユウマくんがなにかのスパイスになったみたいに」
そうつづけた。
ユウマくんは首をよこにふってから落ち着き払った声音で
「スパイス。おもしろいですね。あはは。てゆうかセックスは自然の原理ですし、旦那さんとの行為はむしろあって当然だ」と言いきって、あ、わかった風な口ぶりすみません、と、謝った。
いえいえ、という感じであたしはうなずく。ユウマくんはほんとうにかわいいしあたしの中でのスパイスでもありオアシスでもあるみたいだ。週に1度。たった2時間だけれどこの時間があたしにとっての貪欲の根源かもしれない。
「今度友達にユウマくんを紹介してみようかしら」
えっ? なにかいいました?
女友達もほんとうはもっと貪欲になりたいはずだわ。だって死ぬまで女なんだもの。
「いいですよ」
「え? 聞こえてた?」
~それは・あるひとつぜんに~
喉の違和感に気が付いたのは昼食のお弁当の中に入っている切り干し大根を飲み込むことがなかなか出来ないことだった。飲み込むため何度もお茶を飲んだ。試しにご飯を食べてみたらそのようなことがなかったのでそのときは気にもしていなかったけれど、今度は耳の裏側に熱を持っていることを自覚し触ってみると小さなシコリを発見した。直径1センチくらいだろうシコリはどうやらあたしの体内の中で暴れているらしい。
勤続30年になるあたしは50歳で独身であげく処女だ。会社に命捧げちゃったなぁ、山田ちゃんは。と営業の男性たちにいわれる。嫌味でも非難でもない世間話。ふと、後ろを振り返ってみる。振り返ったところで誰もいないことにいまさらながら愕然となる。
『甲状腺のガンです』
そう診断されても待っている人もいないあたしはもう愕然を通り越してぼんやりと空虚を貪るだけだったしああ、そうなのか、やっぱりなとどこか諦めていたふしがある。
検査をした結果手術は絶対なので2週間後の手術まで一旦会社は有給で休みにした。猫ときままな2人ぐらし。あたしは暇を持て余していた。さみしいわけではなかったけれどネットをいじっていたら『レンタル彼氏』というサイトにたどり着いた。
顔出ししている人もいたら横顔だけの人もいたりしてネット観覧だけでも十分に楽しんだ。けど。と、考えてみる。あたしだって女だし。もしかして万が一だってあるかもしれない。いつもの控えめな性格が急に傲慢な女の性格に変わる。あたしは初心者を悟られないようレンタル彼氏にコンタクトをとった。
「はじめまして」
顔出しをしている『ルイくん』を選んだ。自宅でも可能ということで自宅に来てもらっている。
「こちらこそ」小汚いですけど座ってくださいと促しルイくんをテーブルの前に座らせた。わ、実物の方がかっこいいな、ルイくんの顔はプリンスメロンの小玉のようにちいさく線の細い体躯。30歳という年齢はそうともいえるけれど全くわかならい。
「山田さ、あ、いや、ようこさんって呼んでもいいですか?」
「あ、ええ、構わないわ。じゃあルイくんはルイくんで」
ようこさんなどと名前で呼ばれるのなんて何年ぶりだろうとつい心の中で指を折る。その前に男性がうちに来るなんて。もしかして初めてではないだろうか? と、脳内の記憶装置をフル活用し検索をかけるけれどまるで残っていなかった。
「さーて。さーて。今夜は僕になにをして欲しいですか? なんでもしますよ」あ、でも鼻からソーメンは無理ですよ。とルイくんはいいながらクスクスと笑う。そんなこといわないわよもう、あたしもいいながら同じように笑った。猫のたまも一緒になって、ナァー、ナァーと鳴いている。
会社の男性以外と喋ったのも何年かぶりだし何もかもが新鮮で異空間にいる感覚になり自分の部屋なのに他人の部屋のように思えてくる。
ルイくんへの要望は裸のまま抱きしめてもらうことにした。処女だとかガンだとか。もうそんなことはその瑣末なときだけ忘れていた。ルイくんは柑橘系の香りがした。こんな仕事もあるんだなぁ。ルイくんの横顔を見ながら思う。大変な仕事だなぁと。好きでもない女と添い寝をする。まあどのような仕事も楽ではない。わかっている。ルイくんは躊躇なくあたしの頬にキスをした。首筋を触る。ルイくんはわかったかな。リンパ腺が腫れていること。朝になったら腫れが治まっていればいいのに。そんなことを考える余裕などルイくんと並んで眠るまで思いもしなかった。
ー生きたいー
手術は成功して1週間の療養の末職場に復帰した。
「わ、山田さんだ。大丈夫ですか?」
制作の八栗さんがふんわりとした茶髪をなびかせぽんと肩を叩いた。
「ええ、ご心配おかけしました」
あっれー? なんだか山田さん綺麗になった気がするぅ〜。へー。とかなんとかいいながら八栗さんは通り過ぎていった。
あたしは退院してしばらくしてからまたルイくんを呼んだ。これといって進歩はないけれど勇気と希望をたくさんくれるルイくんに今とても感謝している。
~ジェラシー~
うそっ? えっ!
パソコンの中で見たこともない上品なスーツを身にまとい、富士額だからおでこを出す髪型はどうもね。と、いっているはずなのに思い切りおでこ全開にしオールバックにした髪の毛はワックスで綺麗に固められている。カツラなの? と突っ込みたくなるような完璧な髪型。顔の写真と全身の写真が2枚づつ。ちょっとだけ濡れたような目と唇は意図的なのだろう。
それにしても。あたしは画面にうつる『性感ホスト・夕(ユウ)』を食い入るように見つめる。こんなに本人の顔を見つめるのはいつ振りだろうと心の中で指を折る。
ユウはしかしうっとりするほどな笑みを向けあたしに笑いかける。ユウなんだ、あなたそうして笑えるんだね。と、感心半分まだ驚き半分だ。
「いってきます」
今朝いつものように優は仕事に出かけた。無精髭をこしらえて水筒とあたしの作ったおにぎりを2つ持って。優の仕事は『とび』で「とんびじゃねーよ。鳶」と出会ったころ何も知らないあたしに教えてくれた。同棲して半年。付き合って1年。あたしは今まで優のこと(全体的に)をうたぐったことなど一度もないしあるいは仕事場になど出向いたこともない。
きちんと7時に帰ってくるのだ。おもての空気と汗くささと汚れた作業着を着て。おにぎりもっと大きくして。足りねーよ。といって。
どうやら優は『性感ホスト』の『夕』らしい。そういえば。と出会った頃を思い出してみる。あたしは優のなにに一番引かれたといえばしかし『顔』だった。『性格』とか『趣味はあう』とか。そんなのってその場でのとりつくろう常套句であって最初は絶対に『顔』なのだ。そういうあたしもこういっては女友達に叱咤されそうだけれど顔とスタイルだけはいい。顔がいい人生と悪い人生ならいい方に決まっている。ブスは死ね。ブスは実際性格が良くない。女友達の中にもそれに属している子がいるけれど、ブスなので引きたて役になるのかいやに友達が多いのにおどろく。そのブスの主催の飲み会で出会ったのが『優』だった。
優は果たして『夕』となりブスでもデブでも相手にしているのだろうか。ふっ、つい鼻白んでしまう。てゆうかそんなことはどうでもいい。『優』はもう『夕』に決定されたのだ。
脇が甘いぞ。優。写メ日記を遡ってみるとどうみてもこのアパートの全身うつる鏡の中でTシャツ姿の写メを鏡越しに撮り『さてー。今日はおやすみ〜はーと。料理でもしようかなぁ〜って。こうみえて僕は料理男子で〜す!明日は出勤するのでご予約お願いしまっす!』嘘つけ。あたしはつい声を出す。料理の、り、の字も書けないじゃないのかってほどなにも出来ない優。栄養士のあたしだからこそ彼の身体を維持しているのだよ。優くん。といってやりたい。
多少の嫉妬と多少の怒りと多少の諦観。けれど、優を責めるつもりなどさらさらない。だっていつもあたしの所に必ず帰ってきてくれるのだし。おもての世界に出てお金を稼ぐことは『鳶』でも『ホスト』でもなんら相違ない。きっと出会ったころからホストだったのだろう。
「ねぇ、松坂桃李くんの映画、えっと、娼年だっけ? 観に行こーよ」まさか優がその世界にいるなんて思っていなかったので微笑んで誘ったら、いや俺はいいや、とあっさり却下された。
あーあー。今思うと納得をしてしまう。そうしてクスクスと笑いがこみ上げる。
身体と時間は売っている。けれど心までは売れない。どこかのホストがTwitteでつぶやいていた。
まあ、そうね。