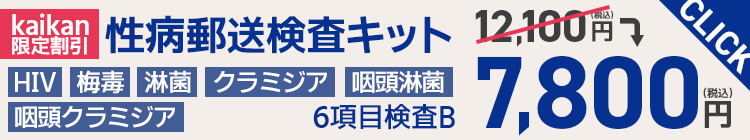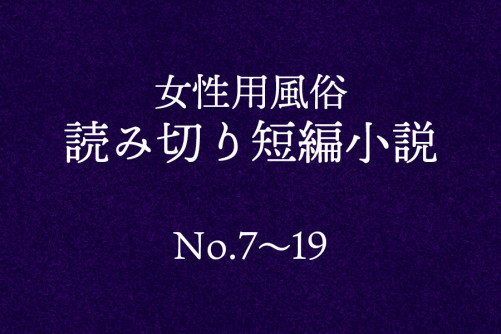
【女風小説】7話~19話|1話数分の読み切り短編サイズ
1.
〜みてみられて〜
2.
~ゆれてゆられて~
3.
~まゆこのこい~
4.
~ねぇ、すって~
5.
~やさしくしないで~
6.
~おいしそうね~
7.
~あたたかいくちびる~
8.
~すきなのに~
9.
~いちゃいちゃだけ…~
10.
~しめくくり~
11.
~ほんきになっても~
12.
~すみません~
13.
~ここが、いいの~
〜みてみられて〜
いまどきの主婦はほどんどの人が働いている。専業主婦とゆう肩書きを口にすると逆に、えー、働いてないの? などといわれる時代だ。
昔は専業主婦になるのが夢だったし幼稚園の頃小学校の頃の夢はずっとぶれることなく『およめさん』だった。
幼い頃の『およめさん』という人種は純白のウエディングドレスを着たいがためのイメージでしかなかった。いやらしい感情などは微塵たりともなく純粋にウエディングドレスが着たい、という一点に絞られた。
しかし、大学生になったころは幼い頃のような無垢で純粋な心情などはすっかりと忘れ、『およめさん』になるにはウエディングドレスを着るだけではダメでそれよりも大事なことがあることを知った。
もちろん、愛している男性と結婚をするのがいいに決まっているが、あたしはなにせ、専業主婦に憧れを抱いていたので積極的に合コンに参加をし、これっだよ、これ。という男性と巡り合った。
コンドームに穴をあけセックスをしたら妊娠をしあっけなく結婚をした。付き合ってから一年。22歳のときだ。大学は一旦休学をし子どもが2歳になったタイミングでまた復学をした。
ある種、専業主婦だし、学生だし、それはそれはまだ生ぬるいお湯に浸かっているようで毎日が幸せだった。あまりおもての世界に出てわーわーするたちではないので優しくておカネもあってまーまー顔も良くて記念日などにプレゼントを買ってくれる旦那さんにひどく感謝をしていた。
「ユリはね、学校に行ってさくらの面倒をみていればいいんだよ」
旦那さんはあたしをひどく子ども扱いした。25歳になろうとしているあたしを学生だからといって子ども扱いをする旦那さん。
「うん。そうね。わかってる、ねえ、ねえ、さくらね、今日ね、」
までいいかけて、旦那さんの手元を見る。食事中だとゆうのにスマホを操作していた。仕事でだれかとメールでもしているのだろう、と思いつつ、そうっと画面を覗いたら、オセロのゲームをしていた。
またか、と、思う。結婚をして5年。旦那さんはほどんどあたしに興味がなくなっていてさくらをあやすようあたしも同じようにあやす。とゆうかなだめる。いつも婉曲気味にあたしの話すことを避けている気がする。
「ん? なにかいった?」
ずいぶんと間があってから旦那さんの声がしてあたしはなんでもない、と、肩をすくめた。さくらは最近言葉が増えて、『バーロー』と、いうようになった。保育園の先生いわく『えっと、多分、ばかやろう、かとぉ』と、とてもいいずらそうに口にした。『ママ』『パパ』『マンマ』『ワンワン』それと『バーロー』保育園に入れたのは至極ありがたいが、悪い言葉を次々に習得してくるので、笑うに笑えないというのが本音だ。あたしは文学部に通っている。そして哲学科。突き詰めることが好きなのだ。さくらもきっと今『バーロー』の意味を突き詰めているのかもしれない。
しかし、さくらを産んでからセックスレスであたしは身体がさみしいと感じていた。出産した女は出産前よりも感じる。と、どのサイトにも書いてあった。個人差もありますが。そうやんわりと添えてはあったが。
あたしはいったいどうなんだろうか。他の男とセックスをするのは浮気になるのでまずい。けれど、旦那さんといまさらできない。とゆうか旦那さんをあたしから誘ったらぎょっとなるに違いない。旦那さんはいってもまだ28歳だし、性処理はどうしているのだろう。ふと、そんなことが脳裏をかすめる。自慰? あたしは首を横にふった。
「ユーリ、今日さ、午後から時間あるぅ?」
講義が終わってぼーっとしていたところだった。昨夜さくらが夜泣きをやらかし寝不足だ。
講義の先生の声が秋の緩い、いや緩すぎる空気と同調をして頭の中は半分だけノンレム睡眠中だった。はっと、顔を上げると、目の前に水野さんが座っていた。
「ていうか、よだれ、出てるし」きゃはは。水野さんがハンカチであたしの口元を拭いてくれ「もう、ユーリさ、本当に子どもみたい」と、笑いながら続ける。あはは。子どもがいますけどね。そういいながらあたしは目を擦った。
水野さんはあたしよりも一つ下で24歳。浪人しているのであたしたちは皆よりもお姉さんだけれど、大学にくると年齢を忘れる。たまにいやに老けた人もいるし。ハゲもデブもいる。
「なに? 水野さんは? 今日講義ないの?」
「あるような、ないような」
なにそれー。あたしはまたクククと笑った。
「ユーリにね、合わせたい人がいるんだぁ」
「え? 誰? えええ? もしかして、性感エステの次郎ちゃん?」
「おお、するどい。今日の午後三時に予約してあるんだぁ」
水野さんはそこで言葉を区切って唇を舐めた。秋って乾燥してんなぁ。と思う。あたしも唇を舐めてからカバンから薬用リップを取り出して唇に滑らせた。
「うん。そうなんだ。ユーリさ、もしよければあたしの施述しているところを見てみないかな。よければユーリもしてもらうといいよ。はじめは一対一だと不安でしょ。ユーリはいちおう、人の妻なんだし」
人の妻。ひとのつま。その単語に思わずプッと吹き出す。
「そっか。そういえばあたし人妻だったわ」
「なによ。いまさら。さくらちゃんのママでもあるのに」
性感エステの話はずっと前から聞いていた。けれど今一歩踏み込めなかった。
旦那さんに悪いから。そのような有り体な理由ではない。さくらの顔があたしの目の前に浮かぶのだ。
「見てさ、ユーリが決めて。次郎ちゃんは観覧大歓迎だって。それでユーリがやる気になればいいし、無理ならやめるしで」
うーん。あたしはうなった。
___________
デーユースでとった簡素なビジネスホテルであたしと水野さんと次郎ちゃんが顔を合わせてから30分が経とうとしていた。
次郎ちゃんという名前から連想をしていたのは思い切りダサくて胡散臭い男性だった。けれど、ええ! 次郎ちゃんとの初見での感想は端的に『いい男』だった。35歳という年齢のわりには落ち着いていてそれでいてゆっくりとした口調で喋る人だった。
「かすみちゃんは人に感じている姿を晒しても平気な人なんだよ」
そういえばさ、あたしは水野さんにいくつかの疑問を切り出した。あたしが見ていても平気なのか? そういえば。裸になって感じる顔を見られても。それを代弁して次郎ちゃんがこたえた。ああ、そういえば水野さんってかすみってゆう名前だったけ。すっかり忘れていた。結構大胆なんだねぇ。あたしは感心して感嘆をもらした。
「ていうか、あたし女でもイケるんだ」
「え? オンナデモイケル とは?」
あたしは目を泳がせつつ疑問を口に落とした。
「だからそのまんまのことよ」
ふふふ。水野さんが妖艶に微笑んだ。
おや、と思った。これはまさかいかんやつでは。脇汗がすごい。
「あはっ、ユーリはそういう対象ではないからね」
えっ、やだぁ、そんなぁ。あたしは心を見透かされたようで耳朶を赤らめた。
「じゃあ、施述を初めていきますね。時間は80分です。ユリさんはどこにいてもかまいませんので」
次郎ちゃんの合図で水野さんがガウンを脱いでベッドにうつ伏せになった。すばらしいプロポーションとはいいづらい部分もあるけれど、ひいき目にみてあたしの好きな身体であることには間違いなかった。ハリのある胸。ハリのあるお尻。尖った乳首。そしておどろくのはその色の白さだった。漂白剤でも飲んでいるのではないのか。というほどに肌が白かった。レズではないがさわりたいと心の中がざわついた。
仰向けになった水野さんに温めたオイルをそっと垂らしてゆくところから始まった。オイルを湯煎で温めてあることに気がきくなぁ。と感心をする。
水野さんは眉間にしわを寄せている。これがよくある羞恥に顔を歪めるということなのだろう。柔らかそうなおっぱいをつぶさないように揉みしだいてゆく。その掌の大きさがちょうどよくおさまっている。水野さんのおっぱいの先はトントンに尖っていて興奮を隠しきれない様子がありありとわかる。
「あ、はぁん、」
かわいらしい吐息が洩れるたびに目が離せないし、あたしの下半身もやけに熱を帯びていて尿意を感じている。陰核が飛び出てきたようでショーツのクロッチにあたる。水野さんの乳首に次郎ちゃんの手がふれるたびあたしも乳首が痛くなった。
よがりまくる女の痴態を目の前で見たのはもちろん初めてだったけれど、それが水野さんとゆう友達だったとゆうのもあるけれど、女が男によって愛撫をされ歓喜の涙を流すことに対してなにも隠すことなどはない、臆すことはないと思った。人間らしさがにじみ出ている。
水野さんは何度も潮を吹いた。あたしは吹いたことがないのでそれはそれは神秘的な経験になった。感じている水野さんを傍観しつつあたしは自分で自分を慰めた。その姿を察したのかちらっと次郎ちゃんが一瞥しニヤッと笑った。
あたしも笑いかえし、あ、で、でちゃうーぅぅ! とゆう水野さんの声がしたと同時にあたしも指でイッタ。
シーツは一面に濡れていておもらしをしたようなありさまになっていた。シーツの下に敷いてあった茶色のバスタオルはその役目など果たすことなく水野さんの汗だか愛液だか潮だかわからない液体を吸い上げるものとしてだけ大いに役立っていた。
~ゆれてゆられて~
あたしは今電車に乗っている。平日の昼間。まだらにいる人たちのほとんどといっていいほど、おじいちゃん、おばあちゃんと呼んでもいいほどの年齢層が多い。たまに若いスーツの男性を見かけるが稀だ。
窓の外に目を向けて流れる景色を見ている。ふと、窓に黒い影が映りこんできて、隣に誰かが座る気配がした。
男性特有のコロンの匂いがあたしの鼻梁をくすぐる。
「ここ、座ってもいいですか?」
低音ボイスの声を背にあたしは窓の外をみながら、うなずいた。平日の昼間である。席などたっぷりと空いている。あたしの視覚に入る人など誰もいない。振り向いて、顔がみたい。けれどぐっと我慢をして男性の出方を待つ。
ふっと、空気が動く気配がしあたしは身を強張らす。そして吐く息をとめた。
膝上のタイトミニの中にゆっくりゆっくり手が入ってくる。ドキドキする。手は太ももを散々撫ぜ回してから、パンティーのクロッチ部分に到着をした。一本の指がパンティーのクロッチを上下させてワレメをなぞる。
「アッ……、」
つい、声がもれた。それを聞いた男性があたしの耳元で息を吹きかけるよういじわるくささやく。
「シー。黙ってください。後ろの席にご年配のご夫婦が座っています。声、聞かれちゃいますよ」
そうやってしている間にも指はまるでミミズのようくねくねと動く。本当は顔を見ないよう努めようとしたけれど、つい振り向いてしまった。
え? わ、若い? そして、ジャニーズ系のイケメンじゃない。
目が合ったと思ったら男性が急に俯く。かわいいなぁ。と思う。
あたしはもういいや。と、諦めて男性の首に腕を回してキスをした。ミントの味。きっとタバコを嗜んでいるのだろう。若いのに、なんていってはいけないけれど、下を絡めあうキスはあたしをほどんど満足させ虜にした。
キスをしながら男性の手は器用にあたしのセーターをまくりあげてブラジャーのホックを外す。指が乳首を捉えてコリコリと音がなりそうなくらいにつまみあげた。ハァン、いや、いや、あたしはいやでもないのに抗う真似をする。悪戯の手はいやがるほど強くつまみ上げる。空いた方の手はどうとうパンティーのクロッチをずらし、陰核をつついた。
「すごい、濡れてるね。ここ」
ここ、と、いった声があまりにも官能的すぎて、何度か陰核を突かれ弄られているうちに、陰核が膨らんだ感覚がおしよせ、くすぐったくなり、何度目かの刺激でイッテしまった。
指でイクなんてことはここ数年なかったことだった。イッタあと
「イッタね。よかった」
男性の安堵の声音がした。乳首はまだつままれたままだ。トントンに尖った乳首。現実に戻ると後ろの席にる老夫婦だろう人達からか寝息が聞こえる。
緩く流れる電車に緩く入ってくる温かい日差し。
「あのぅ。本当にイキました」
口がやけに乾いていたので乾いた声で笑った。
「それはそれは。よかったです」
男性も優しい目をして微笑む。あっ、と、何かを思い出したのか、紺色のカジュアルなトートバッグから、ペットボトルのお茶をとりだして
「はい。飲んでください。僕、口がからからで。乾燥してるし……」
「ありがとう」
男性も同じ銘柄のお茶を持っていて、一緒にゴクゴクと喉を鳴らして飲んだ。
「こんなおばさんでごめんなさいね。それに、電車で痴漢してくれなんて無茶な要望をして」
「なんの。なんの。女性の願望を叶えるのが僕の役目ですよ」
「ふふふ。そうね」
次の駅で降りてこの時間は終わる。イッタことがないんです。というようなことを女性向け風俗店に問い合わせたところ
『興奮するシチュエーションってなんですか?』と、質問され
『痴漢です』
と、即答でこたえた。
『あー』電話対応の男性は納得をしていた。痴漢をしたい男性がいるように痴漢をされたい痴女もいるのだ。
「あたし、変体かしら?」
「えっ?」
まだ身体が火照っている。本物の痴漢に何度もあっているけれど、やっぱり名のある合法のお店に頼むに限ると思う。
「あはは。なんでもないわ」
男性もあはは、と一緒になって笑った。
~まゆこのこい~
「ねぇ、ずっと、このまま寝てたいよぅ」
白昼からラブホテルにしけこんでいる。じゃかりこのサラダ味と、サラダチキン、缶チューハイの柚子味と、ハイボールを買って。
テーブルの上には食べかけのサラダチキンの汁がこぼれている。あたしの隣で耳を噛んで甘える人は、いつでも最後まで全部食べ物を食べない。なんでも少しだけ残す。
薄暗い部屋にところどころこぼれる細い光の光線が余計に非日常の空間をつくりだしている。
あたしは隣にいる人の頭を撫ぜ、「そうね」と、短く応えた。
「出来るならたーくんとずっと居たいわ」
あまりに短い返事だったので、ほんとうは、普段めったに口にしない台詞に胸内でひどく恥じた。
「まゆこさん、だってさ、とても好きっ」
この人は容赦なく甘えてくる。まるで猫のように。屈託ない笑顔で。あるいは子どものそれのように。
15歳も年上のあたしに。
たーくんは出張ホストだ。甘え上手だし、なんといっても綺麗な顔にシミひとつない身体。癖っ毛の黒い髪の毛。白魚のような指。
そして甘いマスクによっての苦い愛撫。月に2度程指名し呼んでいる。
「まゆこさんってさ、社長さんでしょ?」
ターくんには本当のことを話している。あたしは小さなデザイン会社の取締役だ。あたしは、そうよ、なんで? と、質問返しをした。
「僕を雇って欲しい」
「はぁ?」
たーくんは冗談か本気なのかわからないことを唐突に口にした。
雇う? それは社員として雇うなのだろうか。それともあたし専属の秘書的な感じで雇ってということなのだろうか。
あたしはクスクスと笑う。たーくんも口角を右にあげて少しだけ笑った。緩くかけてある暖房で二人とも裸だ。あたしはその綺麗な背中にそっと唇を這わす。わ、くすぐったいや。身じろきをしたたーくんの声はちっともくすぐったそうではない。
「まゆこさん、キスして」
あたしは背後から前に向き直ってたーくんの柔らかな頬を両手で持ち唇を重ねた。柚子チューハイの味とタバコの味を互いに絡めあう。なんてここちのいいキスなのだろう。薄く目を開ける。たーくんはうっとりとした顔をして目を閉じていた。たーくんの指があたしの蜜の穴にゆっくりと飲み込まれていく。あっ、少しだけ身を引き抗う。細くて綺麗な指があたしの蜜の穴に入っているということだけで下半身がとても熱い。愛液が滴るのがわかる。たーくんがちゅっぽと指を引き抜いて
「ほらぁ〜。こんなにトロトロになってるぅ〜」
意地悪な声をだして羞恥心を煽る。
「もう!」
あたしはたーくんを押し倒して胸に顔をうずめた。たーくんの下半身は全快に勃っていた。勃っているとゆうだけで至極嬉しい。あたしでこんなにも感じてくれているなんて。男性の勃起は女性の自信に繋がるのかもしれない。
「大きくなったね」
「まあね。僕若いもん」
「そうね」
それから何度も抱き合ってキスをし愛撫を交互にし最後にマッサージをし合った。足つぼマッサージがとても得意なたーくん。
「足の裏ってね、ツボがすごいのよ。知ってるでしょ?」
マッサージに必死のたーくんに声をかける。そろそろ時間も迫っている。この時間がいつまでも続いてほしい。
「知ってるよ」たーくんはいいきってから
「ここはね、性感のツボ!」と、土踏まずあたりを思い切り押して続けた。
「あん。そこ感じるわぁ」
「まゆこさん。劇団員になれそうですね」
あたしは肩をすくめ笑う。たーくんも一緒に笑っている。
甘えてもらったり甘えれる存在がいるということだけでうまく生きていけるのかもしれない。
~ねぇ、すって~
「お、お願いよっ、す、」
素っ裸でいるのはあたしだけで目の前の彼は正装とでもいうべきか、はたまた戦闘服というべきなのか、彼はきちんとした高価だろうスーツのままあたしの横に腰掛けている。ホテルの灯りは調光可能なの最小限にまで落とされた照明があたしを大胆にさせているのもある。
「えっ? なあに? 聞こえないなぁ?」
聞こえない訳などはない。なにせテレビだってつけていないし、地上8階の最上階。防音だって耐震だってしっかりしているホテルだ。聞こえないなぁ、と、ささやきの声をだしたとき、成瀬くんは耳の穴に指を入れた。
「もっと、大きな声でいって」
そうっとあたしの唇が成瀬くんの食指によってなぞられる。冷たい指先。長くて細く、男なのに透明のマニキュアを塗っている。あたしは、はぁ、はぁ、と息を乱しながら、自分でデンマを握って一人エッチをしている。
「い、いじわるぅ、」
公開オナニーをどうどうと披露しているにもかかわらず、どうしても痴態めいた言葉がはけない。すでに恥じらうことなどないくせに。裸になるよりも言葉を脱がす方がよっぽど恥ずかしいのかもしれない。成瀬くんがトントンに尖った乳首をつまみあげ
「わお。こんなに固くなってるよ。すごいよ。みさ子さん」
「ああ、もっと、もっとつまんでぇ〜」
腰を浮かしながらほとんどアダルトビデオ女優のように雄叫びをあげる。
「だから、舐めてって、吸ってっていわないとしてあげないよぅ〜」
とても意地悪だなぁといてもたってもいられなくなってけれどどうしても吸っての三文字がいえない。
デンマの刺激はなにせ強烈なので故意に的を外している。エクスタシーを迎えるに至っては、乳首の刺激を添えてイキたい。さあ、さあ、と、成瀬くんが言葉をねだってくる。痴態めいた言葉をどうしても引き出したいのだ。
「す、吸って、成瀬くん。あたしの乳首をぉ」
あー、やだぁ。恥ずかしくて顔から火が出そうになるも出たようで、顔と耳がとても熱くなっていた。背中に薄っすらと汗をかく。
「あっ、」
ふと、乳首に息がかかり一気に人間の体温の中に吸い込まれてゆく。ネロネロとせわしなく動く舌先はトントンに尖った乳首には刺激があまりにも強すぎる。
あたしは、今だ、と、意を決して的にデンマをあてがった。
乳首と子宮はリンクしている。うまい具合に。
「あ、イクぅ」
乳首を吸われたのが決定打になって呆気なくイってしまった。
「はやっ」
みさ子さんさ、本当にイクの早いよね、毎回同じセリフをいわれるも、まあね、と、あたしは肩をすくめた。
「デンマでさ、イクのはそれこそ簡単よ。でも、男性に乳首を舐めてイクのでは訳が違うんだ」
へー。成瀬くんは、女じゃないからわからないなぁ、とつぶやき
「男でたとえるなら、アダルトビデオみたいな感じですかねぇ?」
眉根をひそめつつ、そう付け足す。んー。あたしは唸る。そうなのかなぁ。興奮のスパイスみたいな感じかなぁ。
「あ、わかったわ」
え? なになに? 成瀬くんが興味深々な形相であたしを見つめる。
「ひ・み・つ」
あたしは指を一本差し出し唇の前にあてた。えー。なにそれー。
かわいい男の子は目の前で憤慨しているけれど、どこか楽しげであたしまで楽しくなってくる。
「カイカンを今日もありがとうね」
あたしは部屋の窓をあける。風に乗って香ってくる金木犀の優雅な香りに目を伏せる。
~やさしくしないで~
(どうしてこんなあたしにそんな優しい目が出来るの? あたしを見てるようで本当はど近眼じゃないのかな? 普通の感性の持ち主ならどう考えてもあたしを見つめることなど出来ない思うのに……)
ベッドに並んで添い寝をしている優雅さんはあたしを抱き寄せ頭を撫ぜてくれている。
「ユイさんが眠るまで僕は寝ないよ。だから眠って」
「……、え、ええ」
今夜初めて女性向け風俗店の添い寝やというジャンルのお店に電話をした。本当に添い寝をするだけですか。電話をしたとき訊いてみたら、もちろんです、とゆう見事な即答ぶりを発揮してくれたので今、横に優雅さんがいる。
「あのぅ、」
「なに?」
照明は豆電球にしてあるけれどすっかり目が慣れてしまい、優雅さんの顔が98%くらいはっきりと見える。顔のいい男性はよしてください。と、電話口にいた人にくどく伝えてあったにもかかわらず、この顔面偏差値の高さったらない。参ったなぁ。あたしは意を決して幾つかの質問を施した。
「ふたつほどの質問があります」
「はい」
優雅さんは真面目に耳を傾ける。あたしはそのままひとつめの質問を口にしだした。
「初対面で出会ってあたしのようにブスでも怯まないのですか? 帰りたいて思わないの?」
目を丸めながら優雅さんは、あはは、と、失笑をして
「嫌ならね、辞めてますよ」あはは。ユイさんはそれにブスではないですって。と、付け足す。だって、どう見てもブスですよ。お世辞はなしです。あたしは頬を膨らます。優雅さんはあたしのおでこにかかる髪の毛をどかしてキスをした。
「キャッ」
急なアクシデントに驚き腰が抜けそうになる。
「あ、かわいい、そのリアクション」
優雅さんはいたずらっ子のように歯を見せて笑った。かわいい。うーん。かわいいなどという単語を生まれてこのかた一度も耳にしたことがない。唯一、父親だけが三十路になるあたしを「かわいい」と褒める。親の贔屓目だよ、それって。父親の前でも素直になれないあたし。
「手繋いでもいい?」
「え、ええ」
お布団の中でお互い指を絡ませ手をつないだ。優雅さんの手はギョッとするほどに冷たかった。
「あたしね、恋人つなぎするのって初めてなんだ。いいね。なんだか」
「うん、僕もね、女性の手を握るのが好きなんだよ。知ってる? 手をつなぐこともね、愛撫と同様なんだって」
へー。そうかもしれないと思った。手をつなぐことって普段の生活で同性でも異性でも滅多にしないことだ。それを今、異性としている。優雅さんの手の温度があたしの体温と同化してくるのがわかる。
なにもセックスにこだわらなくても手をつないだり、抱き合ったりするだけで女とゆうものは英気を養いことが出来てしまう。奥深いけれど存外単純な生き物なのかもしれない。
ちっとも眠れそうにないあたしは優雅さんの手をギュッと握りしめた。
先に眠ってくれますか?
これがね、ふたつめの質問なんだ。あたしはそう話しかけた。隣からはスースーと規則正しい寝息の音楽が耳の穴に届いてくる。
優雅さんはあたしの質問にこたえる前にこたえを出してしまった。
その横顔をじっと見つめる。綺麗な肌に整った骨格。稜線を描いている鼻梁。
よしっ。
~おいしそうね~
「いつもながら見ていてすがすがしいわ。本当に……」
江見くんは目の前にあるサーロイン肉を器用にナイフとフォークを使い分けみるみると口の中に放り込んでいく。250グラムの厚切肉の横に申し訳ない程度に添えてある人参やジャガイモまでもペロッと食べてしまった。あたしは赤ワインを舐めながらその豪快な食べっぷりを見てすでに満足をしている。
「江見くん、ワインのおかわりは?」
「あ、じゃあ、いただきます」
舌で唇を舐めながらワイングラスを差し出す。舌で唇を舐める仕草にグッときてしまう。あたしはついジッと見入ってしまった。
「えっ? あ、僕の顔汚いですか?」
いけない。あまりにも見入ってしまっていたので江見くんは誤解をしてしまったようだ。
あたしは首を横にふって
「ちがう、ちがうのよ。つい、ね。江見くんの豪快さで、あたし、イキそうになったのよ」
クスクス。あたしは笑いながら肩をすくめる。
「イッてください。どんと!」
「まあ! なんてたくましい。江見くん」
まあね。僕食べるの好きですもん。江見くんは小鼻をこすりながらまた笑った。
120分のホストコース。その中でディナー付きコースがあって毎回同じコースで同じ江見くんを指名している。男性と食事をすることが苦手なあたしに江見くんは楽しさを教えてくれたし、食べている男性の姿がとてもエロティックに見えたのだ。
食べ方が綺麗な男性程、性に対してあまりがっついていなく、食べ方が豪快かつ健啖な人ほど逞しいセックスをするというのがあたしなりの見解だ。それはあながち間違ってはいない。
こうやって出張ホストを何人も呼んでみて一緒に食事をしベッドでも楽しませてくれる男性はたくさん食べてたくさん飲んでたくさん笑ってあたしにもたくさん食べろとすすめる。食事はあたしもちだとはいえ、少食のあたしに
「たくさん食べないと精がつかないですよ!」
そういって食べさす男性はベッドでも優しい。
江見くんは28歳というちょうどいい年齢も相まってかなりの人気を得ている。
それでもあたしとの食事は本当に楽しみと豪語する。嘘かもしれないし本音などは江見くんしかわからない。
江見くんの愛撫はいつもお肉の匂いがするけれど全く嫌ではないし、むしろ官能の火が余計に滾る。あたしも同じ匂いだし同じものを食べてきたからこそ同化した感じがする。お互いの舌と舌を絡ませたキスなどはさっき食べた肉を妄想させる。肉を食べその肉が肉になり血になり体液になる。あたしの体液はきっと肉の匂いかもしれない。
ただ、食事をするだけでもいい。
一緒に美味しいものを食べ、「おいしいね」「うん」そうやって会話をするだけでも満足を得られるのだ。
食事はセックスの前菜。食事をしたらその男性の大半がわかってしまう。
江見くんはそれを裏切ることなく豪快でエッチで素敵だ。
「ゆきさん、お肉って赤ワインだけが合うと思ってません? 意外と白ワインもいけますよ。白ワインって魚ってイメージが強いじゃないですか? いやいや、ちがうんですよね。ワインが基本赤でも白でもなんでも合うんですよ」
「へー。そうなんだぁ。まあ、あたしさ、本当は冷酒がね好きなんだよね。鬼殺しが」
「えー! まじっすか? 実は俺も本当は日本酒が好きなんですよ。寒い日の熱燗。最高っすね」
そうなんだね。今度は居酒屋に誘ってみようかな。
まだまだ行きたいところがたくさんある。あたしはどこに連れていこうかなぁってことだけで胸がいっぱいになる。
~あたたかいくちびる~
そのお客さんとは初見だったけれど、出会った瞬間なぜだか同じ匂いがした。纏っている空気とか雰囲気とかなんといっても異様な気づかい。いやいや、風俗嬢のあたしにそんな気づかいはいらないし。
「あ、いいよ。いいよ。そんなにすぐにシャワーしなくても。てゆうかさ、ちょっとお姉さんと話がしたいなぁ」
えっ? そんなことをいうお客さんに出会ったことがないあたしは本当に驚いてしまい、え、あ、の、と、そんな感じでやや取り乱した。余裕を見せてけど実は……。的な出で立ちでもない。
「お、話しですかぁ、けど、時間がなくなってしまいますよ」
お客さんは90分という時間を提示した。90分って意外に長いようで短い。プレイをしたら一息をつく暇なく時間が来てしまう。
射精をさせることがあたしの仕事で話し相手になるのは仕事ではない。話に興じてしまい結果最後急いで手コキで。などというぞんざいなことになどしたくない。
「だから、」
あたしは、だから早くシャワーに、そういいかけたらお客さんが話を遮って
「いいから。ナオミさんは僕の隣に座ってよ」
鷹揚な口調で促された。
「僕はね、」お客さんの隣に座るとあたしの方を見ながらゆっくりと手をつないで話し出した。
「出張ホストなんだよ」
そっか。特に驚かない。そんな気がしたから。同じ匂い。同業者の。けれどどうして出張ホストが風俗嬢を? あたしは話しの続きを待つ。
お客さんもといホストのケントさんは普通に爽やかイケメンだ。紺のブレザーをうまく着こなしている。童顔な顔に黒目がちなアーモンド型の目。
「いつもさ、癒す方でしょ。だから風俗嬢さんにいつも僕がしているようなサービスをしていただきたくて呼んだんだけど、ナオミさんを見ていたらついお世話したくなって」
あはは。そこでケントさんはクスクスと笑う。えっ? なぜそこで笑うの? あたしは首をかしげる。
「僕さしてもらうよりも、サービスをする方がいいってわかったんだ。風俗を利用するの初めてだけれど、お客さん側のね、気持ちがわかったような気がする」
あたしはどんな風に気持ちがわかったの? と訊ねた。
「えー、なんていうのかなぁ。ドキドキするし、ワクワクするし。ナオミさん、綺麗だし。キスしたいし。触りたいしって。僕もお客さんにそう思われたいしそうなりたいなーって」
「そっか。じゃあ、今は、お客さんだと思ってキスさせてくれる?」
ケントさんはまばたきをしてから目を細めてあたしを抱き寄せた。いつもは裸と裸で無言の話しをし白い液体を放出させるだけのあたし。ケントさんの唇は柔らかくて甘い匂いがする。唇を少しだけ割って舌と舌を絡め合う。
あれ? キスを真剣にしたのいつぶりだろう。
ふと、そんなことが頭の中をよぎる。
ホストだからキスがうまいとか女性の扱いがうまいとかそれもあるのかもしれないけれど、風俗嬢もホストもやはり清潔感や見た目が大事だと察した。
長い長いキスのあと無理やりベッドに押し倒し横になって時間まで喋った。喋るのがあまり得意ではないのに同業という安心感からいやに饒舌に話しをするあたしがいた。
出張ホストの仕事も大変だぁ。けどこんなに女性にたいして渾身的な男性が増えたらいいのになぁー。って思いつつ、あたしはムスクの匂いに抱かれつつゆっくりと瞼をつぶる。
「今度はね、あたしがケントさんを指名するわ」
「あはは。ありがとう」
~すきなのに~
「佐藤って浮気したことないでしょ?」
とうとつに切り出されてあたしは微笑んで、ないないと手のひらを顔の前でヒラヒラと振った。
目の前にいる涼子は細くてしなやかな指先でアイスティーのストローを持っている。真冬だというのにこの喫茶店は真夏のよう暖房が効いている。まわりを見回す。ほとんどの人が冷たいものを注文している。
「なによ。急に。浮気なんて普通はしないでしょ?藪から棒に」
「はい? 浮気をしない主婦の方がね最近少ないのよ。あなた本当に生真面目ってゆうかなんとゆうか」
涼子は氷で薄まったアイスティーをすすりながら呆れた声をあげた。
「いいの。あたし。夫ラブだし」
「へー。ごちそうさま」
本当に夫が好きだ。子どもはまだいない。けれど結婚3年経った今でもラブラブだとは思う。
けれど……。
「あたしはね、浮気してるよ。うーん。浮気ってゆうか、ホストにねラブなんだぁ〜」
「ホストって?」
「だから、出張ホスト。お金を介してあってるの。なんかさ、お金を払っているってのもあるけれど、ちっとも後ろめたくないのね。むしろ夫に優しくできるんだ」
酔ってもいないのに涼子はやけに饒舌でそれでいてうっとりとした表情を向けた。へー。そうなんだぁ。あたしはそのときはちっとも興味希薄で右から左へ聞き流していた。
______
「けれど、僕を呼んだってわけですね。佐藤さんは」
「佐藤さんってね、苗字で呼ぶのはよしてちょうだい」
あはは。タケルくんは大仰に笑う。
「はい。はい。み〜ほさん」
タケルくんは涼子の紹介だ。あのあと、涼子のごり押しもあって一度だけ呼んでみて。紹介割があるの。と、両手を合わせられてしまい断れなかったのだ。
「この前はオイルでしたよね? 今日はバウダーを試しませんか?」
「パウダー? ですか? 天花粉の?」
「はい。まあ、うつ伏せになってみて」
シャワーも済んでいたのでうつ伏せになる。タケルくんはいつも洋服は脱がない。白いワイシャツに紺色のスラックスという清潔感ある出で立ちだ。
バスタオルをはらりと剥いでうつ伏せになった。
ハウダーを落としますね。タケルくんの声は心地がいい。背中に今までにないようなソワソワ感が押し寄せて、キャッと声をあげてしまった。
さらさらと滑っていくパウダーはなつかしい匂いもするけれどそれ以上にタケルさんのフェザータッチが絶妙であたしはため息をひとつ落とす。
「くすぐったいわ」
身体を捩って素直に告げる。くすぐたいという単語は感じてるという同義語。タケルさんが以前そういっていた。
背中からお尻太もも足の裏足の指。
おもてむきになって乳首からおへそ。そしてもっとも性感帯が走っている秘部に向けでパウダーの舞いがおこなわれた。
声もだせないほどの強いカイカンがあたしの身体の全てを支配した。感じすぎると身体が震える。
目の前がプールに潜ったように潤んでいる。あれ? あたし……。
「どうしたの?」
タケルさんがあたしの頬を伝う涙を短めな爪の指先で拭った。
あたしは首を横にふるふると少女のように振ってから
「わからない」
それだけ声に出して顔を両手で覆う。
「夫のことは好きなの。けど、けど、」
タケルさんは優しい顔をしてあたしの背中を撫でている。いいですよ。感じても。なにも後ろめたくなどはないから。みほさんは女です。誰でも感じて頭の中が真っ白になりときに取り乱したりもします。
だから。
暖房が効いていた部屋だけれど裸だったと意識したせつな急に悪寒が走る。
~いちゃいちゃだけ…~
2週間前に性感コースを頼んだばかりなのに、また明日の夜の枠に予約をいれた。人間とゆう生き物はなんと精密な脳を持っているのだろう。一旦覚えた快感が脳内にインプットされ一種の中毒になる。
まるでタバコのようだ。
また吸いたくなるように、またあいたくなる。
セガミさんと出会う前。あたしの身体は3年程男性のぬくもりや声そして官能の愛撫のことなどすっかり忘れていた。
決してモテナイ訳ではない。ただなんとなく男性の体温から遠ざかっていただけだった。仕事が忙しかったのもある。俗いう『お仕事が彼氏』ってやつだった。
それが、ふとしたことで呼んでみた性感ホスト。あたしはその時、初で潮を吹き、感じすぎて白目を剥き、あげく吐きそうになった。
ほどんど狂気のような嬌声をあげていたのだ。
知らなかった。あたしの中の牝(メス)の部分。
欲していた男性の体温を。
しっかり糊で固くなっていた真っ白なシーツは最後は見事に水たまりになっていた。それを見て急にカーッと身体が火照ったし、初対面の男性にここまで感じさせられるなど羞恥がかき乱された。
その次の日はとても調子が良くって『あさこさん、今日顔色いいわね』とか『なんだかフェロモン出てるぅ〜』と、嘘かもしれないけれど何人かの同僚にいわれた。
『やだぁ。気のせいよ』なんて笑いながら話しを濁したけれどまんざらでもないのは自分でもわかった。
__________
「また、呼んじゃった」
やっとあえた。2週間ぶりにあうセガミさんはあいかわらずエスコートがうまい。ラブホテルのエレベーターに一緒に乗る。手を恋人つなぎにして。
「また、呼ばれました。嬉しいです」
狭い密室の中でフレンチキスをされた。セガミさんの顔はお面のように綺麗な顔をしている。あたしはついうつむいた。恥ずかしい。
「あさこさん、今日はどのような御プランで行きましょうか?」
部屋に入って真っ赤なソファーに腰掛ける。セガミさんはそうあたしに質問を向ける。80分とだけしかいってない。なのでホストがこの時間をどう使いたいのか聞いてくる。とてもいいアイディアだと思う。そのときにしたいこと。
「いちゃいちゃ」
「えっ?」
いちゃいちゃ? セガミさんが同じよう繰り返し首をかしげる。
「そう。いちゃいちゃしたいの。時間目一杯」
「毎回、いちゃついてますよ」あははは。セガミさんは笑う。あたしは、首をよこにふってから
「違うの。ソフトいちゃいちゃって感じ……かなぁ。脱がなくてもいいの……」
ラブホテルの簡易的なソファーはお尻がかたい。うちのソファーではないことだけでドキドキしてしまう。
「わかりました」
低い声が上からふってくる。そうして温かい手のひらがあたしの髪の毛を優しく撫ぜる。華奢に見えるけれどやっぱりこの人は男なんだなということを突きつけられる。
柔軟剤の匂いのしたシャツに抱かれあたしはまるで猫になる。そんなに頑張らないでもいいんだよ。心の中の声が聞こえるようだ。
シャツに香る柔軟剤の匂い。もしかしたらセガミさんには家庭があるのかもしれない。
なにも知らない。表面的なことだけしか。
けれどそれでいいのだ。知ってどうする? 今だけはマサキさんはあたしのものだ。
「今度は背中を撫ぜて……」
「はい」
もう……。
背中にある手が温かい。誰かに撫ぜて、いや、触れらてもらうことは生きて行く肥やしになる。
~しめくくり~
「じゃあ、先に行くわ」
「あ、はーい。お義母さんによろしくいっといてね」
おお〜。わーったよ〜。夫は、土産なにがいいかなぁ、とつぶやきながら玄関の扉を開け年末のあわただしい光の中に吸い込まれていった。
はぁ〜。行ったかぁ。
と、一息ついている場合ではない。
今日は大晦日。夫が先に実家に帰り、あたしはうちの大掃除をしてからやや遠方にある実家に向かうということを毎年している。
「いっそげー!」
あたしは腕まくりをし、ゴム手をして一気に掃除を開始する。
換気扇から始まり、窓拭き、シーツの洗濯、冷蔵庫の中身の整理。普段共働きなため、年末でしか掃除出来ないところを徹底的に磨き上げる。
そう、年末でしか掃除出来ないのはもうひとつある。
あたしの『性欲』だ。
ふと、時計を見ると短い針と長い針が天辺で重なっている時間になっていた。ジュンさんにはおととい連絡をしてある。
《ジュンさん。キヨミです。もう年末がきました。年に一度の大掃除にいらしてください。お待ちしています》
《こんにちは。キヨミさん。もちろん貴女のために時間はあけてあります。一年ぶりですね。キヨミさんにあわないことには新年を迎えれません。笑》
笑。の後にはニコニコマークの絵文字が添えてあった。
まるで織り姫と彦星みたい。そう、メールをしようとしたけれどやめた。夫と同じ職場な上一緒にいる時間が普通で一人身になるのはこの大晦日だけなのだ。
_______
「おじゃまします」
ジュンさんは時間通り自宅にきた。午後の1時に。1年前よりも少し痩せた感じがする。殊勝な面もちで
「やっぱり旦那さんがいる自宅っていうのは本当未だに緊張しますね」
綺麗になった部屋をくるんと見回してつぶやく。
「あたしもですよ。だって……」
そのとき、ジュンさんがささっと移動しあたしを抱きしめた。あっ、声をあげる。そうして唇を重ねた。わわ、キス。キス。そういえばキスを最後にしたのもジュンさんだった。気がする。
ネチャネチャという粘着音が部屋に響き渡る。猛烈に抱き合い縺(もつ)れ合いながらリビングのソファーに寝かされた。
「あっ、こ、ここじゃあ、し、寝室に、いき、」
いきましょう。と最後までいわせてくれず、そのまま一気に洋服を脱がされた。慣れた手つきでブラのホックを外される。あまりの俊敏な動きは女慣れしているという事実を突きつけられる。
けれど、その思考は次の瞬間なくなる。
ブラジャーからまろび出たおっぱいの先端は抗っても正直にトントンに勃起している。
「こんなにかたくして」
ジュンさんは容赦なく乳首を指先で弾きながらも片手でパンティーのクロッチをゆっくり撫ぜた。
あたしは、腰を浮かせて痺れる下半身を弛緩させる。クロッチにはシミがついているだろう。愛液の滴りが自分でもよくわかる。
クロッチをずらし、ジュンさんの指がそうっと割れ目に入ってきた。
「ああっ!」
「すごい、ヌルヌルだ!」
ただのソフトなタッチなのに指を2、3度上下させたら呆気なくイッテしまった。
「うっそ? イッタの?」
ジュンさんが素っ頓狂な声をあげる。あたしは肩で息をしながら、コクンと首を折った。いいわけのように口を開いた。いいわけじゃないけれど。
「今年はジュンさんに始まってジュンさんで終わったの。オナニーもしてなかった。だからものすごく敏感になっていたみたい。まだあそこがジンジンしていてまるでそこが心臓になったみたいよ」
「キヨミさん」
ジュンさんが名前を呼ぶ。真剣な声に耳を傾ける。
「はい」
「……、オナニーをしてくださいね。健康と若さを保つために」
「えっ?」
ジュンさんはオナニーをかなり推奨してくれた。オナニーでも女性ホルモンの活性化になるようだ。
「わかった。来年の目標はオナニーを頻繁にする! に決めたわ」
「おお、それはいい。てゆうか旦那さんと手をつなぐだけでもいいですよ」
「そうね。そうかもね」
ジュンさんが帰ったあとあたしは夫のいる実家に向かった。
新鮮な気持ちで。なぜだか夫にあいたかった。
新しい年を心地よく迎えれそうだ。
「ジュンさん来年もよろしくお願い申し上げます」
ジュンさんの笑顔はとても神々しかった。
~ほんきになっても~
最初は興味本位だったし、何事にも真剣にならない性格のあたしだから性感エステというものにも絶対にハマらないという自信があった。まっ、一度は体験してみるか。そんな軽率な考えがあまかった。
なぜなら今まさに『ハマっている』のだ。性感エステに。エステティシャンの『ノゾム』さんに。
今日で5回も指名しているし、あったあとでもまた直ぐにあいたくなる。エステの癒しを求めている以上にノゾムさんの存在に依存している。
「あ〜、参ったよ〜」
あたしは参っているけれどちっとも参ってない口調でノゾムさんの前でつぶやいた。
「なにに? 参ってるの? ナナさんは?」
平気な顔をして他人事のよう訊いてくるのだから余計に参ってしまう。とにかくかわいいのだ。
「いってもいいのかな? ノゾムさんはそれを訊いたらあたしの今参っている悩みを叶えてくれるのかな?」
ん〜。それはどうだろうなぁ? 腕を頭の後ろに組んで目をつむった。たぶんきっとなんとなくは気がついている。あたしが本気で好きになりかけていることに。こんな状況はきっとよくあるだろう。一体女性側が本気になった場合エステティシャンはどう打破をするのだろうか。
嫌われるような仕草をする?
はっきりと断る?
お客さん(顧客)を減らさないために嘘恋愛をする?
「好きなの? 本気で好きになって」
「ナナさん……、」
最後の語尾は唇で塞がれた。温かい唇の温度はやや高めの37度くらいだ。長いキスのあと、ゆっくりと唾液を垂らして離れていく。
「僕もナナさんが好きです。けれど、その好きは決して『ラブ』ではなく『ライク』の方です。お客様に好かれるのが僕の仕事ですしそこで嘘をついてまでもお客様を引き止めません」
ハキハキとしているしそこにはプロとしての矜持が垣間見えてあたしは自分のいった言葉をとても恥じた。ノゾムさんはそうだ。プロなのだ。誰のものでもない。テレビでいうところのアイドルなのだ。
あたしだけのものにしたいとか、そんな軽はずみな考えを持ち合わせている時点で重たいお客さんになってしまう。
割り切ってお金を介しているのだから、割り切らないといけないのに。それでもノゾムさんはあたしにいつものようきちんと抜かりなく愛撫を施してくれるし、キスをたくさんしてくれる。
おんなならば誰しもが勘違いを起こしても仕方がないのだ。とも思う。
勘違い、かぁ。あたしはつぶやきつつ肩をすくめてみせる。
「じゃ〜ん」
目の前の彼は重たい空気の中でも決して重たくしない。じゃ〜ん、とくだけた口調で取り出したものは『電マ』だった。
「これ、試してみませんか。ホテルに備え付けで置いてあったので」
へへへ。ノゾムさんがいたずらに笑うからあたしも負けないくらいの笑顔で笑ってみせる。
「うん。したい。電マして」
「お安い御用です〜」
笑顔、癒し、恋心を一気に与えてくれる、爽やかな青年に感謝をしないといけないなぁ、と、ぼんやりと考えつつもいつのまにか、陰部に電マをあてがわれていた。
部屋に無機質な機械音が鳴り響いてあたしはどうしてだか笑いが止まらなくなっていた。
~すみません~
「こんなおばさんでごめんなさいね〜」
こんなおばさんだけれど、男性の温もりに飢えていて真冬の海原に飛び込む勢いで最近もっぱら流行りの『女性向け風俗』のお店に電話をした。ジャンルは出張性感エステ。
エステとゆう呼称はちまたでもチラホラと見るので性感と2文字がついていてもなんとなく安心を与えた。普通のエステは2回ほどご招待で行ったけれど、もうこの歳だし今更エステなどに通うという気力もなくてやめた。
51歳で独身だし、ややぽちゃで、顔も良くないし、シミとシワももちろんある。
「いや、いや、ぼくをご指名くださってありがとうございます」
『性感エステ・ルイ』というお店の中の『マサヤ』さん? くん? を指名した。さん、と呼ぶべきか、くん、と呼ぶべきか、対峙して戸惑う。ネットの年齢は32歳だと書いてあったけれど、その年齢よりもとても若く見える。
「みつよ、さん、と呼んでもよろしいでしょうか?」
とても礼儀だだしい上にきちんと目を見て喋るなぁ、と感心しつつ、はい、とうなずく。
「あなたは? マサヤ、さん? かしら? マサヤ、くん? のほうがいいのしら?」
名前の呼び方に迷ったので本人に訊いてみる。と
「あはは。そんなことですか! みつよさん、気にしすぎ! マサヤでいいですよ。もう、呼び捨てちゃってください!」
あはは、大仰な笑いはちっとも嘘くさくなくてあたしも同じようにあははと笑った。
「わっ、笑顔、ナイスです! みつよさん!」
「もう! やだぁ、でもありがとう」
マサヤは犬のように人懐こくてそれでいて嫌味がない。『こんなおばさん』を『普通のおばさん』として扱う。お仕事でしているとわかっているけれど、何年ぶり? くらいに気持ちがいい。
事前のアンケートでやけにNG項目が多かったのでマサヤは目頭を揉んでから、キスもダメかぁ、と、つぶやく。
「あ、いろいろと恥ずかしいので、すみません……」
咄嗟に謝る。マサヤはアンケート用紙から視線をあたしのほうにうつし、首をよこにふった。
「いいえ。一緒に慣れていきましょう。今日は背中と臀部のオイルトリートメントでよろしいでしょうか?」
ラブホテルに入ったのは2回目だ。今時のラブホテルはなんだかおもちゃの小箱だと思う。その中にいるあたしとマサヤ。あたしは、まるで少女のように頬を赤らめつつ、顎を引いた。
ベッドにうつ伏せになる。いくら背中でも裸だ。背中にシミなどはないのだろうか。ふと、不安になった。けれど、そのようなことはまるで杞憂で、お背中、とても綺麗です、と、世辞かもしれないけれどマサヤがいった。
嬉しかった。背中にマサヤの指が滑るたび、背筋がビクンとなって子宮がうずいた。男性に触れてもらったのはいつぶりだろう。ほどんど記憶がない。あたしは心地のいいエステという名の愛撫を堪能をする。目をつむると脳裏にはマサヤが屈託なく笑っている。
『こんなおばさん』でも、あたしはやはり女なんだなぁ、と久しぶりに感じた。
「ねぇ、マサヤ」
「はい?」
時期に時間が来る。おもちゃの小箱の中の出来事はあとで夢かもと思うかもしれない。
「また、指名してもいいかな? こんどはNG行為、少なめにしてみるから」
「ええ。もちろんです。僕はいつでも駆けつけますよ」
~ここが、いいの~
待ち合わせの時間まで後2時間。ルイくんとあうのは今日で2度目。一度きりで済むわけなどはないって自分でも思っていたけれど、思っていただけだった。やはり想定内でまた指名で呼んでしまった。
初めて頼んだのは2週間前だ。後2時間で2度目で2週間前で、あげくあたしは38歳。って年齢を省けば『2』が3つってラッキー! なんてうかれていて待ち合わせの駅にいく電車を乗り間違えてしまい、急いでルイくんにLINEをした。
【ルイくん、少しだけ遅れます。間違えて反対周りの電車に乗ってしまいました】
その文字とウサギがペコりんとお辞儀しているスタンプを送る。時間で稼働しているルイくんだからきちんと謝らなとならないし、あるいは遅れた料金も多少は払おうと思っていた。
【わかりました。遅れても全く問題無し! 駅前のスタバにいますねー】
返事は拍子抜けするほど呆気なく、おつかれさまでーす。というお笑い芸人のスタンプが連続で送られてきた。ホッとする。何度も呼んでいる常連でもないのに遅刻をするなんて。あたしは窓から見える流れる景色に目を向ける。今日はどうしてもらおうかなぁ〜。いやらしい夢想をしているときが一番楽しい。それを叶えてくれるちょっと頼りない身体の色白の黒目がちのルイくんの顔が目に浮かぶ。
「さーて、さて、ナミさん、遅れたお仕置きをしますよ」
駅に着いてLINEをしたら改札口にいるよ、と返ってきたので首をキョロキョロとさせていたらルイくんが素敵な紺色のスーツを身にまとってそこにいた。
「す、すみません、」
目をふせめがちにし謝る。ルイくんは、あはは、冗談ですよー、とはにかんで笑う。まあ! あたしもつられて笑った。
駅前から少し歩いたホテル街の中の一室に入る。あたしは一人でホテルには入れないたちだ。先にホテルで待っているお客さんもいるらしいけれど、それはとてもむつかしい。
「わ〜、やっとあえた」
きゃっ、不意にルイくんが背後から抱きしめてくる。甘いミルクのような香りが以前の快楽を思い起こさせる。あっ、ま