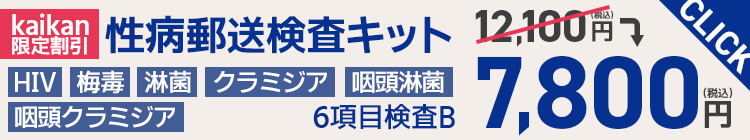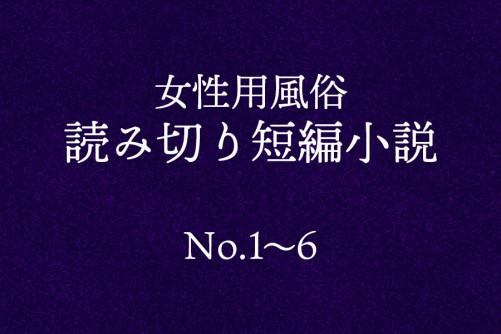
【女風小説】1話~6話|1話数分の読み切り短編サイズ
~こんなのはじめて~
30歳。独身。
と、ここまではまだいい。あたしのまわりにも大勢とはいえないけれどそれなりにいる。しかし……。大きな声では絶対にいえないこと。
あたしは生粋の処女なのだ。
もちろんキスもしたことがない。憧れはあるし、夢の中に至ってはたくさんのイケメン(芸能人とか、会社の中村部長とか、宅配の人とか)と乱れに乱れた。朝起きて陰部から愛液が滲み出ていたことなど幾度もある。男性でいうところの『夢精』だろうか。こんなに性に貪欲で興味もあるのにどうして今まで処女だったのだろう。と、最近とても強く思うようになった。
女子校育ちで女子大にいき、あげく三人姉妹の次女と来て両親は離婚をし母親に引きとられた。あるていどのお嬢様で(祖父が会社経営)門限もきつく男性の入る余地などまるでなかった。そんなこんなで処女のままきてしまった。
「ねぇ、みさ!」
「ん?」
同僚のようちゃんと社食でお昼をとっている。ようちゃんは快活で華奢だし顔がなにせ小さい。あたしとは真逆だ。性格も容貌も。
「あのね、あたし最近ハマってるものがあるんだ」
ようちゃんは少しだけ声のトーンを落としつつあたしの耳のそばで話し出した。社食を見回す。もうほどんどの人は食べ終わってどこかに散らばっている。
「え? なに。なに。今度は」
ようちゃんの『ハマり』は毎週変わるので。つい口にする。
「そうそう。今度はね……」
まあどうでもいいことが多いので気もそぞろだ。けれど今回だけは興味をそそられた。
「女性向け風俗店があるのよ!」
あたしは、うむ? と唸ってから首をひねった。今日の社食はB定食の唐揚げ定食だ。ようちゃんの唇は油ぎった唐揚げでテカテカしている。
「でね、あたし毎週お気にをね呼んでいるのよ」
ようちゃんは前のめりになって付け足した。
かいつまんでいうと、最近女性のためにある風俗店が流行っているとゆう。
女性が男性をホテルないし自宅に呼ぶとゆう逆デリヘルとゆうことだ。ようちゃんは自分の気に入りとゆう『ゆうま』とゆう性感ホストの写真をスマホ越しに見せてくれた。
「わ!」
思わず声をあげてしまった。
「でしょ?」
「うん」
あたしたちは声に出さなくても会話が成立していた。『ゆうま』とゆう画面越しの人は王子様のような顔立ちで俗にゆうイケメンだったのだ。
「この人がきちんときてくれるのかな?本当に?」
あまりにも信じられなくて再度確認をしてみる。ようちゃんは、もちろんよ。でなきゃお金払ってまで呼ばないわよ。あはは。結構大仰に笑った。余裕な笑顔はあたしに安堵と勇気をあたえた。
「ふーん」
興味希薄そうにしてみたけれど、興味深々でサイトのアドレスを脳内にインプットし、「あ、ちょっとトイレ」と、立ち上がって、トイレに駆け込むや否や、サイト名を打ち込んでサイトを早速観覧をした。時間がもうあまりなく《お気に入り》に登録をしスマホをスカートのポッケにしまいようちゃんのもとに戻る。
「さあ、行こっか」
ようちゃんの掛け声と共にあたしたちはお昼からの仕事に戻る。こじんまりとしたあまり光のささないオフィスに。
あたしはきっと今日仕事が終わったら早速電話をするだろう。
そう考えるだけで下半身がうずうずと疼く。
午後からの仕事はいつもやる気がないのにやる気になっていた。データ処理があたしの仕事。
あたしだっておんななんだもん。はじめての感覚にうっすらめまいをおぼえた。
仕事が終わりコンビニに寄って缶チューハイと唐揚げ弁当を買って帰路を急ぐ。お酒は毎日飲んでいる。お酒がないと眠れないのだ。さみしいのだろうか。ようちゃんから聞いた出張ホストのことが気になって夜空に神々しく大きくなって存在を誇示している満月など見向きもしないでカギ穴にカギを突っ込んだ。
毎日毎日パソコンと対峙している仕事なのでなるたけうちではパソコンを開きたくなかったけれど今夜は違った。先ほどお気に入りに登録したスマホの画面を開き、パソコンに名前を打ち込む。
小さい画面よりも大きくうつしだされた『出張ホスト』たちはおどろくほど鮮明だったし、リアルだった。
ブログを書いているホストも多数いてその中でも好きな物お酒一般。と書かれた【アルト】とゆうホストに興味を惹かれた。
年齢は31歳。175センチ。70キロ。趣味は酒。あたしは最後の酒のあたりで缶チューハイをおもわず吹き出した。
口元だけを隠している写真。けれど見るからに好感が出来る顔に違いないと感じた。趣味も好きな物も酒だからだろうか。共感する部分が同じだとゆうところでかなり安心感がある。あたしはざっと彼のブログに目を通し、お問い合わせメールでアルトさんを呼びたい旨を伝えた。
メールでの対応は迅速で早々と会う日にちが決まり場所も、時間もあたしが指定したところになった。
一人暮らしだけれど最初はビジネスホテルにした。ようちゃんにいたっては二回目からは自宅にしたと言っていた。
年齢にそぐわないけれどチエックのミニスカートと黒色のダボっとしたパーカーにした。スカートなど滅多にはかないので足元が心もとない。あたしは多分、いやものしごく緊張をしている。
ホテルはツインに一泊でとった。先にホテルで待つ。心臓がバクバクなって落ち着かなくて喉がいやに渇く。買ってきたペットボトルのお茶の蓋をあけ渇きを潤す程度に口に含む。初めての体験は後10分後には始まる。あたしはまたお茶を口に含んだ。
「こんばんは」
夜の7時。
ぴったりに来たアルトさんはネットから飛び出してきたように軽やかに挨拶を交わし、笑顔のお面を貼り付けあたしの目の前にあらわれた。
「あ、わ、あっ、」
言葉が喉に突っかかってうまく声が出せない。じっとあたしを見つめる彼は予想以上にイケメンだった。とゆうかイケメンすぎた。
「よろしくお願いします!」
「あはは。こちらこそ」
緊張しすぎると声も出なくなるんだな。そんなことを思う。あたしは一応言っておいた方がいいだろうな、とゆうことをまず切り出した。はーっと息を吸う。
「みさです」
「はい。みささんですね」
すぐに返されてしまい、わ、女慣れ、と思ってしまう。なので続けた。
「あのぅ、きっとあたしのような女性はいないかと思います。メールでも書いたのですがあたし処女なんです。で、キスもしたことがありません……、な、」
「え? それがどうしたの?」
なので、いいのでしょうか。とゆう言葉は遮られてしまいあたしはいつの間にかアルトさんに抱きしめられていた。
「あっ」
驚いて声を上げる。ムスク系の匂いに包まれる。アルトさんはとても華奢に見えたけれど胸はかたかった。男性の胸ってこんなに温かいんだ。あたしはすでにうっとりと満足だった。
「シャワーをしてきて。部屋はね暗くしておくから。安心して」
「はい」
頭の上に優しい声が降ってきてもう安心感しかなかった。ここで恥じらっても仕方ないしなにせ今はあたしとアルトさんだけだ。たった二時間の恋人。
シャワーから上がると清潔な真っ白なシーツに赤色のバスタオルが敷いてあった。
「裸でうつ伏せになってね」
「あ、はい、」
ちょっとだけ恥じらいつつも誘導されて裸体のままうつ伏せになる。
真っ赤なバスタオルからもムスクの匂いが鼻梁をかすめる。ああ、もうどうにでもして。あたしは身体の力が抜けてゆくのを肌で感じた。
「リラックスしてください。僕に身を任せて」
あたしは顎だけを引きうなずいた。オリーブオイルをベースにラベンダー油を調合したマッサージオイルが背中を滑ってゆく。アルトさんの手はとても柔らかい。まるで女性の手のように。ゆっくりと背中を滑ってゆく手が意地悪に胸スレスレのところを何往復もしている。
「あっ、」
あたしは腰を少し浮かしつつ声をひっそりとあげた。躊躇なくお尻を撫でてゆく魔法の手。あたしの子宮はかなり疼いている。お尻の割れ目にオイルが垂れる。吐息は甘みなものに変化をしてなすがままに愛撫をされた。
「おもて向きになってね」
腰をくねらせうつ伏せから仰臥の体勢になる。空気にさらされた乳首がトントンに尖っていて痛いほどだった。
「わ、みささん、乳首がピンクだ。かわいい」
そんなことをさらっといいながら愛撫を執拗にされるも全く痛くないしむしろくすぐったいくらいだ。陰部は腫れ物にでも触るようとても優しく指先で突かれた。
「あ、そ、そんなぁ」
おしっこがしたくなる。きっと豆を弄っている。ああ、もっと。なんて気持ちがいいの。指先が上下左右にゆったりと行き来しているうちにあたしは絶頂を迎えた。人の手によっての絶頂はむろん初めてだった。愛液が太ももを伝うのがわかる。
豆がドクンドクンと脈を打ちそこが心臓になったかのようとても敏感になっていた。
膣には決して指をいれなかったのはあたしが処女とゆうことを知ってだろう。
「処女はね指を突っ込んでも破れないけれど、でもね、処女だからこそ好きな男性と行為を持ってほしいんだ」
アルトさんはそっと唇を噛む。
「あ、もちろんファーストキスもね」
キスもしたことがないあたしにそう付け足す。
「あたし、アルトさんがファーストキスの相手でもいい」
心からそう思ったので口にした。え? アルトさんは口をポカンとあけ、あはは、と、また笑った。なんで笑うのかな。だって、みささん子どもみたいなんだもん。あはは。あたしたちは気を許したカップルのようたくさん笑った。
「ありがとう」
あたしはやっと女として生きていけるような気がした。
「みさ、最近なんだか綺麗になったんじゃない?」
「え? わかるぅ?」
あれから二度程アルトさんを指名しその後から急にモテ期がきて今は会社の上司と密かに付き合っている。
「あたし、女でよかったよ。ようちゃん」
「はぁ?」
わからないなぁ。とゆう顔をするようちゃんもとても綺麗な顔をしている。女って男とゆう潤滑油がないと綺麗になれない。きっと。
あたしはこの先も恋愛を楽しみたいし綺麗になりたい。
お腹が空いたなぁ。もうすぐお昼のチャイムが鳴る。
〜あっちもこっちも〜
なにをしても物足りなく息苦しい毎日を過ごしている。生きているのか死んでいるのかもよくわからない。
惰性で仕事をし、煽るように酒を呑み、リア充そうに綴られているSNSに毒づき、あたし綺麗でしょ? みて、みて! とゆうのを誇示している嘯いたインスタの写真を見て、アホくさと嘲笑をしてみたり。
見なきゃいいのに。とも思うけれどそうゆうことをする人間を可哀想だ。病んでる。と、同じ同胞がいるんだとどこか安心しているあたしがいる。
付き合っている男とのセックスは最低だ。せめて、男が性に真摯に向き合ってくれもっとあたしを喜ばそうとゆう努力をしてくれたならば、こんな世界全滅のような絶望感を味わうこともなかろうに。
セックスの最中に
「どう? 気持ちいだろ?」
「俺のペニスはどうだ?」
「俺のこと好きって叫べよ」
行為の最中に会話を求めてくる。言葉をねだる。そうしてたまにクスクスと笑ったりする。その笑いがどの類の笑いに属するのかがわからない。
下手なセックスでも感じているふりをしているのに、男はまるでそのような思考など持ちわせてはいない。あたしが股を濡らすのは、そうゆう体質だからだ。男はすっかり勘違いしている。
けれど、そんな女の気持ちもわかっていない男でも別れたらきっとさみしいはず。身体だけで付き合っているわけではないのだから。
あたしたちはもうさほど若くはないのだ。
いつからなのだろう。と、遠い記憶を彷徨ってみる。いつからこんなに性に冷めた女になってしまったのだろう。
来週、男は神戸に出張にゆく。
あたしはスマホを手にとって、電話帳を開き、【リアリティ】に電話をかける。《プププ》リアリティに電話をするといつも《プププ》とゆう変わった音がする。転送しているからね、と、以前マサキさんが教えてくれた。キャッチじゃないからさ、切らないでね、と、付け足して。
『あ、おつかれさまでーす』
コール3回ですぐに電話が繋がってマサキさんが開口一番に口にした。あたしは、クスッと笑って
『疲れてないけど』
意地の悪い女になる。マサキさんは、あー、そーですね。ゆりさん。甘ったるい声が耳に届き
『お久しぶりね』
と、言葉を添える。
『そうですよぅ。本当に。俺、会いたかったんですよー。ゆりさんに』でたよ。でた。あたしは、マサキくんのチャラけた対応にしばらく耳を傾ける。今日はマサキくんって感じじゃない気分なの。話が一旦落ち着いたあと、そう続けた。
『え? 僕じゃあないっすか?』
マサキくんはあきらかに落胆が隠せない様子だった。一人称が『俺』から『僕』になっている。
『若くなくてね、おじさんがいいの。そして2人で来て欲しい。確かあったわよね? 2人を呼べるデラックスコース?』
『はい。ありますよ。んー、おじさん、ですかぁー?んー』
電話の向こうで眉間に指をあてがい悩んでいるマサキくんの顔が浮かぶ。かわいい顔したマサキくんにはもう何度も裸を見せている。
かわいい顔だけでまだ大人の魅力は持ち合わせていない。今はまだ勉強中だとゆう。年齢を重ねるほど女がわかってくるわ。そう諭したけれど、そうでもない男もいるから、若いときの性体験は将来においてとても大事な基盤になる。性感ホストの仕事はきっと将来的に役立つとさらにいい放った。
『わかりました。いつですか?』
『もちろん、今夜よ。自宅に来てくれるかな』
はい! わかりました。最近入店したダンディーな男性をご堪能くださいね!
マサキくんはまるでどこかのアナウンサーのよういいきって通話を終えた。
ダンディーか。別にダンディーでなくてもいいし、てゆうかあまりイカしてない方がいい。あたしは逆の期待に胸を焦がし、ハイボールを三本買って帰路を急いだ。
あたしは先にシャワーを浴びて寝室にお客さんようの布団を敷いてうつ伏せで待っている。
まどろっこしい前戯話などは要らない。鍵を開けてあります。奥の部屋に裸でいるので勝手に上がって勝手に始めてください。とゆう要望もマサキくんに話してある。
『ゆりさんってほっんとうに〜かわってますね』
マサキくんのときも初っ端からそうだった。最初にあーだのこーだのと私情を絡めた話をするといつの間にか打ち解けてしまい、エロティックな世界が台無しになってしまう。お互いが知ることが性感帯だけでいい。あたしはお金を払っているのだ。癒しなどは皆目求めてはいない。
夜の8時過ぎ。玄関の開く音。バタバタとゆう足音。おじゃましますー。とゆう太い男のひそひそとした声。
薄暗い部屋に人の匂いと気配を感じる。
「ゆ、りさん、じゃあ、早速施述をしていきますね。あ、僕らはシャワーもしてきていますし、ご要望に添えるよう小道具も持ってきています。アオイと申します」
声の感じだと30代〜40代前半だろうか。
「僕はマサトです。三十路です」
「え?」
あたしは驚いて声をあげ、ついでに身体も上げた。
あ、すでに裸だ。今さら、隠すこともない。けれど……。
2人を見て、やられた、と、内心で思った。マサキくんたらぁ。二人ともおっさんどころかあたしと同じ年くらいで同級会か! と突っ込みたくなった。
「あ、お願いしますね」
あたしはもう身を委ねるしか選択はなくなる。2人の性感ホストはゆっくりと手のひらで背中を撫でてゆく。パウダー性感か。粉はオイルよりも滑りは悪いが肌触りがいい。
いつもは2本の手で触られる。けれど今はその2倍。うつ伏せでわからないけれど、一人は頭の上にいてもう一人は脚の方にいる。手のひらはおもしろいようにフェザータッチを繰り返し、やはりあたしの下半身からは液体が降りてくるのがリアルにわかる。濡れやすいたち。あたしはどうしてこんなにも潤うのだろう。腰のあたりを浮かして太ももをこすり合わせる。
あっけなく仰向けにされる。目をきつくとじる。おじさんたちがしている、と妄想をする。頭の中を妄想で満たす。トントンに尖った両の乳首が同時に温かい温度に包まれ舌先で飴を舐めるように転がされる。あっ、愉悦の声がつい洩れる。薄目を開くとあたしの胸に2人の男のつむじがあった。ネロネロ、ジュルジュルと乳首を弄ぶ。ああ、どうしよう。どうしよう。尿意は快楽と捉えることができる。子宮がわななく。あたしは、「あん、もっときつく吸ってーぇ」かすれた声で叫んでいた。
一人は下半身にゆき、股のあわいにそっと侵入してくる。脚を持たれゆっくりと開いてゆく。ああ、綺麗だ、感嘆の声が聞こえ、その瞬間、割れ目を舌先でなぞられた。きゃ、また、声が洩れる。
「声、出してもいいですよ。気持ちがいい時は声を出すべきですよ」
あたしは、目をつぶりながらうなずく。それからはダムの決壊のよう声を出しまくった。陰部を攻められ、同時に乳首を転がす。デンマを充てがわれ、そのときは、2人に乳首を吸ってもらうよう懇願した。
乳首とくりとりすがリンクをし、あたしは外イキを何度もした。デンマを充てがわれるうち、潮を吹いた。クジラになった。
終わりなどない。とすら思った。快楽は永遠と続きそうだった。セックスって男が射精をして終わる。それって一体誰が決めたのだろうか? あたしは、何度でもイケるし、もっとたくさん触って欲しいし、乳首を吸って欲しいし、足の指だって一本一本舐めてほしいのに。
「あれ……」
あたしは泣いていた。あまりにも感じ過ぎて涙が出たのか涙の意味すら不明瞭でよくわからない。
「時々泣いてしまわれるお客さんがいます。女性の快楽など底なしです。男は出せば終わり。まるで女性の性の貪欲などに気がつかない。男は身勝手な生き物なのです」
なにかのハウツー本の一文を聞いているようだった。あたしの子宮はまだまだイケそうだった。
「時間だね。ありがとう。シャワーは玄関のすぐ隣よ。してきて」
2人とも汗だくになっていた。汗なのかあたしの愛液なのか。はたまた潮なのかなんなのかも混じってしまいわからない。
「ゆりさんも。お体を流しませんか?」
あたしはちょっとだけ微笑んで首を横にふる。
「狭いの。ユニットバスなの」
ありがとう。そう、気だるい声音でお礼をいい、湿ったシーツに横たわる。
〜ワインごしのうそ〜
デーユースで入ったわりと豪奢なビジネスホテル。カーテンを全開に開けて、秋の緩やかな日ざしが憂鬱になるほど眠気をそそる。
素肌に清潔とゆう名前がしっくりくる真っ白なガウンを羽織って20階からの景色を独り占めをし、赤ワインを飲んでいる。
優雅すぎるし……。と、目を細めつつ思ってみる。
あたしは超金持ちのセレブで旦那はIT会社の社長。子供はまだいないけれど、旦那とは仲良しだし、海外旅行にはゆくし、奈緒は専業主婦家のことだけをしてくれればいいよ。え? お小遣いが足りない? なにが欲しいんだ。え? シャネルのピアス? そんならついでにバックや服も買っておいでよ。青山あたりまで出るんだろ? おっと、じゃあそこらへんで高級フレンチでも食べようか。ワインはやっぱり赤だよな。奈緒。う、うん。あたしはおそろしいほど蔓延な笑みを浮かべて目尻を垂らす。
と、ゆう妄想に浸ってしまうではないか。現実的にそのような暮らしをしている同性がいるのかと思うと蹴ってやりたくなるし、シャネルのバックを盗んでやりたくなる。
あたしは未だに独身だ。アラサーってやつ。アラサーちゃんなんてゆう漫画があったけれど、あの漫画に出てくる『アラサーちゃん』にあたしは似ている。尻と胸が無駄にでかい。色気などはないと自負しているけれど、会社(小さな印刷会社)のオトコどもの卑猥な視線にいつも犯されているのでお金を搾取したい。
彼氏もいなければ、特に趣味もなく、安月給はだいたい性感マッサージ代とホテル代と酒代に消える。異性に身体を触ってもらう至福はなにごとにも代えがたい。じゃあ、そこらの整体でもいいじゃないか。おじさんがひとりで切り盛りしている安い料金で施述をしてもらえるところでもさ。と、ゆうのとはまた話が違う。なにせ凝っているところから違う。肩や腰や脚の裏とか頭ではなく、心が凝っているのだ。心の凝りは普通の整体院では叶えられない。そこで流れ流れて行き着いたのが、性感マッサージの世界なのだ。
今日は有給で会社を休んだ。有給でって? なんだかせこく感じる。まことさんには「えっと、今日はね、さっきまで映画を見てお友達とランチしてきたんのよ。おほほ」と、いう気持ち悪い笑いも添えてそう話そう。まことさんには、『ちょっと金持ちなセレブ系』で通してある。嘘をついているのだ。小さな会社の事務員でオタクで友達が猫しかいなく、妄想で生きているなどと口がさけてもいえない。見栄を張るのも存外いやではない。あたしはこの時間だけはセレブになりきれるのだから。
コンビニで買ってきたワインを隠し、ちょっと高額なワインを窓際のテーブルに置く。冷蔵庫にはワイングラスを冷やしてある。よし、完璧。あたしは少しだけグラスに残っているぬるくてまずいワインを一気に飲み干した。
________
「どうですか? 最近お体の方は?」
「え、ええ。最近、夫にね肌が綺麗っていわれるのよ。おほほ」
とても気持ちの悪い声で笑う。自分でも吐きそうになる。まことさんは、それはよかった、と、鷹揚な声でつぶやいて
「奈緒さんはもともと肌綺麗ですもん」
背中にオイルを滑らせながら口もついでに滑らせる感じがしないでもない。上手にオンナ心を読んでいる。あたしの肌は別に綺麗ではない。汗疹も出来ているし、なにせ毛深い。
「ありがとう」
なんの脈絡のない言葉はあたしを素直にさせる。嘘のつきあい。けれど一体あたしはなにに嘘をついているのだろう。なんの利害もない相手にまで嘘をつくし、見栄を張る。なんで。まことさんの他のお客よりも見栄え良くうつりたいし特別に見られたいからなのか。わからない。
「あのね、まことさん」
今は脚にオイルを垂らされている。訊きたいことがあって呼びかけた。
「はい」
さすがにプロ。口を動かしつつ手も動かす。あたしは続ける。
「あのね、こんなこと訊いても本当のことをいわないってわかっているのね、けれど、ひとつだけ質問です」
「はい」
「彼女いるの?」
そう言葉にした途端、まことさんの手がとまる。ええ? 図星だったの? まことさんは嘘をつけないタイプに見えるし。3秒くらい、いや4秒くらい間があって
「いないですね。今は。仕事で必死ですし。なにせ余裕がありませんよ。女性は奥が深い」
そう。あたしは短くあまり深入りしない程度にこたえた。
「もし、あたしが彼女だったら、嫉妬で狂いそうね。きっと」
え? と、小さく声がして、あはは、と、まことさんはおおげさに声をあげて笑った。
「奈緒さんだって旦那さんに内緒できているでしょ? 最後まではないにしたって、男性に身体を触られるとゆう時点で僕だったら嫉妬ですよ。逆に」
へー。あたしはまた興味なさげに聞き流した。
彼女がいようがいまいが嫁がいようがいまいが、性感マッサージの仕事は特殊なので特殊だからこそ気を使うのだ。あたしもまことさんのなんとなく背負っているものがわかるような気がしないでもない。
仰向けになるとまことさんは胸を隠す。大きな胸は自慢でもないが乳輪もデカイので最初に胸はNGだと伝えた。えー。そんな女性初めてだし。まことさんは最初おどろいていた。さして乳首は感じないし、とゆうのはまんざら嘘ではない。
白魚のような指で陰部をなぞられる。ゆっくり、ゆっくり、そしてしっかりと陰核をさわる。あん、腰を浮かしながら声を上げ、下半身がまるで別の生き物にでもなったみたいに浮遊する。ローションを垂らされあたしの股の中に腕を入れ腕で陰部を愛撫する。何往復もする腕に他意はなくただ快楽を与える武器になる。挿入などおまけにすぎない。愛撫がしっかりしていれば、あたしはどこまでもイケるのだし、オンナであることを確認できるのだから。
「ワイン飲まない?」
「ええ、少しなら」
施述を終えたまことさんがはがすがしい顔をしている。ああ、終わったとゆう達成感と安堵感なのだろう。多分夜は、一杯やるかぁ! と叫んでいそうだ。
はっ! 窓際に置いてあるワインは高価ではあるが、見せもの化したワインに成り上がてしまい冷蔵庫にしまうのを忘れていた。なんでまたこんなときに見栄を。見栄晴? あたしは急に笑いがおとずれて、クスクスと笑う。
「てゆうか、僕テーブルの下に置いてあるワインの方が好きなんですよ。奈緒さん」
まことさんの顔をまた見る。やっぱり嘘はついてない目だった。あたしは顔から火がでそうになるも、出てしまい、顔を両手で覆い
「やだぁ、やだぁ、もう、もう、」
〜このまま・ずっと〜
「あのさ、明日からあたし熱海に出張なの」
目の前にいる夫は好きなものを後に食べるタイプで大好物のエビフライがまた手付かずでいる。タルタルソースは手作り。あたしは料理も好きだし、夫も申し分ないくらい好きだし、猫のアンコも好きだし、小柄でぽっちゃりでちょっとだけ大根足の自分も好きだし、会社の野々山部長も好きだし世の中は好きなもので溢れている。
へー。そうなんだ。夫はあまり感心のない声を出し、あたしを一瞥したあと、再び箸を動かしいよいよメインのエビフライをつまんだ。
「お土産よろしく」といってからエビフライをほおばる。うめー! さすが、尚美のタルタルソースは最高だな! と、本当にうれしそうに褒め称えた。
「うん。温泉まんじゅうかってくる」
「またぁ? 地酒もね」
うん、あたしはうなずいてエビフライをほおばる夫を見やる。口の端にタルタルソースがついている。教えてあげようか、それとも、ねぇ、ついてる。などといってから背後から寄り添って唇を舐めようか。ふと、どちらかを思い浮かべる。
夫はあたしよりも5歳下だ。あたしは今年42歳。夫は顔立ちも整っているし、優しいし、真面目だし、嫌なところがひとつもない。ないのに、どうして一緒に暮らすとセックスとゆう最大級のコミュニケーションがなくなってしまうのだろう。準備もなしで急に唇を舐めたら怒るだろうか。それとも嬉しがるのだろうか。まるで検討がつかない。
夫と最後に寝たのはいつなのかが思い出せない。夫は他に女が、いや、セフレが、いやいや、彼女が、やだぁ、いるのだろうか。頭の中が渦を巻いている。
夫はあたしがセックスなしで平気だと思っている。な、わけないじゃないか。したくて、したくて、昨日など、宅配の兄ちゃんを襲って犯したし、それから会社の上司でもある野々山部長とは立ちバックでセックスをしたし、コンビニの定員の古淵くんとはカーセックスをした。古淵くんは若いので2発発射した。あたしの膣は完全にぽっかりと穴が開き、男どもが皆中だしをするものだから膣からはイカの匂いが充満をした。
「ごちそうさま」
ハッと我にかえる。あまりにも欲求不満が過ぎてあう男あう男と妄想でセックスをしまくっている。理性があってよかったなぁ。と、胸を撫で下ろす。
『あのう、セックスしませんか』
などとあう男あう男に声をかけていたら警察に捕まるか、こいつ頭大丈夫か? などといわれて精神科いきだ。
「はーい。一泊だから明日の夜は適当に食べてきてね」
「うん、わかった。風呂入って寝るね。お先」
「うん、おやすみー」
夫の背中に声をかけあたしは洗い物をしだす。明日は一ヶ月ぶりのデートだ。ずっと楽しみにしていた。熱海なんてどうかなぁ。温泉街の提案をしたのはあたしだ。今夜楽しみ過ぎて眠れないかも。まるで小学校の遠足の前の日みたいにあたしの思考は完全に小学生になっていた。夫にはまるで後ろめたさなどはない。あたしが稼いだお金で遊ぶのだから。お金とゆうのは心は決して買えないが、肉体は買うことが出来る。世の中金じゃー。それはまんざら嘘ではない。
あたしはいつも現地集合、現地解散にしている。今から来るのは、
【マダムお助け隊】
とゆうサイトから選んだ気に入りのたけしさんだ。いわゆる彼氏代行業みたいなシステムで一泊になるとそれに価する時間給と交通費に食事代ホテル代などがかさむ。前金制になっていてすでに料金は振り込んである。
目に見えない相手だから約束をすっぽかすおそれがある。なので前金制はいいことだと女のあたしでも思う。実際、前金制にしたら急に緊張していくのが躊躇われてもいかないと損だ。とゆうことにおいても理にかなっている。
あたしは熱海駅のホームに座ってたけしさんを待つ。待つのは嫌ではない。待つこともプレイの一環だと思う。だってこんなにドキドキするなんて滅多にないことだから。
「あー、尚美さん、もういらしたのですか」
新幹線が目の前で停車し、その2分後にたけしさんが声をかけてきた。あたしは、昨日からいるの、あまりにも楽しみだったから。と、口を尖らせていうと
「ええ! 本当ですか? だったら僕も前乗りで昨日きましたよ」
内緒でね。と、笑って付け足す。え? 本当に内緒で来るの? いやいや、来ないだろうよ。口がうまいなぁ、てゆうか信じているのだろうか。
「いやぁ、嘘だけど。さっき来ました」
ですよねぇー。まことさんは、尚美さん面白すぎるぅ、と、目を細めて笑った。白い歯が嘘くさい笑顔を引き立たせるも、50歳とゆう年齢にしては茶目っ気たっぷりな紳士さが好きだ。
「行きましょうか」
まことさんは右手を差し出す。あたしもその手に自分の左手を乗せた。恋人つなぎをする。心地の良い風があたしたちの間をすり抜けてゆく。無骨な手が大人の男だ。
ホテルは熱海では有名なホテルにした。待ち合わせが3時とゆう半端な時間だったけれど、チエックインは出来るので先に温泉で汗を流すことにした。
「一緒にお風呂にいきましょう」
「ええ。出たらそこの休憩所で待ってますね」
ホテルの浴衣を着て一緒にお風呂にいくだけで陰部が濡れそうだ。エスコートの上手なたけしさん。そういえば彼は独身なのだろうか。会うのはこれで3度目だけれど、彼のことを何も知らない。
お湯はとにかく柔らかくて身体は火照って陰部も火照った。酒を飲む前に濃厚な愛撫をしてもらわないとならない。愛撫だけでもいい。早く触って欲しい。見た目は人間なあたしだけれど、中身は歩く性器だ。
休憩所にたけしさんがいてスポーツ新聞を読んでいた。あちゃー。これはいかんやつだ。なんて素敵なの。浴衣でスポーツ新聞が似合うのって、たけしさんと、マスオさんくらいじゃない? は? たけしさんはあたしに気がついて手を挙げた。わ、まぶしい。冷静に、あたしは性器から人間に戻って牛乳を買った。
部屋はまだ布団は敷いてないけれど
「お願いよ。強く抱きしめてぇ!」
あたしは着ている浴衣を脱ぎすて座布団の上に寝そべった。性急だなぁ、と、たけしさんの冷笑。それでももう我慢ができなかった。陰部から愛液が滲み出ているのがわかる。あれ? もう濡れてるよ。細い食指があたしの割れ目をなぞる。
「ああん、もっと、弄って。お願いよ。ずっとオナニーを我慢していたのよ」
どうでもいいことまで口に出てしまい、けれどもはや恥じらいなどはない。ヌルヌルと愛液が湧き出てくる。たけしさんはおもむろにローターを取り出して豆を剥いてあてがう。無機質な機会音が部屋に響きあたしの嬌声も負けじと響く。挿入がないことを除けば、キスはするし、舐められるし、もっと舐めてといえば舐めてくれるし、てゆうかもっと舐めてと何度も懇願しても舐めてくれる。陰部がふやけるまで舐め、溶けてしまうのではとか考える。陰部は塩を振ったらなめくじのよう溶けてなくなりそうないきおいだ。
なくなってもいいし、このままずっとなにもかも忘れて快楽の湯に快楽のぬるま湯に浸かっていたい。
【湯の花】が急に脳内に浮かびあがる。どこの温泉だったか。夫と一緒にいった温泉で初めて湯の花を見た。黒くてまるでゴミのようで汚いものに見えたけれど神秘的でそれでいていい成分が抽出されていると触りたくなった。
手にどきそうで手に届かない存在。けれど欲してしまうその指先。
たけしさんはまるで湯の花だ。
夕食時に酒を飲みすぎてしまい、べろんべろんのあたしをたけしさんは渾身的に介抱してくれたようだ。朝方、頭が痛い中起きたら、たけしさんの顔に疲労の影が見えていた。
「とーってもたのしかったわ。このままたけしさんと駆け落ちしちゃおっかなぁ」
へへへ。あたしは笑って肩をすくめてみせた。
「いいですよ」
え? いいの?
あたしたちは大笑いしながら駅までの道を歩く。来た時と同じように恋人つなぎをして。あなたがなにものでも構わない。なにものでもないから楽しいし、夫にだってもっともっと優しく出来る。
〜あなたがほしい〜
50代くらいの夫婦ってセックスをしているのかしら……。
夫と買い物にいくたびに同年代の夫婦を見るとついそう思ってしまう。
子ども達も皆成人して手が離れるとまた以前のように2人の時間がおのずとおとずれる。
子ども達が家にいたころは子どもがなにかと潤滑剤になっていて会話もまあまあ、いや、盛りだくさんあったけれど、いざ2人っきりになると会話がちっともないことに気がつく。
明日、雨だから傘持っていってね、とか、今日ね仕事先で失敗しちゃったのね、とか、やだぁ、また太ったみたい、だとか。そんなありきたりな会話しかしないし、あげくセックスもめっきりしなくなった。
そんなもやついて鬱積していたあたしを悟ったのか夫がとんでもないことを白状した。
「俺さ、風俗にいってきたんだ」
この人は唐突になにをいってるんだろうか。頭がおかしくなったんじゃないのだろうか。妻を抱かずに風俗にいってきたって。なにそれ。慰謝料、慰謝料、憤りを通り越して頭の中では一気に電卓を叩く。あたしは銀行に勤めている。電卓は左手で叩く。猛烈な速さだ。
なんて言葉を返していいのかわからずに黙っていると
「でな」と、前置きをして感情のこもってない声音で話しを続けた。
「風俗にいったなんてさ、普通の旦那ならいわないだろ。いった意味がきちんとあるからお前に聞いてほしいんだ。お前が好きに決まっているし、お前とこの先もずっといたいと思っている」
「……、じ、じゃあ、なぜ? なぜなの?」
うつむく夫のつむじのあたりがかなり薄くなっていることに気がつく。夫は今月56歳になったばかりだ。あたしは声をふるわせ詰め寄った。
「勃起をしないんだよ。てゆうか精子もでないし、全く勃たない。役に立たないんだ」
え? 思わず声が出た。全く勃たない。役に立たない。って、勃たないと立たないってなにかの比喩なの? てゆうか冗談にしてはおもしろくないし、けれど役に立たないのはどうでもいいけれど、全く勃たないなどとゆうのは非常自体だ。
「だから、お前をこわくて抱けなかったんだよ。ここのところ」
かなりの落胆気味にあたしまで物悲しくなった。ここで、いいのよ、おとうさん。あなたがいてくれるだけでいいの。そんなこと気にしないで。もう、だったら先に話してくれればよかったのに。あたしがうーんとサービスしちゃうからぁ。と、喉の先まで出かかったけれど、風俗嬢さんを前にしても勃起しなかった。などといわれてしまってあたしはかなり憂鬱な気分になる。あたしも風俗で働くか? いやまてよ。銀行はバイト禁止だ。って、違う、違う。あたしはかなり混乱をしているようだ。
「病院は? 行ったの?」
夫は、恥ずかしくていけないよ、と、自虐気味に笑う。風俗にいくまえに病院にいけよ、そう突っ込みをいれたかったけれど、なんとなく夫の羞恥心が垣間見えて、そっか、としか言葉が出なかった。
「でな」と、またなにかを思いついたように前置きをして話しだす。
「お前が寝取られる所を見たら勃つかもしれないんだ」
なにそれ? 意味がよくわからないことを言い出す夫の顔を見ると嫌に真面目な顔だったので詳細を聞くことにした。
商売(プロ)の男の人に頼むんだよ。お金をきちんと払ってさ、お前をイカしてもらうんだ。俺の前で見ず知らずの男に触って舐めてもらうんだ。浮気じゃない。俺の要望だ。風俗にいったのも浮気じゃないよな。それに付随しているんだ。わかるか? 俺の前だからといって痴態を晒すことに対して遠慮をすることなどはない。俺が望んでることだ。どうだ。いいだろ?
いいだろ? いいの? 逆に。あたしだって性欲もあるし、この先男のかわりに大人のおもちゃとか絶対に嫌だし、浮気とかも勇気がないし、いいだろじゃなくて、いいよな? と、いい切ってくれたらいいのに。
「わかったわ」
あなたの為だし、と、一言付け足しつつ心では未知なる世界に高揚をしていた。
「これは、これは」
数日後。夫は同じ歳ほどの男性を連れて帰ってきた。
「お綺麗な奥様ですね」
男性はあたしを見るなり開口一番で世辞を口にした。うーん、慣れている。さすがだわ。これが噂の出張性感師なのね。夫からはすでに男性性感師が来ることを聞いていたので心の準備と布団の準備と部屋の準備とそうして陰毛のお手入れまでしてあった。
「まあ、お上手ね。今夜は主人のわがままですみません」
夫は、まあ、立ち話しもなんだし、と、いいながら男性性感師を部屋の中に招き入れた。子どもたちが巣立ってからリフォームしたので割合部屋は小綺麗だ。
テーブルを囲んであたしと夫と性感師はとりあえずほうじ茶を啜った。
「あらためまして、僕は、ヒカルともうします。48歳です」
性感師が名前と年齢とゆう簡単な自己紹介をした。同い歳だったのでびっくりした。なんだろう。この落ち着きは。この人は結婚をしているのだろうか。旦那が性感師だったら嫌だなぁ、と、考えていたら
「バツイチです。僕は。で、この店をやり始めました。女性だって癒されたいし、結構需要はあります。こうやって夫婦さんにも呼ばれますし。うーん、なんだろう。僕がこう2人にとっての愛液みたいなものですね」
はい、と、雄弁な口調で説明をする。
「納得」
あたしと夫は同じタイミングで言葉を発し、顔を見合わせケラケラと笑った。
「おお、仲がいい」
ヒカルさんもクククと笑う。笑い皺がかわいいと思った。
「じゃあ、えっと、旦那さん、はじめましょうか?」
「ええ」
2人の男達はアイコンタクトで号令をかけあった。
寝室に移動しあたしはいわれるままベッドに横になった。シャワーは済んでいるし、裸にガウンなので脱いだらすぐ肌を晒すことになる。夫は寝室にある鏡台の椅子に腰掛けている。いつもは空気みたいな存在なのに、今はそこにいないでくれと思う。夫の勃起が治るか治らないかの治験みたいなものだ。けれど、はっきりいってその目が疎ましい。
目をつぶっていても人の気配は感じるもので、おでこに温かい唇の温もりを感じ、ああ、はじまったんだな、と、ぼんやりと思いながら下半身を熱くする。ミントの匂いが鼻梁をくすぐる。他人の匂いを久しぶりに身近に嗅いだ。夫ではない他人の匂い。柔らかな唇は滑らかに首筋から胸へと降りてきて、ハラっとガウンがはだけた瞬間、お山の頂がトントンに尖っていることに羞恥が芽生えた。頂のあたりに気配を感じ、ああ、舐められる、と思ったときすでにおそしで頂を舌先で転がされる。ああ、声が洩れる。喉を反らし、あああ、と、さらに声を上げる。
「なんだ、そんなに気持ちいのか? なあ?」
夫の声。夫は嫉妬心なのか興奮しているのかわからないけれど、明らかにあたしをアダルトビデオしかりの目で見ている。
前開きのガウンを全部剥ぎ取られ、あたしはいつの間にか、2人の男達に下も上も舐められていた。
「旦那さん、ほら、奥さんのここ。見てあげてください。ヒクヒクって」
ヒカルさんはあたしの陰部を躊躇なく夫に見せている。あたしは、あん、いやだぁ、と、いいながら両手で顔を覆った。
「す、すごい、ダダ〜に出てる。お前こんなに濡れるやつだったのか」
乳首を抓っているヒカルさんは、夫の男根に指を差して
「あ、勃ってます!」
まるで自分のことのよう大声をあげた。夫は、おおお! と、驚いでそれでいて、あっけなくあたしの中に男根を挿入した。
「おお、これこそ、愛の結晶です」
ヒカルさんはあたしの手をぎゅっと握って、まるでお産の立会いのよう優しい目であたしたちのセックスを傍観していた。夫はひたすら元気だった。抽送も今までにないほど能動的でそれでいて愛されていると感じた。
「で、出るー!」
一気に男根を引き抜いてあたしのお腹に精子を放出させた。これでもか。とゆうほど飛んだし臭った。
夫はあたしを抱きしめ、ありがとう、と、ささやく。まだ肩で息をしていて心臓が早鐘を打っているのに。ドクン、ドクン、と。
これがきっかけで勃起がきちんと出来るようになればいいし、風俗にいってもいいとさえ思った。男はセックスをしてこそ男だし、女を抱いてこそ男なのだ。生涯現役。男であるために勃起はしないとならない。
それ以降、月に一度はヒカルさんを呼んで、プレイをすることもあれば、酒を飲んでご飯を食べていくだけのときもあるけれど、楽しい宴会を開いている。
お金を頂いているから。仕事として来ているから。そんな紳士的なスタイルを全く変えずにぶれない、ヒカルさん。
あたしにも夫にも愛おしい存在になっている。
そしてあたしたち夫婦は前よりもお喋りをするし、セックスもするようになった。
〜もうひとりのあたしが〜
夕方の6時を過ぎると次々に値下げのシールがペタペタと貼られてゆく。それを待ち構えるよう並んでいる人間はほとんどが醜い風貌をしている。男も女もなく皆一様に同じ顔にも見えるし同じ宇宙人にも見える。いや、もしかしたら、あたしが地球外生物なのだろうか。あたしを見ると、気のせいかもしれないけれど、だいたいの人間は避けていくか、二度見をしてゆく。
「チッ、見んなよ」
あたしは、ひとりごち、人間達を睨みつける。睨み返す人間はいない。あたしははやり地球外生物なのだろうか。
値引きをされた惣菜コーナーに醜い風貌をした人間達と混じって買いあさる。ほとんどが3割引〜5割引だ。気に入りのかぼちゃサラダに半額シールが貼られたせつな、あたしは率先して3つ確保した。焼き鳥のぼんじり3本、牛肉コロッケ5つ、柔らか鷄の唐揚げ1パック、一口シュークリーム、手作り食パンにクロワッサン、ジャムパンに、クリームパン。カルボナーラスパゲッティにコーラー1・5ℓ2本とハイボールの500mlを3缶カゴに入れ、セルフレジに並ぶ。
人件費の削減なのか、最近はセルフレジが主流になっている。こうゆうせこい買い物をするあたしのような地球外生物にはしかしありがたい。こんな人間離れをした姿のあたしからの見切り品はありえない。なにせ普通とは違いおそろしいほど綺麗で華麗だからだ。モデルさんかなにか? などと声をかけられることもある。モデルのような姿をしている地球外生物のあたしは、セルフレジでお会計を済ませて、さささっとマイバックにしまいこみ涼しい顔をして出口に向かう。
『2,350円』
あれだけ買ってこの値段。コンビニで買ったならこの倍はするだろう。この安さもあって近所の汚いスーパーに買いにゆく。すがすがしい気分になる。これなら捨ててもいいし、さいあく盗まれてもいい品だ。けれど、実際これらの食べ物はあたしの胃におさまるものではない。
みつるさんを今夜予約した。その前にどうしてもしなくてはならないあたしだけの儀式。これを知ったらみつるさんは叱るだろうか。呆れるだろうか。はたまた殺してくれるだろうか。
出張性感ホストのみつるさんをネットでみたとき、頭のてっぺんから足のつま先まで瞬時に凍りついた。『ハルキ?』つい、声がもれた。
昔付き合っていた男にそっくりだったのだから。ハルキとは2年くらい付き合ったが、嫉妬深く、束縛系で、おもてに出て働くことも許されずあたしは狭いワンルームにほとんど監禁状態だった。けれど、そのアブノーマルな行為によってあたしは愛されているんだとゆう錯覚を起こし、ハルキ以外との接触は付き合っていた期間ほとんど避けていた。家の中にこもってすることといえば、セックスとテレビとユーチューブと排泄と洗濯と掃除と食べることに限定をされた。その中での優先順位はセックスと食べることだけだった。ハルキはあたしがおとなしくしていたら機嫌がよかったし、本当に優しく接してくれた。セックスも申し分なくよくて溺れたし、時間のない朝だって短くてもセックスは欠くことなどはなかった。
生理でセックスが出来ないときは最悪でその時だけ食に走った。一日中何かしら食べていたし、食べることでなにもかも忘れることが出来た。だから当然太る。ハルキは「美緒は痩せているからさ、もっと食べた方がいいよ」と、いって、仕事帰りに毎日食べ物を買ってきた。大好きなかぼちゃコロッケ、モンブランケーキ。部屋には絶対に食べ物があったし、冷蔵庫はいつもいつでも図書館にある本棚のように満タンに食べ物とゆう書物が詰まっていた。
そんなある日、ふと、鏡を見たらあたしじゃないあたしがそこにうつっていた。二重顎して目も一重で顔中パンパンで針をさせばパンクしそうなぶつぶつの顔の人間だった。
ハルキはあたしを太らせて売るつもりなのか? こんな醜いあたしでもかわいいとゆうのは普通ではないじゃないか。なので輪をかけておもての世界から余計に遠ざかっていった。ハルキがいる、あたしにはハルキがいる、なにもこわくない。そう念仏のように言い聞かせ毎日ぶくぶくと太ってゆくなかハルキの帰りを待った。
「えー。美緒ぉー。あいつはもういいや。俺はまた豚に餌をやりまくって肥えさせたんだぜ。まあ、俺の趣味かな。豚になっちまった豚はもう出荷しかねーよ。え? そうそう、デブ専のさ、ヘルスに売るってやつね。もう3匹養豚場に出荷したしな」ギャハハハー。
ハルキが帰ってくる時間だと思いたち、アパートの前で待っていたら、誰かと電話をしながらこっちに歩いてくるハルキを見つけ、声をかける前に、電話の内容を聞く気などなくても聞いてしまった。
「うそっ」
あたしはもっていたスマホをその場に落として呆然と立ちすくんだ。その後の記憶は曖昧だ。それを境にあたしは家出をし、ハルキの前から売られる前に姿をけした。
値引きで買ってきたものは全て封をあけその蓋の上に口の中に入れた食べ物を何度か咀嚼をして味わってから全て吐き出す。ゆっくりと味だけを楽しみ鼻から息を吐き出してくちゃくちゃのまま吐き出す。
過食嘔吐をしていたけれど、吐いても結果体内に食べ物蓄積されてしまい停滞期なのか吐いても太るようになってしまった。なので今は噛んで吐き出すことをひたすらとくりかえしている。一時間くらいかかるおもしろみのない無駄な食事。顎も痛いし唾液も出なくなる。コーラーで口を何度もゆすいで、ハイボールだけを胃のなかにおさめる。噛み砕いた食べ物はなんて無残で汚くてそれでいて憎たらしいのだろう。胃のなかに詰めたって同じことだ。ならば飲み込む前に出せばいい。あたしはこんな汚い生活を得てすばらしい身体を手に入れた。安く食べ物を買っているのもあって罪悪感はないし、むしろすがすがしささえおぼえる。しかし、寂寥感だけがあたしの心と身体を真っ二つに切り裂く。
なにが正解なのかがわからない。
あたしはみつるさんとの待ち合わせのビジネスホテルに向かう。なにごともなかったように、「あ、もう食事ね、済ませてきたの」などといいながらあたしは引きつった顔をして笑うのだろう。きっと。
「こんばんは」
紺のスーツに身をまとったみつるさんが、美緒さん、と、名前を付け足し挨拶をする。ハルキと顔は似ているけれど性格はまるで違う。紳士的だし、屈託ない笑顔はあたしだけのもの。この時間だけは。
「あいたかったの」
チェーン店のビジネスホテルは部屋が狭い。その声はとても大げさにきこえた。みつるさんは眉間にしわをつくり、首をかしげている。
「え? どうかし、た?」
あまりにも難しい顔をしているために質問をしてみた。それにしてもいい香りがする。
「……、えっと、美緒さん、また、痩せましたか?」
すこしだけ言葉を考えて発した言葉だったようだけれど、それ以外の言葉などはなく単刀直入ってな感じで声にした感じがする。
あたしは、ううん、痩せてなんてないわ、むしろまだ痩せたいくらいなの。だって豚でしょ。あたし。
えっ? みつるさんから笑顔はスーッと消え去り、たちまち涙目になる。まるで思いがけなく交通事故を見ちゃったよ! 的なおどろきの顔をして
「あまりにその身体ではかわいそうですよ。身体を大事にしてください。美緒さん。あなた、鏡を見ていますか? 一ヶ月ぶりです。前回よりも、悲痛です。何かお悩みでもあるんですか? 僕はあなたの味方です」
饒舌に話す言葉達がうまいこと頭のなかに入ってこない。ただ、『かわいそう』『だいじに』『かがみ』『ひつう』『なみだ』それらのどこかのうさんくさい小説に出てくる単語がパラパラと脳内で暴れまくる。
あたしは必死に首を横にふった。そしていった。
「あたしはけんこうできちんとしょくじを……、し、して、」
しています! といいたいのに喉の奥になにかが挟まっていていえない。
はっ、目の前が急に暗くなりムスク系の匂いに包まれる。広い胸。華奢に見えるけれど立派な体躯。あたしをすっぽりと包み込んでしまうその抱擁力。そして温かい体温を持った人間。あたしはどうしてだか涙を流していた。ロクに水分を取ってなどいない。ハイボールくらいだろう。水が苦手だしコーラーはうがいのためだけのもの。あたしの身体は一体なにで出来ているのだろう。胃にはハイボール以外一切入れてなどはいない。この一年であたしはすっかり変わったようだ。誰しもがあたしを好奇の目で見るのが今やっとわかった気がする。
きらびやかな夜景の見える大きな窓ガラスにうつっているみつるさんの中にいるその女は誰? その骸骨みたい、いや、もはや白骨化した女は誰なの?
あたしはその女と目が合ってお互いに睨み合っている。みつるさんはきつくあたしを抱きしめる。美緒さんもっと太って。死んじゃうよ。なにかつぶやいてはいるけれどまるで頭には入ってこない。目の前にいる女はみつるさんに抱きしめれている。ちっとも綺麗じゃなくそれこそ地球外生物みたいな女がそこに。目だけをぎよっとさせそれでもあたしを睨みつける。